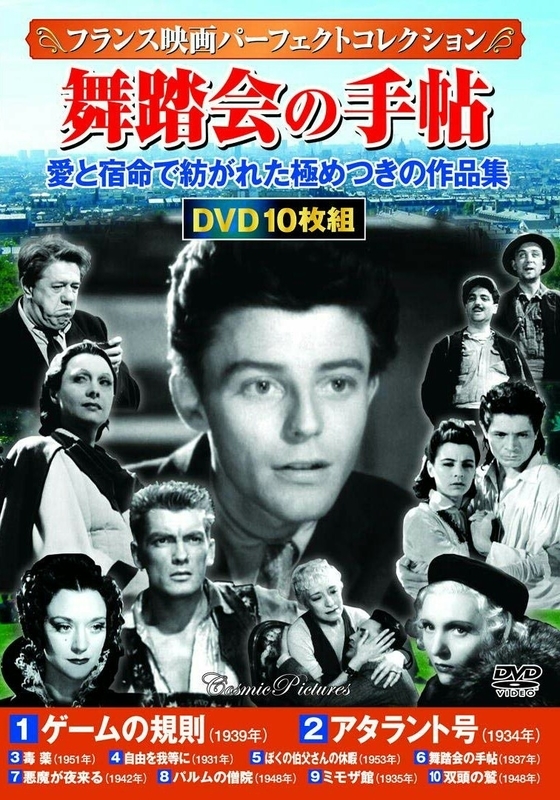
筆者もこのボックス・セットで学生時代以来に都直した作品もあり、当時めったに上映されず、近代美術館フィルム・センターならまだしも、映画マニアのための特殊上映会などではかろうじて英語字幕のボロボロの画質の民生用16mmプリント版で遠方まで出向いて観た作品も多く、上質な画質の日本語字幕つきDVDで気軽に自宅で鑑賞できる今では夢のようです。またこれらの映画も70年~90年あまり昔の作品なので(だからパブリック・ドメインになっているのですが)、現代の映像文化とははっきり違う、決して再現できない世界が映画の中にあり、今年作られた映画が2088年~2108年にも観られているかを想像すればそれは途方もないことですし、その時にはこれらフランス映画の古典作品も誰も観なくなっていて、映画自体が別の文化に取って代わられているかもしれません。それはさておき、今回も作品解説文はボックス・セットのケース裏面の簡略な作品紹介を引き、映画原題と製作会社、映画監督の生没年、フランス本国公開年月日を添えました。

『自由を我等に』A nous la liberte (Films Sonores Tobis, 1931)*83min, B/W : 1931年12月18日フランス公開
監督:ルネ・クレール(1898-1981)、主演:アンリ・マルシャン、レイモン・コルディ
・刑務所からの脱獄を図った囚人二人。一人は逃げきって、大富豪に。片割れは捕らえられ、再び刑務所に。相棒が刑期を終えて出所すると……。工業化社会への風刺と友情の素晴しさを描いたR・クレールの傑作。

[ 解説 ]「巴里の屋根の下」「ル・ミリオン」に次いでルネ・クレールが原作脚色した映画で、スタッフは殆ど全部右二作と同じ顔ぶれであるが、音楽は所詮「大人組」の一人、ジョルジュ・オーリックが特に作曲した。出演俳優は「ル・ミリオン」のレイモン・コルディ、舞台から来たアンリ・マルシャンが二人の主役で、フィルム・オッソの専属女優ローラ・フランス、及びジェルメーヌ・オーセエ、「ル・ミリオン」のポール・オリヴィエ、ジャック・シェリイなどである。
[ あらすじ ] 脱獄囚ルイ(レイモン・コルディ)とエミイル(アンリ・マルシャン)は官憲に発見され、ルイだけが成功する。利口なルイは世の中へ出てから忽ち出世して縁日のレコード売りから蓄音器店の主人、最後に大蓄音器工場の社長となる。一方、刑を終えて出獄したエミイルは途上、乙女に出会い、彼女に近づこうとして彼女の働いている工場までついて来る。その工場はルイの工場である。エミイルはそのまま工場で働くことになるが、どうもエミイルの呑気な性質は労働に適さない。いろんな失敗の揚句、首を切られる時になって社長の前に引っ張り出される。初めはエミイルが無心にでも来たのかと思ったルイも真意を知って喜んで彼を迎え、自宅の晩餐会に招待する。ルイは、エミイルのジャンヌ(ローラ・フランス)への恋心を聞いて尽力を約束する。しかし、その夜ルイのもとには昔の周囲の者が彼の正体を知って無心に来、エミイルはジャンヌに恋人ポール(ジャック・シェリー)のあるのを知って失望する。そこでルイは、無心に来た悪者どもを金庫室内に閉じ込めてしまう。翌日はルイの発明にかかる全て機械力で自動的に動く新しい工場の上棟式であるルイが式場に出席していると悪漢共の密告でルイの前身を知った警官がルイの捕縛のために乗り込んで来る。式場は忽ち大騒動となり、ルイとエミイルはその隙につけ込んで逃亡する。数日後、工場は機械力のおかげで人手を借りずに仕事を開始する。そこを遠く離れた畠道には二人の放浪者が唄いさざめきながら歩いて行く。富のイリュージョンを失ったルイ、恋のイリュージョンを失ったエミイルの二人である。しかし二人とも人間に与えられた膨大の富「自由」を取り戻したのに狂喜した。さんさんと降り注ぐ太陽の光、自由万歳!
――キネマ旬報の紹介は上記の通りですが、今回は次の『にんじん』でもそうですが、乗りに乗って「あらすじ」を起こしているのがわかります。ほとんどサイレント映画の弁士のような調子で、日本の映画界がほぼ完全にサウンド・トーキーに移行したのは昭和10年(1935年)ですから昭和9年度までの日本映画はまだ半ばサイレント時代だったのですが、この「あらすじ」を「~であります」調にするとそのままサイレント映画の弁士の口舌になるくらいなので、それほどキネマ旬報の近着外国映画紹介筆者は入れこんで書いたのが伝わります。かく言うこの感想文筆者も中学生の頃にテレビの深夜放映で初めて観た時は『巴里の屋根の下』も本作もいたく感動したもので、思春期とも呼べないような頃に感動した映画は人生経験を積むにつれ見方が上がったり下がったりしますが、今回はクレールのトーキー最初の3作を連続して観直して、学生時代このかた下がっていたクレール映画の印象がひさびさに上がりました。クレールはサイレント時代から作品がある人ですがそれは20代の助走の時期で、30代になって大きな仕事をしようというタイミングがちょうど映画のトーキー化に重なった、そこで一気に才能が開花したのが『巴里の屋根の下』『ル・ミリオン』『自由を我等に』(と『巴里祭』)で、さらにスケールのでかい作品をと挑んでフランス本国では大失敗に終わったのが『最後の億万長者』です。『最後の億万長者』は才人才に溺れるの見本みたいな怪作ですが、その兆候は『ル・ミリオン』『自由を我等に』にもあって、自戒して再び『巴里の屋根の下』に戻ったのが『巴里祭』でしたがやっぱり手を出してしまったやりたい放題映画が『最後の億万長者』だったので、日本やイギリスでは受けてもフランス本国ではそっぽを向かれることになった。そうした成り行きを含めてクレールには憎めないところがあって、イギリスに行けば『幽霊西へ行く』'35を作り、ハリウッドに渡れば『奥様は魔女』'42や『そして誰もいなくなった』'45を撮る。戦後フランスに帰国して撮った復帰作『沈黙は金』'47は、『自由を我等に』がチャップリンの『モダン・タイムス』'36の先駆作だったようにクレール版の『ライムライト』'52(チャップリン)と言えて、クレールはチャップリンよりも年少ですしこのあとも監督作品はありますが、映画監督自身による本人主催の生前葬みたいな映画でした。『自由を我等に』の感想文にはちっともなっていませんが、『巴里の屋根の下』から『ル・ミリオン』でぐっと作り物めいた趣向が増したクレール映画は『自由を我等に』ではもうリアリティもへったくれもありません。登場人物には性格すらありませんし、展開はご都合主義そのものです。これを押し進めたのが『最後の億万長者』ですが、『自由を我等に』ではまだ作為よりも自発的なクレール映画本来の人の好さが生きています。惚れる価値もない女(ローラ・フランス)に厳格なくせにたやすく昇給で買収される間抜けな伯父(ポール・オリヴィエ)を配したのも嫌みのないユーモアにとどまっており、本作は『モダン・タイムス』のみならず盟友ルノワールの傑作『素晴らしき放浪者』'32にも少なからず着想のヒントを与えたと思われます。またクレールが『巴里の屋根の下』1作の映画監督で終わっていたらその方が損失だったではありませんか。
●9月4日(火)
『にんじん』Poil de carotte (Les Films Marcel Vandal et Charles Delac=Pathe-Natan, 1932)*92min, B/W : 1932年11月4日フランス公開
監督:ジュリアン・デュヴィヴィエ(1896-1967)、主演:アリ・ボール、ロベール・リナン
・赤い髪とそばかすから「にんじん」というあだ名で呼ばれる少年フランソワ。愛の冷めきったルピック夫婦からは父母の愛情を与えられず、そのまま思春期を迎え……。ジュール・ルナールの名作文学を映画化した傑作!

[ 解説 ]「巴里-伯林」のジュリアン・デュヴィヴィエがジュール・ルナールの有名な小説並びに戯曲に基いて作った映画で、脚色もデュヴィヴィエ自身の手になるものである。主役の「にんじん」に扮するのは無名から抜擢された少年俳優のロベール・リナンで、これを助けてルピック氏にはフランス劇壇で名高いアリ・ボールが、ルピック夫人には舞台でこの役をたびたび演じているカトリーヌ・フォントネーが、それぞれ扮して出演している外、なお、オペレット畑のクリスチアーヌ・ドールや、ルイ・ゴーチエ、子役のコレット・セガル、マキシム・フロミオ、等も顔を見せている。撮影はアルマン・ティラールとモニオとが担当。それからアレクサンドル・タンスマンが特にこの映画の為めに作曲を受持っている事を附記する。
[ あらすじ ] 家庭とは同じ屋根の下に到底解り合えない人間が無理矢理に集まっている所であると「にんじん」(ロベール・リナン)は考えていた。で、彼は夏休みが来て家へ帰って皆と一緒に暮らす日が来ると味気ない気がした。が、このにんじんなどというのは、勿論この男の子の本名ではない。彼はフランソワという立派な名を持っている。然し末子に生れた彼は、家の者の誰からも愛されなかった。母親(カトリーヌ・フォントネー)は冷かに彼を睨みつけては、いつも小言ばかり云っていた。その癖に、兄のフェリクス(マキシム・フロミオ)や姉のエルネスティーヌ(シモーヌ・オーブリー)は大のお気に入りだった。が、この兄や姉もが、またにんじんには耐らなかったのである。そして又、父親のルピック氏(アリ・ボール)とは彼はまるで口をきいた事がなかった。で、彼はこの人を好きでも嫌いでもなかったが、実の所、彼には父親がまるで解らなかったのである。そんな風で、このにんじん――真赤でパサパサした髪の毛と雀斑だらけのこの子を人は人参と綽名した――は神経質に、いじけて、そして人の愛に飢えながら一人ぽっちで暮らしていた。人と遊べない彼は犬のピラムと遊んだ。そして新しく来た女中のアネット(クリスチアーヌ・ドール)と友達になろうとも考えた。が、ルピック夫人は朝から晩までにんじんを叱り飛ばしては彼から楽しみを総て奪ってしまう。にんじんが未来の花嫁として遊ぶ可愛いいマチルド(コレット・セガル)とも、そうした訳で間をせかれてしまった。斯うなってはにんじんは、もう生きているのが佗しくなって来た。そしてにんじんは夢を見るのである。夢の中ではもう一人の自分がこの自分を嘲っている。お前の様な奴は死んでしまうが良いんだ。にんじんは目を醒してから何となく楽しい死という事を考え始めた。そしてルピック氏が村長に当選して大得意になっている夜、にんじんは納屋で首を縊ろうとした。そこへ折よく駆けつけたのがルピック氏だった。だが彼にはどうして息子が死にたい気になったのか解らなかった。するとにんじんが答えた。だって僕は母さんが好きになれないんだもの。これを聞いてルピック氏が答えた。では俺が彼奴を好いてるとでも思っているのか。この言葉はにんじんを有頂天にした。この世には自分以外にも淋しがってる人間がいるんだ、そう思った時に、にんじんは、僕はこれはどうしても可哀想な父さんの為めに生きて行かなければならないんだと思った。
――これまた文末表現を「~でありました」調にすればサイレント映画の弁士のような解釈しすぎのあらすじで、映画は要点に台詞を絞った、映像をして語らしめているものです。デュヴィヴィエ映画は『白き処女地』以降どうだ、というような技巧が1作毎にエスカレートしていきますが、『にんじん』の映像は自然なカメラワークと適切な演出で落ち着いたもので、過剰なアップも目立たなければカット割りとコンテニュティーも快適なテンポで、ストーリー上山場となる部分も節目節目にありますがむしろ抑制した演出で進んでいきます。貧相なそばかすの少年にんじんと心を通わせる遊び人の老釣人パレイン(ルイ・ゴーチエ)やにんじんを慕う(「お嫁さんになる」)純心な幼女マチルデ(コレット・セガル)との交情が救いで、この二人が気づいて結末のにんじんの自殺を父のルピック氏が救いに駆けつけるのも自然な流れになっていますが、主演のアリ・ボール演じる村の名士で多忙ゆえ家を空けてばかりいるルピック氏、にんじんを虐げる母親ルピック夫人、甘やかされて弟のにんじんを見下す自分勝手な兄フェリックスと姉エルネスティーンら、ルピック家の人々は最小限の描写で見事に酷薄な性格造型がなされ、にんじんの立場に気づき守ろうとする若い新任女中のアネットの描き方と物語上の役割も老釣人パレイン、幼女マチルデ同様自然で適切です。にんじんが自殺を決意する夜中のベッドの上での自問自答(寝ているにんじん、ベッドに起き上がるにんじん、それと対話するにんじんの三重映しで表現されます)、にんじんが馬車を暴走させ自殺未遂を起こす場面(主観ショットによる馬車の疾走)、屋根裏でのにんじんの首つり自殺(駆けつけた父に間一髪で助けられる)、エピローグ部分と言えるルピック氏とにんじんへの父子の愛の確認の会話、と山場山場はあり、それも首つり自殺の前にマチルデに別れを告げに行き、マチルデはパレイン爺さんに知らせ、パレイン爺さんが村長就任パーティーの会場に駆けこんでルピック氏に知らせる、という細かく説得力のある(特に幼いマチルデが主人公の自殺の決意を聞き、「あなたが決めたなら仕方ないわ。でも残念、私はあなたが好きだから」と淡々と答える場面は泣けます)場面の積み重ねのきめ細かさはのちのデュヴィヴィエ映画からは消えてしまうもので、デュヴィヴィエらしいと言えば客前で「優しい母親にすら反抗ばかり!」とルピック夫人がにんじんを叱責すると客の一人ひとりの表情がクローズアップで次々示される場面はのちのデュヴィヴィエの客気に富んだ技法を思わせますが、自殺を思い詰める夜中のベッドの多重露出撮影もここでは技法が映画から浮いておらず、この映画は性格描写を中心にしてその深度と的確さのために名作になっています。ルピック夫人はルピック氏がにんじんの自殺を止めさせようと急いで戻ってきた際も姉娘に「どうせ注目されようとしてるのよ」と言い放ちますし、姉娘も弟の自殺にまったく無関心です。長男は父親の村長就任に反感すら抱いて遊び仲間と出かけています。にんじんが足台を蹴った間一髪にルピック氏は息子を抱いて助けますが、このにんじん役のロベール・リナンの自殺は尋常な子役の演技を越えています。アリ・ボールのルピック氏とロベール・リナンのにんじんはルピック家の中には愛情はない、末っ子のお前が生まれた時にはお父さんとお母さんの間の愛情ももうなかった、以来家族の間の憎しみはお父さんにとってもお前にとって共通の苦しみで今後も大変だろうが、パパとフランソワ(にんじんの本名)だけは本当の愛情を守りあっていこうじゃないか、と初めて愛を確認します。この結末はハッピーエンドながら人生の真実に触れた苦みがあり、これは10代で観てももっと歳をとってから観ても人生経験を増すごとに響いてくる映画でしょう。案外デュヴィヴィエの最高の映画は一見地味な田舎のホームドラマの本作で、以降は時流に乗った職人監督の映画ではないかという気さえするのです。