小津安二郎『東京の宿』(松竹1935)

『東京の宿』(全・サウンド版)
https://www.youtube.com/watch?v=_LQ2PZsQXAQ&feature=youtube_gdata_player
*

1935年の小津にはフィルム散佚作品の『箱入娘』(1月20日公開)と、この『東京の宿』(11月21日公開)があり、どちらも坂本武主演、飯田蝶子がかあやんで突貫小僧が富坊の「喜八もの」ですが、残された文献によれば『箱入娘』は『出来ごころ』『浮草物語』と続いた喜八ものではもっとも人情コメディ色が濃く、煎餅屋の喜八が近所のお嬢さんの見合い相手を探しにとんちんかんな騒ぎをする、と、それまでの喜八ものにはあった哀切さはあまり感じさせない作品だったようです。ですが、次作であり喜八ものの第四作で最後の作品『東京の宿』は小津作品としても、日本映画の歴史の中でも極端に大胆で、衝撃的なまでに飢えと放浪の苦痛を描いた作品になりました。
サウンド版(音楽入り)ではありますが、これは小津にとって最後のサイレント作品でもあります。日本映画では1931年の五所平之助作品『マダムと女房』が最初に成功したトーキーと言われます。これも松竹作品でしたが、土橋式トーキーと呼ばれる技術によるものでした。第二作以降すべての作品を茂原英雄カメラマンと組んできた小津は、茂原式トーキーの開発までトーキーは撮らないと宣言しており、日本の商業映画ではもっともトーキー化に遅れた監督になりました。そのため、サイレントでありながらすでにカット割りはトーキーの技法に移行している、という小津自身による解説もあります。それはまた後で触れましょう。

この映画は上映時間80分ほどの作品ですが、前半五分の三は男やもめで二人の息子(長男=突貫小僧)を連れた失業者・喜八(坂本武)が職を求めて雨風にさらされ、日照りに乾き、飢えながら放浪する、お先真っ暗な話が延々続きます。主人公はやがて、やはり幼い娘を連れて求職のため放浪している未亡人(岡田嘉子)と子供を介して親しくなります。
喜八は偶然旧知のおかみさんのかあやん(飯田蝶子)に出会い、彼女の紹介で職を得ます。一方、毎日未亡人と待ち合わせて子供同士を遊ばせていた町外れの原っぱに、未亡人も幼女も姿を見せなくなります。幼女が突然疫痢にかかってしまったのですが、喜八たちはその事情を知らず、薄情を嘆きます。

喜八が仕事帰り飲み屋に寄ると、酌婦に現れたのが彼女でした。当時の労務者相手の飲み屋では、酌婦は私娼でもありますから、喜八は未亡人を罵りますが(そういう飲み屋の客である喜八が罵るような立場ではないとは思いますが)、未亡人は娘が疫痢になったこと、これまで何度も母子心中を思いつめたこと、それを思えば娘のためなら何でもする、と打ち明けます。喜八は未亡人から宿を訊き、金ならおれが何とかするから、すぐここを辞めてお嬢ちゃんのところで待っていてくれ、と彼女を帰します。
喜八は帰宅し、息子たちに事情を告げるとまた出かけます。路地裏を追う警官らのモンタージュで喜八が強盗し、追われているのが暗示されます。かあやんの家に喜八が立ち寄ります。世話してもらって働いていた10日だけが幸せだったよ、息子たちを頼む、という喜八に、あんな女の娘なんかどうだっていいじゃないか、とかあやん。『出来ごころ』で次郎が「あんな女(春江)なんかどうだっていいじゃないか、とやはり喜八に忠告する場面を思い出させます。おれも何度もガキどもと死にてえ気持になってきたんだ、だからあの子を助けてやりてえんだ、と喜八は言うと、ここから一番近い警察署はあっちかな、とかあやんに別れを告げて夜道をひとり去って行きます。
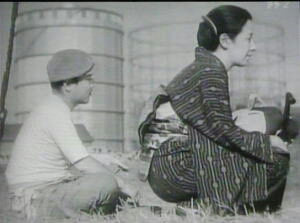
岡田嘉子(1902~1992)は『東京の女』に続いて実は夜の女、という役どころで、オランダ系の混じる血筋に生れ、10代で私生児を出産後も複雑な男性遍歴を経て、1937年にソ連に密入国するもスパイ容疑で大戦中を獄中で過ごし、戦後は日本向けラジオ放送のアナウンサーに従事。1972年に帰国しながら結局ソ連に戻り、ロシアで生を終えた数奇な生涯を送った女優です。出演作品のほとんどがサイレント期で現存しないため、『東京の女』『東京の宿』はその点でも貴重です。
この作品はまだ1935年の映画でしかありませんが、まるで1945年の、敗戦直後の東京のような廃墟感があり、映画としてもイタリアの敗戦後のネオ・リアリズモ映画に共通する姿勢があります。特にヴィットリオ・デ・シーカの『自転車泥棒』『靴みがき』は子供を描いているだけ、なおさら小津作品を思わせます。
映画前半はどこへ行っても雇ってもらえない喜八がチャップリンやキートンを思わせますが、子供たちも野犬を捕まえては売りに行き(当時、東京では実際に役所が野犬捕獲の報奨金を出していたようです)、犬を売った金で飯を喰うか宿に泊まるか、飯を喰うと夜は雨でも土管に入って寝るしかない、という放浪生活をしています。小津の映画でここまで悲惨な生活が描かれたのは後にも先にもこの作品くらいですし、小津以外の日本映画でもチャップリンの『犬の生活』レベルまで、つまり失業者どころでなく浮浪者にまでなってしまった主人公は普通、商業映画の主人公にはなりません。文学ですらクヌート・ハムスンの『飢え』1890が発表時から衝撃を持って迎えられ、類例のない作品として長く読まれていた時代です。『東京の宿』も「喜八もの」だからかろうじて人情喜劇として通った企画でしょう。『出来ごころ』『浮草物語』のキネマ旬報年間ベスト・ワンに較べると、この映画は暗さ、テンポの遅さで不評でしたが、それでも9位にランクされています。

小津にとってこの映画は、喜八をぎりぎりのシチュエーションからさらに踏み込ませてしまう、という内容をいかに描くかというテーマ上の実験でもあったでしょうし、『生れてはみたけれど』1932ではかろうじて成立しながら『非常線の女』や『出来ごころ』1933からはかなりサイレントで押してくるにはきびしくなってきた映像技法の、すでにトーキー移行後のスタイルへの転換をサウンド版ながら試みたもの、と言えるように思えます。翌1936年の『一人息子』は小津のトーキー第一作ですがすでにスタイルは(後年から観れば過渡期ですが)確立しており、『東京の宿』の時点で次作が茂原式トーキーの実用化によるトーキー作品制作への移行が決定していたとしたら、トーキーへの志向だけではなく、サイレント最後の実験を試したものとも見られます。
具体的に小津自身の映画雑誌への談話で、「喜八もの」の時期には通常トーキーで用いられるカット割りをサイレントのままやってみた、と語っています。すなわち、サイレントでは映像が先に出て、後から字幕が出てくる。単純な例で言えば、人物の表情(または動作)、続いて台詞の字幕。これが交互になり、サイレントではあまりやりとりが細かいと煩雑になるので映像だけで伝達できるやりとりはパントマイム的な身ぶり手ぶり、表情で字幕は省略します。
ですが小津はサイレントのパントマイム的演技からはもう脱却したいので、人物の表情や動作の変化はむしろ抑制したい。するとトーキー並みの字幕が必要になってくる。トーキーでは音声を聞きながら画面を観ることになるので、観客にとっては台詞が先で映像が後、という認識の順番になります。小津はサイレント映画にもかかわらず対話が主要になるシーンは字幕による台詞が先で、それから発話者の表情の映像になる、というカット割りを試しています。当然字幕画面の挿入は頻繁になるか、一枚の字幕にしては限界までの長台詞を入れることになりますが、対話自体は雄弁になるにせよ人物の演技はほとんど抑制されたものにできます。初期の『若き日』1929や『落第はしたけれど』1930からは五年ほどしか経っていませんが、小津はトーキー化が進む映画界で孤立したサイレントの改革を考案するうちに、他に類を見ないサイレントの独自進化の様式にたどり着き、それはすぐに小津独自の様式に特化したトーキーに移行できるものでした。

散佚作品の『箱入娘』は残念ながら観ることができませんが、『出来ごころ』『浮草物語』『東京の宿』はいずれもサイレント期の最後期の小津安二郎の充実した作品で重量感があると認めた上で、良くも悪くも「寅さん」の原型を感じさせるのは否めません。『箱入娘』が残っていたら文献でわかるかぎり「寅さん」度はなおさら高かったかもしれない。「寅さん」映画ほど食わず嫌いの人も観たけれど苦手という人も多い人気長寿シリーズはなかったので、松竹というブランドは小津安二郎の諸作と「寅さん」、本数でそれに次ぐのは美空ひばり映画と「釣りバカ」シリーズですし、松竹をホームドラマの映画会社にしたのはプロデューサーの城戸四郎と小津監督でした。
「喜八」は「喜八」でアメリカ映画から発想されたストーリーにあわせて創造されたキャラクターです。困っている他人を見過ごせない、というキャラクターなら(たいがい相手は女子供に限られますが)『化物語』の阿良々木暦くんでも同じで、『男はつらいよ』はテレビドラマ時から喜八ものとの類似を指摘した人がいなかったとは思えませんし、直接的影響があれば類似も相違も異なっていたでしょう。笠智衆のレギュラー出演からしても小津作品への敬意ははっきり表明されており、偶然の類似でも意識的な類似でもないはずです。それに食わず嫌いだったり、国産品は口にあわなかったりするのは寅さんに限ったことではありません。小津監督作品だって没後20年以上かけて、ようやく初期から晩年作までがまんべんなく楽しまれるようになったのです。