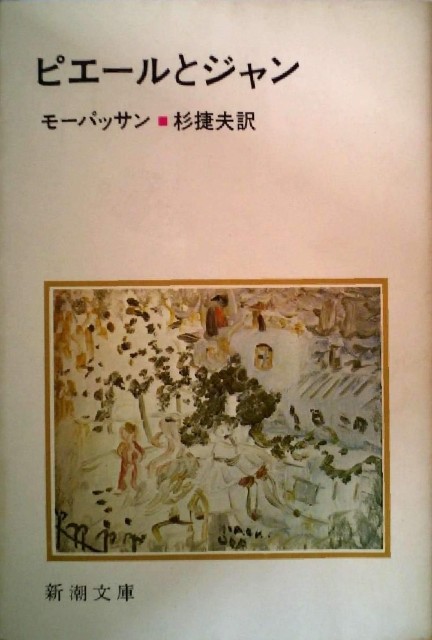
ギイ・ド・モーパッサン(1850~1893)の作家活動は実質10年間という短いものでした。20代で役人生活のかたわら伯父の親友で母の知り合いでもあったギュスターヴ・フローベール(1820~1880)の薫陶を受け、エミール・ゾラ(1840~1902)らフローベールの弟子たちと交わりながら習作を重ね、30歳を迎えた1880年4月にゾラ主宰の同人作品集に発表した中篇小説『脂肪の塊』(校正刷りで読んだフローベールは「叙述、劇的効果、観察の三方面に渡って、文句なしの傑作」と絶讚しました)が出世作になり、同年5月のフローベールの逝去と入れ替わるようにしてゾラとともに一躍フランス小説界の重鎮となったモーパッサンは、30代いっぱいの1890年までに『詩集』を1冊、第一短篇集『テリエ館』を始めとした短篇集15冊(生前の単行本未収録作品を含めて約260篇)、トルストイに激賞された1993年の第一長篇『女の一生』を皮切りに『ベラミ』『モントリオル』『ピエールとジャン』『死の如く強し』『我らの心(『わたしたちの心』『男ごころ』)』の長篇小説6作、長篇紀行文『太陽の下に』『水の上』『放浪生活』の3冊を発表します。しかし1888年には30代前半から持病になっていた神経痛、心臓病、眼疾も急速に悪化して1889年には麻酔薬の常用から奇行が目立つようになり、41歳の1891年には友人との合作戯曲の上演の他創作はなく梅毒の悪化から発狂し、1892年には狂乱状態でナイフ自殺を図り、そのまま精神病院に入院しますが、病状は回復せず、退院することなく43歳の誕生日の1か月前の1893年7月に死去しました。モーパッサン晩年の1892年(明治25年)には島崎藤村が文芸機関誌にゾラとモーパッサンの比較論文を発表しており、最新の外国文学思潮を代表する作家としてすでに生前から日本の文学者たちにも注目されていましたが、その創作期間はモーパッサンがちょうど30代の1880年~1890年の10年間(明治13年~23年)に集中していました。やはり画期的な業績を残しながら、晩年2年間は梅毒の病状悪化で廃疾者になった例にはモーパッサンの師フローベールの盟友シャルル・ボードレール(1821~1867)がいますが、モーパッサンもまた晩年2年間は病状悪化によって創作力を失い、狂気の中で死を迎える悲劇的な末期をたどりました。
モーパッサンはレフ・トルストイ(1828~1910)の中篇小説『イワン・イリイチの死』(1886年)を読んで(当時フランス文壇とロシア文壇は密接な交流がありました)、「私の10巻もの作品はすべて無価値になった」と悄然としたと言われますが、1888年刊の第四長篇『ピエールとジャン』は、『女の一生』、さらに翻訳では上下巻の大冊になる浩瀚な力作『ベラミ』と『モントリオル』の自然主義小説的作風から趣きを変えて、当時60代にさしかかっていたロシアの大作家トルストイの心理小説からの感化が見られます。その省察と抱負が『ピエールとジャン』の雑誌連載に先だって発表され、序文として巻頭に置かれたエッセイ「小説について」で表明されています。
「私はここでこの後に続く拙い小説のための弁護を試みる意図を持ってはいない。それどころか、私がこれから理解していただこうという考えは、むしろ私が『ピエールとジャン』の中で企てた心理研究的ジャンルへの批判を必然に伴うであろう。」
「小説を作るのに規則があるだろうか?それを外れたなら、物語の形式で書かれた文章が『小説』ではない、と呼ばれてしまうだろう規則が?」
「『ドン・キホーテ』が小説であるなら、『赤と黒』は何だろう?やはり小説だろうか?『モンテ・クリスト伯』が小説であるなら『居酒屋』も小説だろうか?ゲーテの『親和力』とデュマの『三銃士』とフローベールの『ボヴァリー夫人』との間に比較を立てることができるだろうか?」
ここでモーパッサンが言おうとしていることは、例に上げられた著名な小説の適切な選択とともに、非常に明晰です。独自な個々の小説に、先行作品に似ている必要はなく、また一律の基準で優劣をつけることはできないということで、
「すべての作家は、ヴィクトル・ユーゴーもゾラ氏も、敢然として勝手な小説を作る権利を、すなわち自分一個の芸術観に従って創造し、あるいは観察する絶対権を、議論の余地なく要求したものである。」
とモーパッサンは小説創作が自発的で自律的である権利を主張します。さらにモーパッサンは実作者として、作家に読者が期待しているであろうことを、作家の立場から考察します。
「読者というのは、書物の中でひとえに自分の精神の本来の傾向を満足させることを求めるので、作家に対して自分の支配的な好みに応えてくれるよう要求する。そして理想主義的な、あるいは快活な、あるいは猥雑な、あるいは陰気な、あるいは夢見がちな、あるいは現実的な、それぞれの想像力に気に入る本なりその一節なりを、相も変わらず「素晴らしい」とか「よく書けている」とか評して品定めする」
「要するに読者という集団は、作家に向かってさまざまに叫ぶ大衆から出来ている。
--慰めてくれ。
--楽しませてくれ。
--悲しがらせてくれ。
--感動させてくれ。
--夢想に耽らせてくれ。
--笑わせてくれ。
--戦慄させてくれ。
--泣かせてくれ。
--考えさせてくれ。」
19世紀後半、1888年のフランスにしてすでに、読者の要求は今日の21世紀日本の消費者(文学、美術、音楽からアニメにいたる「ユーザー」)と変わりないのが痛感されます。1888年は日本で言えば明治21年に当たります。硯友社文学台頭期の日本にあっても読者が創作者に求める要件はさほど変わりがなかったでしょう。「期待通りの作品を提供せよ(give the people what they want)、さもなければその作者は無能だ」という論調は、すでに創作の享受者が貴族や知識階級ではなく、一般市民層になった19世紀には始まっていたのです。
「ただ、少数の思慮深い精神だけが、芸術家に向かってこう要求する。
--何か美しいものを創ってくれ。あなたに一番合った形式で、あなたの気質に応じて。」
ここまでが「小説について」の前半1/3で、後半2/3は『ピエールとジャン』の創作に当たってモーパッサンがいかに過去の自作を乗り越えようと企てたか、さらにあるべき写実小説の考察と小説形式そのものの未来への展望まで進みますが、ここでモーパッサンは師のフローベールとも、年輩の盟友ゾラとも違う独自の小説の可能性を模索し、その成果としてモーパッサンの長篇小説中もっとも短く、兄弟の出生の秘密・母の悲しみというシンプルでミステリー仕立てのプロットに凝縮された名作『ピエールとジャン』が生まれ、モーパッサンが生涯に残した長篇小説6作のうち前期3作『女の一生』『ベラミ』『モントリオル』と、後期3作『ピエールとジャン』『死の如く強し』『我らの心』を分ける分水嶺になったのが、このエッセイ「小説について」です。モーパッサンのこのエッセイはゾラ1879年の自然主義小説マニフェスト「実験小説論」に匹敵し、自然主義文学にとどまらない文学考察としてモーパッサン筆生の力作と言えるものです。モーパッサンは短篇小説「首飾り」、長篇小説『女の一生』が突出して広く読まれているため軽んじられがちな存在ですが、バルザックやゾラ同様むしろ今こそ読み返される意義の大きい、閃光のように鋭い作家です。ルイス・ブニュエルは『ピエールとジャン』を兄弟の母をヒロインとした女性映画として映画化しましたが、ピエールとジャン兄弟の諍いから息子たちの出生の秘密をめぐる母の悲しみが浮かび上がってくるモーパッサンの原作も圧巻なら、時系列を追って母をヒロインとして映画化したブニュエルの『愛なき女』も素晴らしい出来で、成功した映画化作品の多いゾラ同様モーパッサンもまた詩的感受性こそが魅力をなしている小説家なのがもっとも端的に表れている作品こそ『ピエールとジャン』です。モーパッサンはすでに余命5年、創作活動の限界は残り2年にさしかっていました。未訳のうちに夏目漱石は『女の一生』と『ピエールとジャン』の英訳を読み、モーパッサンをあまり好きではないとしながら『ピエールとジャン』については「名作ナリ。Une Vieノ比ニアラズ。」と日記に記していますが、兄弟の確執、出生の秘密、明るみになる過去という題材はいかにも漱石好みと言えそうです。短篇集、傑作中篇『脂肪の塊』、第一長篇『女の一生』でモーパッサンはもういいや、という読者の方にもぜひお薦めしたい名作です。