Charlie Parker - Bird at St.Nick's (Jazz Workshop, 1955)後編

Charlie Parker - Bird at St. Nick's (Jazz Workshop, 1955) Full Album : http://youtu.be/HmdRCut0X2Q
Recorded at St.Nick's Arena by Jimmy Knepper(possibly), February 18 1950
Released Jazz Workshop JWS-500
(Side A)
A1. I Didn't Know What Time It Was(Rogers-Hart) 2:35
A2. Ornithology(Parker-Harris) 3:27
A3. Embraceable You(Gershwin-Gershwin) 2:18
A4. Visa(C.Parker) 2:57
A5. I Cover the Waterfront(Heyman-Green) 1:44
A6. Scrapple From The Apple(C.Parker) 4:34
A7. Star Eyes(Andrew-Speaks)/52nd Street Theme(T.Monk) 3:02
(Side B)
B1. Confirmation(C.Parker) 3:18
B2. Out of Nowhere(Heyman-Green) 2:17
B3. Hot House(T.Dameron) 3:45
B4. What's New(Burke-Haggart) 2:43
B5. Now's The Time(C.Parker) 4:14
B6. Smoke Gets In Your Eyes(Harbach-Kern)/52nd Street Theme(T.Monk) 4:46
Charlie Parker Quintet ;
Charlie Parker - Alto Saxophone
Red Rodney - Trumpet
Al Haig - Piano
Tommy Potter - Bass
Roy Haynes - Drums

("Charlie Parker and Modern Jazz All Stars : Carnegie Hall X-Mass '49")
1949年のクリスマス・イヴにカーネギー・ホールで行われたオールスター・コンサートはチャーリー・パーカーのニックネーム「バード(ヤードバード)」にちなんだジャズ・クラブ「バードランド」の開店祝いを兼ねたもので、バードランドの司会者に抜擢された人気タレントのシンフォニー・シド司会のもとにバド・パウエル&マックス・ローチ・トリオ、さらにマイルス・デイヴィス、ソニー・スティット、サージ・チャロフらを加えたジャムセッション、スタン・ゲッツ&カイ・ワインディング・クインテット、ジミー・ジョーンズのピアノ伴奏によるサラ・ヴォーン、リー・コニッツとウォーン・マーシュをフィーチャーしたレニー・トリスターノ・クインテット、そして当然のようにトリを飾ったのがレッド・ロドニーのトランペット、アル・ヘイグのピアノ、トミー・ポッターのベース、ロイ・ヘインズのドラムスからなる新メンバーによるチャーリー・パーカー・クインテットの5曲だった。曲目は『オーニソロジー』『シェリル』『コ・コ』『バード・オブ・パラダイス』『ナウズ・ザ・タイム』ですべてパーカーの著名なオリジナル曲、5曲できっかり30分になる。この時30歳のパーカーは人生の絶頂にいた。
だが常に新奇な企画が求められたクレフ/ヴァーヴ・レーベルでは、このメンバーでの公式録音の機会は与えられず、わずかにレッド・ロドニーが51年8月のセッションで5曲に臨時編成バンドで公式録音に参加しているにすぎない(アルバム『スウェディッシュ・シュナップス』収録)。だが51年の夏には、すでにクインテットは実体を失っていたとおぼしい。
翌52年にはパーカーはヘイグだけを連れてカリフォルニア巡業をし、トランペットには22歳のチェット・ベイカーを現地採用している。ヘイグはロサンゼルスに留まり、ニューヨークに戻ったパーカーは急激な人気凋落にレギュラー・クインテットの再結成を断念し、まだパーカーの盛名が根強いワシントンやボストン、シカゴや隣接圏のカナダ地方にチャールズ・ミンガス(ベース)とロイ・ヘインズだけを連れて現地採用ジャズマンと共演する活動形態に移らざるを得なくなる。34歳で急逝するまでの晩年は凋落の一途だった。
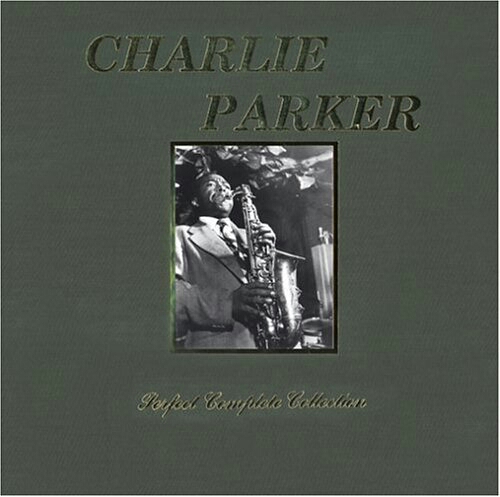
(18CD Box『Charlie Parker Perfect Complete Collection』)
ロドニー、ヘイグ、ポッター、ヘインズからなるパーカー最後のレギュラー・クインテットはそれまでのメンバーと較べると小粒に見えるかもしれない。だが今年90歳を迎えてなお現役のヘインズは、パーカー歿後も常に新しいスタイルに応じたヴァーサタイルなドラマーだった。エリック・ドルフィーの『アウトワード・バウンド』もチック・コリアの『ナウ・ヒー・シングス、ナウ・ヒー・ソブス』もロイ・ヘインズがドラムスを叩いているのだ。ポッターの安定した実力は言うまでもない。
クインテットの5人のうち、ロドニーとヘイグの二人は白人だった。レッド・ロドニー(1924~1994)は白人ビッグバンドで働きながらパーカーとガレスピーのビバップに憧れていた。パーカー・クインテットが空中分解した後も地味な活動を続けていたが、1958年に薬物禍で逮捕され2年3か月の獄中生活を送り、ミュージシャンとしてのキャリアに壊滅的な打撃を受けた。釈放後も警官のマークがつき、1963年には警官から数本の歯を失い完治までほぼ10年を要した口唇の裂傷を負う(目や耳を傷つけず、また脳震盪を負わせずに顔面を打撲して抵抗力を喪失させるため、警察官は顔面の下半分しか打撲しない)。また同年には実父を亡くし、その数か月後にラスヴェガスでの公演からの帰り、夫人の運転する車がハイウェイで事故を起こし大破した。ロドニーは後部座席で眠り込んでいたが、衝撃で目覚めると夫人と14歳の一人娘が死んでいるのを見つけた。
その後もロドニーは音楽活動を薬物禍で何度も中断し、70年代には治療院で受刑者仲間になったウェイン・クレイマー(MC5)に音楽を教えたりしたが、80年代になって5枚の優れたビバップ・アルバムを発表して注目を集め、生きた伝説としてチャーリー・ワッツ(ローリング・ストーンズ)主催のチャーリー・パーカー・トリビュート企画に特別待遇された。
またアル・ヘイグ(1922~1982)はガレスピーとパーカーがニューヨークで共同活動を始めてすぐに準レギュラーとして関わった白人バップ・ピアニストの草分けで、スタイルの確立は2歳年下のバド・パウエルに遅れてバドから強く影響を受けたが、純粋なバップ・ピアニストではバドに次ぐ存在と言える実力者だった。だが1954年の『アル・ヘイグ・トリオ』『アル・ヘイグ・カルテット』をインディーズのピリオドに残しただけで56年にフィル・ウッズの『ザ・ヤング・ブラッズ』、58年にチェット・ベイカーの『イン・ニューヨーク』の参加がある程度になってしまう。1965年に『アル・ヘイグ・トゥデイ』でカムバックしたかに見えたが、1969年に殺人事件で起訴される。前年の1968年10月に再々婚した夫人が不審死を遂げており、ヘイグ自身の弁明では夫人は泥酔して自宅階段を転落した、という。事件は起訴猶予になったが、ヘイグはスキャンダルを警戒して人目に立つ音楽活動を自粛せざるを得なかった。2007年にヘイグの二番目の夫人だった女性が出版したヘイグの伝記には、ヘイグの家族や近親者の証言から家庭内暴力傾向があったことを引き出し、ヘイグの家族は彼が暴力的になった時のために警報ベルを用意していたという。
私生活の荒廃のために音楽活動からリタイアしていたヘイグに新作の録音を持ちかけたのは、ロドニーと同じく外国のオーソドックスなジャズ・レーベルだった。ロドニーが73年の『バード・リヴズ!』でカムバックしたのとほぼ軌を一にして、74年の『インヴィテイション』でヘイグはカムバックし、歿年までの8年間に12枚のアルバムを残す。これもロドニーの13枚と釣り合う。
黒人の音楽であるジャズの、さらにコアなビバップの世界にいち早く白人ジャズマンとして飛び込んでいったヘイグやロドニーがどれほどナーヴァスでストレスの多大な環境にいたかは想像にあまりある。1950年にはアメリカは今日よりもさらにアパルトヘイトの徹底した国家だったが、州ごとにほぼ個別の法律制度を取っている点でも社会構造は封建的だった。黒人と白人の混成バンドはそれだけで憎悪の対象になるため、人種差別の強い地方の巡業ではロドニーは黒人の白子(アルビノ)とステージで紹介されてアルビノ・レッドという屈辱的なニックネームに耐えなければならなかった(ヘイグはピアニストだから白人でも観客の反感を買わなかった)。ロドニーの薬物禍もヘイグの暴力癖も彼らが重すぎる重圧にさらされていた反映のように思える。
マイルス・デイヴィスは自叙伝で、チャーリー・パーカーほど白人に対するコンプレックスを持たなかった黒人を知らない、と発言している。むしろそれまでの優秀すぎる資質を持つメンバーたちよりも、ロドニーやヘイグが熱意と抑制の両方をもってかもしだす余裕のある雰囲気は、ガレスピーはもとよりマイルス、ドーハムら歴代黒人トランペット奏者、パウエルやジョーダンら黒人ピアニストの時代のパーカー・クインテットにはなかったものだった。クインテットの自然消滅直後、西海岸巡業限定とはいえロサンゼルスで現地採用したのが白人ジャズマンならではの柔らかなトーンを持つチェット・ベイカーだったのもうなずける。
トミー・ポッターは60年代初頭のジャズ不況で現役を退いたが、それまでに十分な実績を残した。ロイ・ヘインズに至っては現役最長老ドラマーとして今なおジャズ界の頂点に立っている。ビバップの実力派黒人ジャズマンの多くは50年代以降もスタイルを変化させながら生き延びていった。アル・ヘイグとレッド・ロドニーはパーカー・クインテットに抜擢されたために、栄光とともに呪われた生涯を定められてしまった白人ジャズマンだった。
トランペットとピアノのソロのほとんどをばっさりカットされてはいるものの、『バード・アット・セント・ニックス』はこのメンバーならではのクインテットの一体感を伝える最高のドキュメントになっている。ここでのパーカーのくつろいだ自由奔放な演奏は、10年後のオーネット・コールマンの出現すら予告するものという指摘すらあるほど、肉声に近いニュアンスを持っているとさえ言える。