Charlie Parker - Bird at St. Nick's(Jazz Workshop,1955)前編

Charlie Parker - Bird at St. Nick's (Jazz Workshop, 1955) Full Album : http://youtu.be/HmdRCut0X2Q
Recorded at St.Nick's Arena by Jimmy Knepper(possibly), February 18 1950
Released Jazz Workshop JWS-500
(Side A)
A1. I Didn't Know What Time It Was(Rogers-Hart) 2:35
A2. Ornithology(Parker-Harris) 3:27
A3. Embraceable You(Gershwin-Gershwin) 2:18
A4. Visa(C.Parker) 2:57
A5. I Cover the Waterfront(Heyman-Green) 1:44
A6. Scrapple From The Apple(C.Parker) 4:34
A7. Star Eyes(Andrew-Speaks)/52nd Street Theme(T.Monk) 3:02
(Side B)
B1. Confirmation(C.Parker) 3:18
B2. Out of Nowhere(Heyman-Green) 2:17
B3. Hot House(T.Dameron) 3:45
B4. What's New(Burke-Haggart) 2:43
B5. Now's The Time(C.Parker) 4:14
B6. Smoke Gets In Your Eyes(Harbach-Kern)/52nd Street Theme(T.Monk) 4:46
Charlie Parker Quintet ;
Charlie Parker - Alto Saxophone
Red Rodney - Trumpet
Al Haig - Piano
Tommy Potter - Bass
Roy Haynes - Drums
チャーリー・パーカー(1920~1955)には80年代末すでに放送録音やプライヴェート録音をその時点で網羅した18枚組ボックス・セット『Charlie Parker Live and Private Recordings Chronogical Order』があり、日本盤は『チャーリー・パーカー・パーフェクト・コンプリート・コレクション』としてサウンドヒルズ社から発売されている。だがそれからの25年余りでパーカーのライヴ録音の発掘はさらに進み、先の18枚組に収録漏れだった発掘ライヴと合わせるとCDにして50枚、アナログLP換算で100枚近い発掘録音がパーカーにはあることになる。
パーカーの本格的な自己名義の公式デビュー録音は1945年だから、実働期間約10年(歿年は3月逝去でほとんど活動がない)でサヴォイ・レーベルにCD4枚分(別テイク、未発表曲含む)、ダイアル・レーベルにCD4枚分(別テイク、未発表曲含む)、クレフ/ヴァーヴ・レーベルにCD10枚分(別テイク、未発表曲、公式ライヴ含む)があり、さらに自己名義で活動前にジェイ・マクシャンのビッグバンドでの録音がLP3枚分、ディジー・ガレスピーのバンドとレッド・ノーヴォのバンド、サー・チャールズ・トンプソンのバンドに客演したものが各々LP1枚分あり、以上を公式録音とするとCD換算で約22枚、LP換算で40枚以上になるから、実働期間10年間はパーカーの生命力を確実に消耗させる過剰労働だったのを痛感する。
パーカーの生前から1947年9月プライヴェート録音のライヴ『バード・アンド・ディズ』や、後に公式アルバム『サミット・ミーティング・アット・バードランド』に収められた放送録音のライヴ(1951年3月)は10インチLPの海賊盤で公式アルバム以上のプレミア価格で出回っていた。もちろん闇流通だが、パーカーは観客録音は歓迎でマニアは特別に良い席で堂々とマイクを立てて録音を許可されたという。
特にミュージシャンはスタジオ盤以上に奔放に飛翔するパーカーのライヴ演奏を珍重し、テープ保有者が集まってライヴ録音の鑑賞会を開いていたという。特にジミー・ネッパー(トロンボーン)が良質なテープを自ら録音して鑑賞会を熱心に主催していた。パーカーが1955年3月に急逝してチャールズ・ミンガス主宰のジャズ・ワークショップ・レーベルから年内すぐに発売されたのは、ミンガス・バンドのメンバーだったネッパー提供のテープがあったからだと想像される。
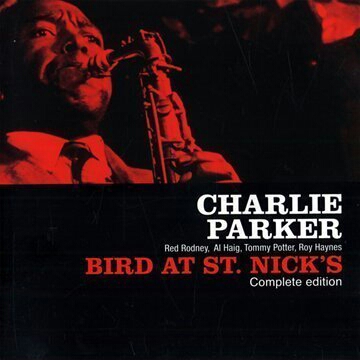
("Bird At St.Nick's : Complete Edition" 9曲増補版)
この『バード・アット・セント・ニックス』はセント・ニックス競技場で開催された単独コンサートからのライヴ録音で、40年代~50年代のジャズの発掘ライヴ、しかもプライヴェート録音を聴きなれない人には音質からしてまず拷問だと思うが、パーカーの公式スタジオ録音をひと通り聴いたリスナーには、オアシスのようなアルバムとして密かに愛されている点では、パーカーの発掘ライヴでも最上位に数えられるだろう。選曲もパーカーのベスト・アルバムと言ってよいほど充実したもので、パーカー絶頂期の終わりに近い時期のライヴとしても円熟した演奏が聴ける。
ただ手離しでお勧めできないのは音質にプライヴェート録音ならではの限界があること、さらにパーカーの演奏パートを残してトランペットのソロもピアノのソロもカットしてあることだ。パーカーの先発ソロが終わると4小節くらいはトランペットのソロが聴けるのだが、そのままエンディングのパーカーとドラムスの4ヴァース演奏につなげられ(つまりトランペットのソロとピアノのソロは割愛され)、アルトサックスとトランペットのユニゾン・テーマで終わってしまう。実際の演奏時間は各曲本来1.5倍~2倍あったと思われる。
バラードものなどは元々テンポが遅い上にエンディング・テーマはAA"形式の曲ならA"の後半8小節+コーダ、というのも普通だから(バラードの器楽演奏はエンディングでもテーマを完奏するとくどくなるのだ)、パーカーのアルトサックスが引っ込んでトランペット~ピアノが引き継ぐ中間部をカットしてエンディングにつなげると、実際の演奏の半分以下の長さになってしまうのだ。
そんな具合に音質はライヴ会場のラジカセ客席録音並み、編集も不完全となると、下手をすればこのアルバムを聴いてパーカーが苦手になってしまう人もいるかもしれないほどだが、パーカーの音楽に病みつきになっているリスナーにはこれほど愛しいアルバムはない。病みつきなくらいだから正規アルバムは全部、主な発掘録音も大半は聴いている、そんなリスナーは当然パーカー以外のアーティストの音楽もやたらに聴いているわけだが、さて久しぶりにパーカーでも聴こうか、という時に選ばれることが多いアルバムがこの『バード・アット・セント・ニックス』なのだ。
スタジオ盤は端正だったりタイトすぎる、ライヴでももっとオーディオ的に良い音質だったり演奏内容が抜群なものは他にある。その点『セント・ニックス』はまるで客席にいるような臨場感と飲み食いしながらでも聴けるくつろぎがあり、パーカーも全力ではなく適度な力加減で吹いていて、おそらくパーカーにとってこれほど普通のライヴ・パフォーマンスはないくらい平均的な内容になっている。パーカーが引っ込むとトランペット~ピアノのソロがカットされてエンディングにいきなりつながってしまうのも、リスナーが聴きたいのはパーカーの演奏なのだから理にかなっている。
ジャズ史の偉人などと意識せず、同時代にふらりとパーカーのライヴを聴けたならだいたいこんな演奏だったろう、という理想的な普通のパーカーがそこにいて、もちろん演奏は名盤名演と定評がある数々のスタジオ録音やライヴ録音に引けはとらないが、力みのなさと優れた演奏がここでは見事に釣り合いがとれているのだ。パーカーといえど不調や手抜きのライヴ録音があり、またパーカー自身はまずまずだが共演ミュージシャンに足を引っ張られている場合が多々ある。
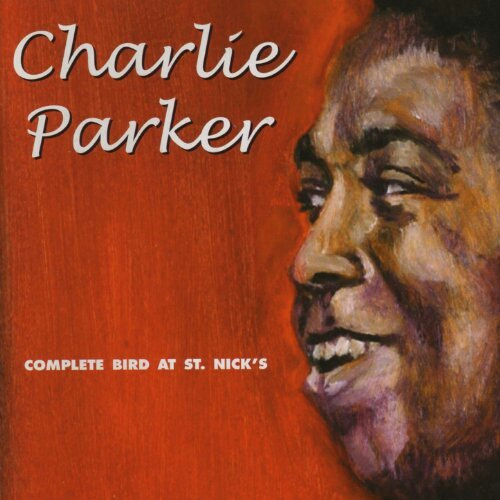
("Bird At St.Nick's"デジタルダウンロード版)
この『バード・アット・セント・ニックス』の良さはパーカー最後のレギュラー・クインテットの結束力を伝えるライヴでもあることで、パーカーがカンサスからニューヨークに進出してきた折は、カンサスに地方巡業に来たディジー・ガレスピー(トランペット)を頼りに双頭リーダー・グループを組んだのだった。ピアノはジョン・ルイスやクライド・ハート、ジョー・オーバニー、ベースはスラム・スチュワートやカーリー・ラッセル、ドラムスはケニー・クラークやシド・カレット、シェリー・マンやルー・レヴィだった。このうちジョー・オーバニー、シェリー・マン、ルー・レヴィは白人ジャズマンだった。この流動メンバーのグループはどちらかといえばディジー・ガレスピーがリーダーだった。
ガレスピーと並んで脚光を浴び、別々にリーダーとなるバンドを組んだ時、パーカーがトランペットに採用したのは18歳のマイルス・デイヴィスだった。一方ディジーは念願のビッグバンド結成に向かったが2年と続かず、再び小編成バンドに戻る。この時テナーサックスに迎えられたのがマイルスと同年生まれのジョン・コルトレーンで、他にミルト・ジャクソン、ジョン・ルイス、パーシー・ヒース、ケニー・クラークというすぐ後にモダン・ジャズ・カルテットになる4人が在籍し、ギターにはケニー・バレルがいた。
一方初代チャーリー・パーカー・クインテットはマイルスのトランペットにドド・マーマローザのピアノ、カーリー・ラッセルのベース、マックス・ローチのドラムスでスタートし、ベースはトミー・ポッターに交替することもあり、ピアノはマーマローザからバド・パウエル、そしてデューク・ジョーダンに代わった。1945年~1948年がそうで、48年秋~49年秋はトランペットがマイルスより2歳年長のケニー・ドーハムに代わる。ドーハムは安定感抜群のプレイヤーである上パーカーも私生活が安定していた時期で、メジャーのクレフ/ヴァーヴ・レーベルに移籍して弦楽オーケストラ作品の録音に力を入れていたためドーハム時代のスタジオ録音が少ないが、ジャズ・クラブのロイヤル・ルーストへの年間出演とラジオ中継から多くの公式ライヴ録音が残されている。
ドーハムは若手の中でもすでに中堅ミュージシャンと認められており、パーカー・クインテット退団後セロニアス・モンクのブルー・ノート録音(1952年)まで活動にブランクがあるが、活動再開後はマイルス同様モダン・ジャズ界最重要ミュージシャンになっていく。ドーハムの退団を受けてジョーダンとローチも独立し、ベースのポッターは残留しクインテットはトランペットにレッド・ロドニー、ピアノにアル・ヘイグ、ドラムスにロイ・ヘインズという最終ラインナップになった。つまり『バード・アット・セント・ニックス』のパーソネルになる。
(以下後編)