現代詩の起源(6); 逸見猶吉詩集『ウルトラマリン』(iii)
逸見猶吉(1907-1946)、『全詩集大成・現代詩人全集12』口絵より。昭和3年(1928年)1~2月頃、同年1月開店・経営の神楽坂のバー「ユレカ」にて。

*報告(ウルトラマリン第一) (昭和4年=1929年10月「學校」)
兇牙利的(ウルトラマリン第二) (昭和4年=1929年12月『學校詩集』)
*死ト現象(ウルトラマリン第三) (昭和4年=1929年12月『學校詩集』)
*曝ラサレタ歌 (昭和6年=1931年3月「詩と詩論」)
*冬の吃水 (昭和6年=1931年3月「詩と詩論」)
*檻 (昭和6年=1931年3月「詩と詩論」)
*廣シイ天幕 (昭和5年=1930年9月「詩と詩論」)
*ベエリング (昭和5年=1930年9月「詩と詩論」)
*ナマ (昭和10年=1935年5月「歴程」)
牙のある肖像 (『逸見猶吉詩集』初出)
途上 (昭和11年=1936年3月「歴程」)
*煉瓦臺にて (昭和6年=1931年6月「詩と詩論」)
大外套 (昭和6年=1931年6月「詩と詩論」)
*終驛 (『ウルトラマリン』初出)
*火ヲ享ケル (『ウルトラマリン』初出)
*海の非情 (『ウルトラマリン』初出)
*神の犬 (『ウルトラマリン』初出)
*燼 (昭和9年=1934年5月「三田文學」)
*手 (『ウルトラマリン』初出)
*蠅の家族 (昭和8年=1933年2月「新詩論」)
*悪靈 (『ウルトラマリン』初出)
兇行 (昭和7年=1932年10月「新詩論」)
十字屋書店版の編集方針は遺稿の整理にまだ検討の余地があり、未発表詩編や『ウルトラマリン』(昭和4年=1929年後半~昭和11年=1936年前半)以前・以降の時期の詩編の扱いもやや恣意的なものになりました。生前未発表の逸見猶吉最長の散文詩「牙のない肖像」の収録という大きな収穫もありましたが、昭和23年時点では戦時中に(当時)満州の風物に材を取った詩編はGHQの検閲を忌避してごく一部の収録にとどまったのです。また、逸見猶吉自身が『ウルトラマリン』をまとめた昭和4年後半~昭和11年前半以外の初期・後期詩編は16編になりますが、分量では詩集後半の4分の1を占めるに過ぎません。前半4分の3を占める22編が『ウルトラマリン』の時期であり、その半数が昭和4年後半~昭和6年前半に発表されており、発表誌不明(または未発表)の『ウルトラマリン』初出作品が推定昭和6年後半~昭和11年前半に集中していると思われます。
十字屋書店版『逸見猶吉詩集』は次回の16編(多くは短詩)でご紹介を終えますが、予告と目次を兼ねて一覧をまとめておきます。前記の通り『ウルトラマリン』収録作品は「熱河」1編しかなく、『ウルトラマリン』初出かつカタカナ詩と『ウルトラマリン』期の特徴を備えており、同作が詩集末尾近くに配列されたのは編集上の都合か何らかのミスかと思われます。発表時期の分布で言っても今回までの3回・22編が『ウルトラマリン』期、最終回分16編中15編が『ウルトラマリン』以前・以後(「熱河」のみ『ウルトラマリン』期)になります。
無題 (昭和16年=1941年2月『歴程詩集』)
ある日無音をわびて (昭和4年=1929年5月「學校」)
青い圖面 (昭和2年=1927年9月「鴉母」)
秋の封塞 (昭和2年=1927年11月「鴉母」)
眼鏡 (昭和2年=1927年11月「鴉母」)
老將 (昭和11年=1936年10月「歴程」)
哈爾濱 (昭和14年=1939年7月「滿州浪漫」)
海拉爾 (昭和14年=1939年7月「滿州浪漫」)
汗山(ハンオーラ) (昭和14年=1939年3月「滿州浪漫」)
*熱河 (『ウルトラマリン』初出)
無題 (昭和16年=1941年2月『歴程詩集』)
無題 (昭和16年=1941年2月『歴程詩集』)
無題 (昭和16年=1941年2月『歴程詩集』)
無題 (昭和16年=1941年2月『歴程詩集』)
黒龍江のほとりにて (昭和18年=1943年6月「歴程」)
人傑地靈 (昭和18年=1943年6月「歴程」)
高村光太郎は逸見猶吉の追悼文に「彼のやうな詩人は多作であり得るわけがないから、恐らく遺した詩は極めて少ないであらう。ウラニウムのやうに小さくて、又そのやうに強力な放射能を持つてゐるのだ」(「歴程」昭和23年=1948年7月「逸見猶吉追悼号」)と書いています。逸見猶吉の客死は敗戦後の混乱期だったので逝去が「歴程」同人に伝わり追悼号が組まれるのも2年かかり、逸見猶吉初の単行詩集の十字屋書店版『逸見猶吉詩集』刊行とほぼ同時になりました。「歴程」の長老的な高村光太郎は「歴程」前身の「學校」に逸見猶吉が参加した時からの知己でしたし、『現代詩人集3』(歴程同人集)の『ウルトラマリン』と「歴程」掲載作品を除けば『逸見猶吉詩集』の8割方は目にしていたでしょう。
つまり『ウルトラマリン』から『逸見猶吉詩集』に新たに増補された分は、初期に本名の大野四郎名義で個人誌「鴉母」に発表されたアナーキズム的作品、『ウルトラマリン』期最大の未発表詩編「牙のない肖像」、満州時代の優れた作品「哈爾濱」「海拉爾」「汗山(ハンオーラ)」「黒龍河のほとりにて」「人傑地靈」などで、『ウルトラマリン』の詩人の拾遺詩編として質的には納得のいくものですが、分量的にはあまりに少ないのです。のちの『定本逸見猶吉詩集』でさらに40編あまりが増補されても精髄は十字屋書店版ですでにほぼ出尽くしており、享年40歳までに20年あまりの詩歴を持った詩人としては、同年生まれの中原中也が享年30歳で遺した詩編の5分の1程度でしかなく、6歳年長で同じ享年40歳で亡くなった小熊秀雄は中原中也の倍近い多作の詩人でした。小熊、中原、逸見に優劣はつけられませんが、確かに逸見猶吉の集中的な寡作には説得力があります。次回の最終回は『逸見猶吉詩集』内の補遺に当たる部分ですが、十分な詩質を保ってはいても『ウルトラマリン』に相当する前半4分の3のパートに匹敵するとまでは言えないのです。
『逸見猶吉詩集』(全38編)昭和23年=1948年6月・十字屋書店
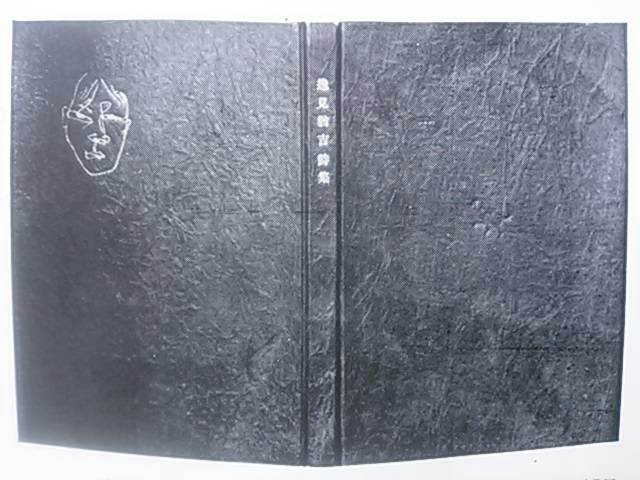
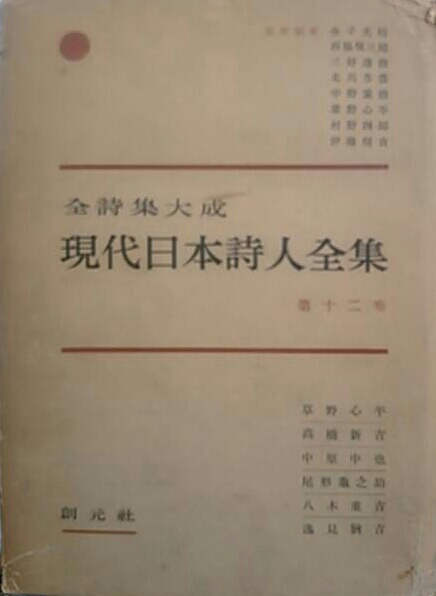
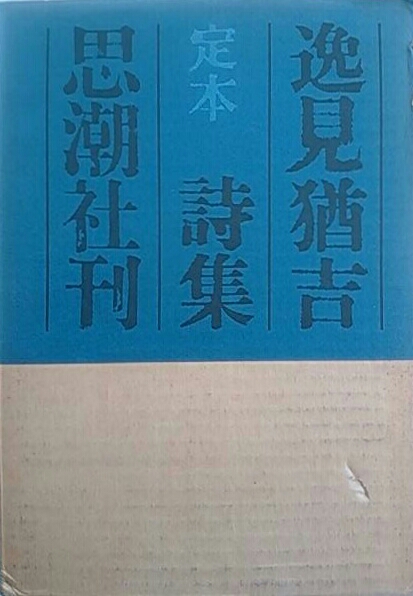
海の非情 逸見猶吉
うねりは深甚な藍青にくろまり
キレの剄い氣流のましたを落ちながれ 漂ひ
油然と息をひそめ また一瞬にたかまつて
碎けちり 錯亂する それもあらたに
しづかな凄みの渦を巻きかへし おもひ返して 奈落へと墜ちなだれ うねり
ああ 繰り返しの齒向つてくる無明の表情 これは涯しない肉體だ
この目にみえて 見えるともない怒りこそ永遠の所有から
踏み出す萬の手の露はなるつながり
鹹水に裸をさらしていま無盡な夢と格闘の
槍穂の束のぎらぎらに醒め
醒めきれぬまゝに立ち邀(むか)はふとしてゐるが……
うねりはおほまかな足摺りで 灼ける水平から寄せてくる
陸地をむざんに噛んでゐる
(昭和15年=1940年3月『現代詩人集3』内『ウルトラマリン』収録)
神の犬 逸見猶吉
ぎいんとした岩場の空が死んで視るかぎり
燦々たる微塵群の天幕は醒めてゐる
鞴のやうな息吹きに 翳をひく時間のながれ
挑みあふ千の枝々に血を滴たらせ
雪の切々たる抑制に ただ前へ目をおとす
背におふ花の印象と燃えあがる灰の錯亂と----
吠えることを忘れ
ああ ひとりなる神の犬よ
荒々しい夢のかたまりとなつて
いまは燼のやうに動くすべをしらない
身を退いて 忍べよ
眼は鹹水に漬かるべし
剛直の毛並に油をそゝぎ
牙にはそれ伐られざる荒蕪地を横たふべし
耿々たる大理石の粉をあび ひたすら
炎上せる季節のましたに血を整へよ
ふたたび夢をゆりおこせよ
きびしい岩場の大天井にしづかにむげんの闘ひが映る
また恐ろしい時間のながれか
陶醉の歌 風に千切れて
(昭和15年=1940年3月『現代詩人集3』内『ウルトラマリン』収録)
燼 逸見猶吉
鋼の巣を強引に張りめぐらせて、酒精と星星の拉ぎあふ死の穹窿を、諸手に抱きこんでゐる流沙の涯だ。透明な光の群落をかきわけて、そこから馥れうつ火の奔馬達。かつては様々に、滾りたつ悲哀や魅惑を堵け、つねに非道の輩と、飽くなき爛醉に棲みながら闘ひを決してきた己だが。ああ、またしても幻を起す、この灼かれた皮膚のしたに鎖を曳いて逆流する海洋、北方の。暗緑の飛沫にけぶる刃の弧線よ。それこそ生々たる闘ひであつてくれ。鋼の巣をむじんに切り破つて、脱がれて生肉の唯一なる膽妄に無数の槍を負つてゐる現在か。だが荒涼として、これが無限の修羅を墜ちてゆく全意識であらうか。----己は笑ひだす。
喉元から身を鐵條に突き刺したまま、足もとに横たわる鴉一羽。その虚ろな眼窩に喰ひさがる青褪めた血の幾筋を、----漆黒の羽毛は残虐な光の逆手にかき窩られて、燃えあがる。打ち据えられた生肉の、熱氣に煽られ、戦慄の、だがもう還るすべもない影の狼煙ではないか。燃えろ、燃えあがつて彼の穹窿の大扉を思ふさまに蹴外してくれ。しどろに荊棘を藉きつめて、臨終の、いま大正午の深い畏怖にひき摺られ、殺戮のあらはな声は無辺の屋根に遠退いてゆく。擅(ほしいまま)なる----それを聴くのだ。
渇いたうへにも渇く檜葉の枝々。
黒三稜(みくり)の重なる沼澤に漬つた凶時よ、この青春時。
醉ひ痴れた姿態の裡に、蒙昧な刹那々々の反應に、ありとある幻象の隈を彫り、背徳と夢と倨傲の立ちはだかる、この青春時。荒掴みに己の裸身をひき起して、なほ哀切の言葉を薄るものは何であらう。足もとには、おお燼が吹きつのる熱氣に擾れて、このひと時の己の愛だ。苦い獸皮のやうに、酒精と星々の拉ぎあふ死の穹窿を、諸手にかけて、----流沙の涯へ沈んでゆく。
(昭和15年=1940年3月『現代詩人集3』内『ウルトラマリン』収録)
手 逸見猶吉
重い油をさすやうに
つめたく秘密にとり縋るもの
この手はひさしく慄えるペン軸を必死と握つてゐるのだが
苦がいインキは海の氣配にそそがれて
やうやく乾いた血いろの底にしづんでゆく
日のひかりはこの手にとどかず
この手は叫ばずおのれに堪へ
沸騰するくらいナヂールの
大廻轉のしたにある
艱める翳に伏したままさうしてばらばらと頁を繰るのだが
水のいろが鹹くぶきみに漂ひながれて
蟲をまいたやうに凶はしい
時をりあの強大なむなしさを孕む幕となつてなだれると
斑らの網に非情の鱶はみえかくれ
翳を拂はふとするこの手もやがて見失はれる
(昭和15年=1940年3月『現代詩人集3』内『ウルトラマリン』収録)
蠅の家族 逸見猶吉
しやべり散らすな 愛を
おもひきり胸には水をそそげ
斧は眞冬の面(つら)に打ちこまれて其處に巣を張れば陣々と鳴る
岩乗な鐵拐のうしろに廻つて
つめたい風が煤を吹きまくる季節中
そいつのために諸々の夢の所在が冱えてくるのだ
冬は
はがねの仕組みで
むしろ萬人の汚辱のなかに廣しく立ち
悔いと怒りに充ちた己こそ千切れなければなるまい
離散する蠅の家族ら
道は道のあるかぎり覆され
とほく終驛にえぐられた跨線橋黒だ
己は血ぬれ
移動する雲と樹々と
そそがれる水のあふれ……
冬の巣が鐵拐の一撃にばりり壊されては
かすかに青みどりの合唱ながれ
胸のなかひとすぢの憂愁は逆毛だつ
たちまち荒々しい光がいり擾れてくるのを
己は身に浴びて目撃する冬だ
(昭和8年=1933年2月「新詩論」/昭和15年=1940年7月『現代詩人集3』内『ウルトラマリン』収録)
悪靈 逸見猶吉
荒地をうしろにして少年は裸馬の上にゐた
ぎらとした染料を溶いて涯しない酷熱が来ると荒地の喚ばふ
その澱みくる酷熱にさきぶれて
渇きは風とともに舞ひあがる
むげんの引き波に漂ふものみなのしじま
鞭をならして砂塵に没した慓悍な影を見送れば
裸馬からずり落ちた少年に哄ひはいつそうむごく残され
さうしてひとたびは身を起したが
無用の白々しい風に捲かれた
(昭和15年=1940年3月『現代詩人集3』内『ウルトラマリン』収録)
兇行 逸見猶吉
この夜明け。秋の眩輝(ぐれあ)に犯されて、困憊の、ざざといふ風や光や、その微かな参差の奥に人を喚んでゐる、あはれ黒松属であらう。雷管を藏した岩尾根が低い天末に削られて、その上に火傷を浴びた雲を飛ばせば、菫青色の深まる天のぐんと向ふ。巨いなる荒掠者の手からふり撒かれ、己の遡る河上にいま、微塵はとうめいの異(あや)しい廢汽となつて沈んでくる。水の面にたゞよふ彼の影像は、水羊歯や蘆のたぐひを啖ひながらも、發(あば)かれた地上に在るものの、匈々たる交感の裡に織りこまれてゆくのか。舊くまた新しく、つねに兇行の果されて來たこの河上に、彼の息吹は人間歴史の跡を曝して、ああ、それを己に傳へる彼の苛烈よ。秋は骨のやうな磧を渉り、水底に渇き疲れた神々の聲を聴いてゐるのだ。哄ふべし。神々と言はふ、たゞわけもなく飜へる水の面、----かき消された妄想が薹のやうに、復た此処に聚るであらう。己は必死なる季節の加擔者。遡るところ、眩輝の異しい漲落を胸に量り 額をもたげて愛のやうな 荒繩のやうな強力の醉ひをこの躯に糾ふのだ。しだいに昂る爛酔となれば、反つて一望の視野は冷然ときりひらかれ、四肢に纏ふ風や光の鳴り響く その戦きを貫いて地と天の境のもの黒松の岩尾根の、不逞にして深甚なる彼こそ、燦として正しく煤を拂ふ荒掠者の姿だ。彼を捉へ、彼に視入り、彼から離れ去る誠実の言葉は、己たちに降りかゝる贖ひの血しぶき、----いつかは涯の日を笞打たれる身であらうに、おもへば己や君や、罕(まれ)なる理會の何んといふ空しさだ。
堕ちゆく面貌の數々といひ
こころなき蹂躙に委せた心情の隈といふ----
喪に塗りつぶされた自棄くそのインキ畫で
生活の 情痴の ひたむきな妄想の蠅といふ----
たちまち群れて唸りをあげ 犇きあがり
修羅の火の手に覆へる大血槽に溺れるといふ----
おもふざま其處でじたばたするといふのだ。
無頼な群集の裡に棲みながら
おもひ上つた信條を悦しいといふ----
ああ 冷酷の無邊大 磁の凄じい牽引に躯を焼いて
すべて闘ひの途に起て。各々はげしい自愛を衝くのだ。
この夜明けに 幾萬の眼をひらく子らは 甍に重なる甍を跨がり 海へなだれる起伏の昏い涯を馳つて 彼等その生長の日々に何を歓び歌ふであらうか。撃たれよ みづからの深傷(ふかで)に生きたる哄ひをあげて 千年の鐵柵に懊のやうな血を流すべし。
河上に 玻璃末の錯亂。
荒掠者の行方。
己はまだ遡る。永遠 風に荒れて 兇行の日々は殷賑たれ。
(昭和7年=1932年10月「新詩論」)