
明治35年(1902年)10月・博文館刊の1巻本『透谷全集』では単行詩集として明治24年に刊行されていた『蓬莱曲』と、日記「透谷漫録摘集」に初期の草稿詩5編と著者控え本の『楚囚之詩』(明治22年4月・刊行中止)が加わり、エッセイ・批評も大幅に増補されましたが晩年明治25年~明治27年の詩群は『透谷集』と同じ9編のままでした。全集と名銘ちながら「ゆきだをれ」は明治25年作品、「ほたる」は明治26年上半期作品、「蝶のゆくへ」「雙蝶のわかれ」「眠れる蝶」「露のいのち」は明治26年下半期作品、「髑髏舞」は沒後発表で明治26年上半期作品と推定されるもの、「彈琴」は明治26年上半期作品「彈琴と嬰児」の初稿型、「みゝずのうた」は前述の通りで、「彈琴」は生前発表の決定稿「彈琴と嬰児」ではなく初稿が採られているのに「ほたる」は沒後発表の初稿型「螢」ではなく生前発表の決定稿が採られている、など同時代人の編集こその恣意性が見られ、何より既発表詩編すら全てが網羅されていないのが問題です。ですが戦後の昭和25年刊『透谷全集』第1巻(岩波書店刊)まで透谷の晩年詩といえば戦前版全集の9編を指し、それらは初出誌の記載や詞書(前書き)を割愛して収録されていました。透谷晩年詩のご紹介の最後に戦前版『透谷全集』の通りの9編を並べてみるのもあながち無駄ではないでしょう。
透谷全集/1902.10.9、博文館
ゆきだをれ ……………………… 388
ほたる ……………………… 395
蝶のゆくへ ……………………… 396
雙蝶のわかれ ……………………… 397
眠れる蝶 ……………………… 400
露のいのち ……………………… 403
髑髏舞 ……………………… 404
彈琴 ……………………… 410
みみずのうた …………………… 412
島崎藤村編『透谷集』明治27年(1894年)10月・文學界雑誌社
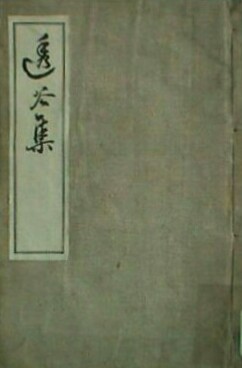
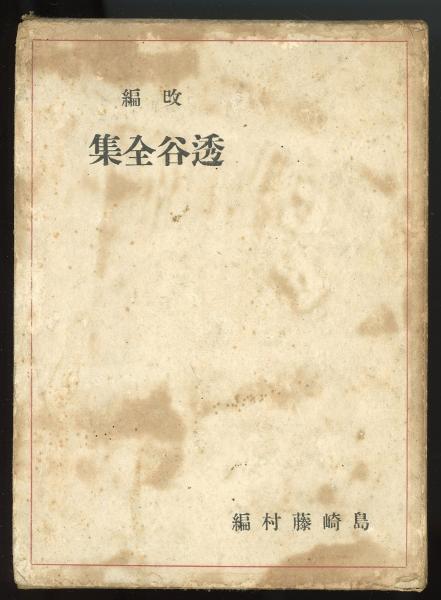
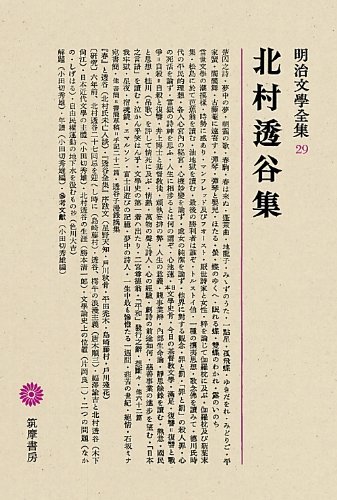
ゆ き だ ふ れ
○瘠せにやせたるそのすがた、
枯れにかれたるそのかたち、
何を病みてかさはかれし、
何をなやみて左はやせし。
○みにくさよ、あはれそのすがた、
いたましや、あはれそのかたち、
いづくの誰れぞ何人ぞ。
里はいづくぞ、どのはてぞ。
○親はあらずや子もあらずや、
妻もあらずや妹もあらずや、
あはれこの人もの言はず、
ものを言はぬは唖ならむ。
○唖にもあらぬ舌あらば、
いかにたびゞとかたらずや。
いづくの里を迷ひ出でて、
いづくの里に行くものぞ。
~~~~~~~~~~~
○いづこよりいづこへ迷ふと、
たづぬる人のあはれさよ。
家ありと思ひ里ありと、
定むる人のおろかさよ。
○迷はぬわれを迷ふとは。
迷へる人のあさましさ。
親も児も妻も妹とも持たざれは、
闇のうきよにちなみもあらず。
○みにくしと笑ひたまへど、
いたましとあはれみたまへど、
われは形のあるじにて、
形はわれのまらうどなれ。
○かりのこの世のかりものと、
かたちもすがたも捨てぬとは、
知らずやあはれ、浮世人(うきよびと)、
なさけあらばそこを立去りね。
~~~~~~~~~~~
○こはめづらしきものごひよ、
唖にはあらで、ものしりの、
乞食のすがたして来たりけり。
いな乞食の物知顔ぞあはれなる。
○誰れかれと言ひあはしつ、
物をもたらし、つどひしに、
物は乞はずに立去れと、
言ふ顔にくしものしりこじき。
○里もなく家もなき身にありながら、
里もあり家もある身をのゝしるは、
をこなる心のしれものぞ、
乞食のものしりあはれなり。
○世にも人にもすてられはてし、
恥らふべき身を知るや知らずや、
浮世人とそしらるゝわれらは、
汝が友ならず、いざ行かなむ。
~~~~~~~~~~~
○里の児等のさてもうるさや、
よしなきことにあたら一夜の、
月のこゝろに背きけり、
うち見る空のうつくしさよ。
○いざ立ちあがり、かなたなる、
小山の上の草原に、
こよひの宿をかりむしろ、
たのしく月と眠らなむ。
○立たんとすれば、あしはなえたり、
いかにすべけむ、ふしはゆるめり、
そこを流るゝ清水しみづさへ、
今はこの身のものならず。
○かの山までと思ひしも、
またあやまれる願ひなり。
西へ西へと行く月も、
山の端はちかくなりにけり。
~~~~~~~~~~~
○むかしの夢に往来せし、
栄華の里のまぼろしに、
このすがたかたちを写しなば、
このわれもさぞ哄笑ひつらむ。
○いまの心の鏡のうちに、
むかしの栄華のうつるとき、
そのすがたかたちのみにくきを、
われは笑ひてあはれむなり。
○むかしを拙なしと言ふも晩おそし、
今をおこぞと言ふもむやくし。
夢も鏡も天も地も、
いまのわが身をいかにせむ。
○物乞ふこともうみはてゝ、
食たうべず過ぎしは月あまり、
何事もたゞ忘るゝをたのしみに、
草枕ふたゝび覚めぬ眠に入らなむ。
ほ た る
ゆふべの暉(ひかり)をさまりて、
まづ暮れかゝる草陰に、
わづかに影を点せども、
なほ身を恥づるけしきあり。
羽虫を逐ふて細川の、
棧瀬をはしる若鮎が、
静まる頃やほたる火は、
低く水辺をわたり行く。
腐草(ふさう)に生をうくる身の、
かなしや月に照らされて、
もとの草にもかへらずに、
たちまち空に消えにけり。
蝶 の ゆ く へ
舞ふてゆくへを問ひたまふ、
心のほどぞうれしけれ、
秋の野面をそこはかと、
尋ねて迷ふ蝶が身を。
行くもかへるも同じ関、
越え来し方に越えて行く。
花の野山に舞ひし身は、
花なき野辺も元の宿。
前もなければ後もまた、
「運命」(かみ)の外には「我」もなし。
ひら/\/\と舞ひ行くは、
夢とまことの中間(なかば)なり。
雙 蝶 の わ か れ
ひとつの枝に双つの蝶、
羽を収めてやすらへり。
露の重荷に下垂るゝ、
草は思ひに沈むめり。
秋の無情に身を責むる、
花は愁ひに色褪めぬ。
言はず語らぬ蝶ふたつ、
齊しく起ちて舞ひ行けり。
うしろを見れば野は寂し、
前に向へば風冷し。
過ぎにし春は夢なれど、
迷ひ行衛は何処ぞや。
同じ恨みの蝶ふたつ、
重げに見ゆる四(よつ)の翼(はね)。
双び飛びてもひえわたる、
秋のつるぎの怖ろしや。
雄(を)も雌(め)も共にたゆたひて、
もと来し方へ悄れ行く。
もとの一枝(ひとえ)をまたの宿、
暫しと憩うふ蝶ふたつ。
夕告げわたる鐘の音に、
おどろきて立つ蝶ふたつ。
こたびは別れて西ひがし、
振りかへりつゝ去りにけり。
眠 れ る 蝶
けさ立ちそめし秋風に、
「自然」のいろはかはりけり。
高梢(たかえ)に蝉の声細く、
茂草(しげみ)に虫の歌悲し。
林には、
鵯(ひよ)のこゑさへうらがれて、
野面には、
千草の花もうれひあり。
あはれ、あはれ、蝶一羽、
破れし花に眠れるよ。
早やも来ぬ、早やも来ぬ秋、
万物(ものみな)秋となりにけり。
蟻はおどろきて穴索(もと)め、
蛇はうなづきて洞に入る。
田つくりは、
あしたの星に稻を刈り、
山樵(やまがつ)は、
月に嘯むきて冬に備ふ。
蝶よ、いましのみ、蝶よ、
破れし花に眠るはいかに。
破れし花も宿仮れば、
運命(かみ)のそなへし床なるを。
春のはじめに迷ひ出で、
秋の今日まで酔ひ酔ひて、
あしたには、
千よろづの花の露に厭き、
ゆふべには、
夢なき夢の数を経ぬ。
只だ此のまゝに『寂』として、
花もろともに滅(き)えばやな。
露 の い の ち
待ちやれ待ちやれ、その手は元へも
どしやんせ。無残な事をなされゐ。その
手の指の先にても、これこの露にさはる
なら、たちまち零ちて消えますぞへ。
吹けば散る、散るこそ花の生命とは
悟つたやうな人の言ひごと。この露は何
とせう。咲きもせず散りもせず。ゆふべ
むすんでけさは消る。
草の葉末に唯だひとよ。かりのふし
どをたのみても。さて美い夢一つ、見る
でもなし。野ざらしの風颯々と。吹きわ
たるなかに何がたのしくて。
結びし前はいかなりし。消えての後
はいかならむ。ゆふべとけさのこの間も。
うれひの種となりしかや。待ちやれと言
つたはあやまち。とく/\消してたまは
れや。
髑 髏 舞
うたゝねのかりのふしどにうまひして
としつき経ぬる暗の中。
枕辺に立ちける石の重さをも
物の数とも思はじな。
月なきもまた花なきも何かあらん、
この墓中(おくつき)の安らかさ。
たもとには落つるしづくを払ねば、
この身も溶くるしづくなり。
朽つる身ぞこのまゝにこそあるべけれ、
ちなみきれたる浮世の塵。
めづらしや今宵は松の琴きこゆ、
遠(をち)の水音も面白し。
深々と更けわたりたる真夜中に、
鴉の鳴くはいぶかしや。
何にもあれわが故郷の光景(ありさま)を
訪はゞいかにと心うごく。
ほられたる穴の浅きは幸なれや。
墓にすゑたる石軽み。
いでや見むいかにかはれる世の態を、
小笹踏分け歩みてむ。
世の中は秋の紅葉か花の春、
いづれを問はぬ夢のうち。
暗なれや暗なれや実に春秋も
あやめもわかぬ暗の世かな。
月もなく星も名残の空の間(ま)に、
雲のうごくもめづらしや。
天(あめ)を衝く立樹にすがるつたかつら、
うらみあり気に垂れさがり。
繁り生ふ蓬はかたみにからみあひ、
毒のをろちを住ますらめ。
思ひ出るこゝぞむかしの藪なりし、
いとまもつげでこのわが身。
あへなくも落つる樹の葉の連となり
死出の旅路をいそぎける。
すさまじや雲を蹴て飛ぶいなづまの
空に鬼神やつどふらむ。
寄せ来るひゞき怖ろし鳴雷(なるかみ)の
何を怒りて騒ぐらむ。
鳴雷は髑髏厭ふて哮(たけ)るかや、
どくろとてあざけり玉ひそよ。
昔はと語るもをしきことながら、
今の髑髏もひとたびは。
百千(もゝち)の男なやませし今小町とは
うたはれし身の果ぞとよ。
忘らるゝ身よりも忘るゝ人心、
きのふの友はあらずかや。
人あらば近う寄れかし来れかし、
むかしを忍ぶ人あらば。
天地に盈みつてふ精も近よれよ、
見せむひとさし舞ふて見せむ。
舞ふよ髑髏めづらしや髑髏の舞、
忘れはすまじ花小町。
高く跳ね軽く躍れば面影の、
霓裳羽衣を舞ひをさめ。
かれし咽うるほはさんと渓の面(おも)、
うつるすがたのあさましや。
はら/\と落つるは葉末の露ならで、
花の髑髏のひとしづく。
うらめしや見る人なきもことはりぞ、
昨日にかはれる今日の舞。
纏頭(てんとう)の山を成しける夢の跡、
覚めて恥かし露の前。
この身のみ秋にはあらぬ野の末の
いづれの花か散らざらむ。
うたてやなうきたる節の呉竹に、
迷はせし世はわが迷ひ。
忘らるゝ身も何か恨みむ悟りては、
雲の行来に気もいそぐ。
暫し待てやよ秋風よ肉なき身ぞ、
月の出ぬ間まにいざ帰らむ。
彈 琴
悲しとも楽しとも、
浮世を知らぬみとりこの、
いかなればこそ琵琶の手の、
うごくかたをば見凝るらむ。
何を笑むなる、みとりこは、
琵琶弾く人をみまもりて。
何をか囁くみとりこは、
琵琶の音色を聞き澄みて。
浮世を知らぬものさへも、
浮世の外の声を聞く。
こゝに音づれ来し声を、
いづこよりとは問ひもせで。
破れし窓に月滿ちて、
埋火かすかになりゆけり、
こよひ一夜(ひとよ)はみどりごに、
琵琶のまことを語りあかさむ。
み ゝ ず の う た
わらじのひものゆるくなりぬ、
まだあさまだき日も高からかに、
ゆふべの夢のまださめやらで、
いそがしきかな吾が心、さても雲水の
身には恥かし夢の跡。
つぶやきながら結び果てゝ立上り、
歩むとすれば、いぶかしきかな、
われを留むる、今を盛りの草の花、
わが魂は先づ打ち入りて、物こそ忘れめ、
この花だにあらばうちもえ死なむ。
そこはふは誰ぞ、わが花の下を、
答へはあらず、はひまはる、
わが花盗む心なりや、おのれくせもの、
思はずこぶしを打ち挙げて
うたんとすれば、「やよしばし。
「おのれは地下に棲みなれて
花のあぢ知るものならず、-
今朝わが家を立出でゝより、
あさひのあつさに照らされて、
今唯だ帰らん家を求むるのみ。
「おのれは生れながらにめしひたり、
いづこをば家と定むるよしもなし。
朝出る家は夕べかへる家ならず、
花の下にもいばらの下にも
わが身はえらまず宿るなり。
「おのれは生れながらに鼻あらず、
人のむさしといふところをおのれは知らず、
人のちりあくた捨つるところに
われは極楽の露を吸ふ、
こゝより楽しきところあらず。
「きのふあるを知らず
あすあるをあげつらはず、
夜こそ物は楽しけれ、
草の根に宿借りて
歌とは知らず歌うたふ。」
やよやよみゝず説くことを止めて
おのがほとりに仇あるを見よ、-
知恵者のほまれ世に高き
蟻こそ来たれ、近づきけれ、
心せよ、いましが家にいそぎ行きね。
「君よわが身は仇を見ず、
さはいへあつさの堪へがたきに、
いざかへんなん、わが家に、
そこには仇も來らまじ、安らかに、
またひとねむり貪らん。」
そのこといまだ終らぬに、
かしこき仇は早や背に上れり、
こゝを先途と飛び躍る、
いきほひ猛し、あな見事、
仇は土にぞうちつけらる。
あな笑止や小兵者、
今は心も強しいざまからむ、-
うちまはる花の下、
惜しやいづこも土かたし、
入るべき穴のなきをいかん。
またもや仇の来らぬうちと
心せくさましをらしや、-
かなたに迷ひ、こなたに惑ひ、
ゆきてはかへり、かへりては行く、
まだ帰るべき宿はなし。
やがて痍(いたみ)もおちつきし
敵はふたゝびまとひつ、-
こゝぞと身を振り跳ねをどれば、
もろくも再びはね落され、
こなたを向きて後退(あとじ)さる。
二つ三つ四ついつしかに、敵の数の、
やうやく多くなりけらし、
こなたは未だ家あらず、
敵の陣は落ちなく布きて
こたびこそはと勇むつはもの。
疲れやしけむ立留まり、
こゝをいづこと打ち案ず、-
いまを機会(しほ)ぞ、かゝれと敵は
むらがり寄るを、あはれ悟らず、
たちまち背には二つ三つ。
振り払ひて行かんとすれば、-
またも寄せ來る新手のつはもの、-
踏み止りて戦はんとすれば
寄手は雲霞のごとくに集りて、
幾度跳ねても払ひつくせず。
あさひの高くなるまゝに、
つちのかわきはいやまして、
のどをうるほす露あらず、
悲しやはらばふ身にしあれば
あつさこよなう堪へがたし。
受けゝる手きずのいたみも
たゝかふごとになやみを増しぬ。
今は払ふに由もなし、
為すまゝにせよ、させて見む、
小兵奴らわが背にむらがり登れかし。
得たりと敵は馳せ登り、
たちまちに背を蓋ふほど、-
くるしや許せと叫ぶとすれど、
声なき身をばいかにせむ、
せむ術なくてたふれしまゝ。
おどろきあきれて手を差し伸れば
パツと散り行く百千の蟻、-
はや事果しかあはれなる、
先に聞し物語に心奪はれて、
救ひ得させず死なしけり。
ねむごろに土かきあげ、
塵にかへれとはうむりぬ。
うらむなよ、凡そ生とし生けるもの
いづれ塵にかへらざらん、
高きも卑きもこれを免のがれじ。
起き上ればこのかなしさを見ぬ振に、
前にも増せる花の色香、-
汝(いまし)もいつしか散りざらむ、
散るときに思ひ合せよこの世には
いづれ絶えせぬ命ならめや。
*仮名づかいは原文のまま、詩の表題と発表誌は正字を残し、本文は略字体に改めました。「みゝずのうた」の特殊句読点(白ゴマ点/白抜き句点)は「、-」に置き換えました。