

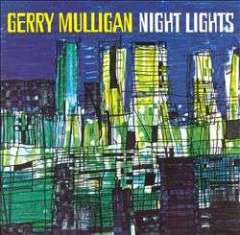
マリガンは、というかヴァーヴというレーベルは大物同士の共演アルバムをやたらに作りたがるところで、たとえば名盤と名高いゲッツとJ.Jの「オペラハウス」などぼくはまるで良さがわからないが、レーベルを立ち上げたノーマン・グランツがジャズのオールスター興行で一発当てた人だった。大御所ビッグバンドから独立した50代のジャズマンは確かにスター・プレイヤーだが新鮮さには欠ける。ビッグバンド出身でジャズの歴史に造詣が深く、先人を深く尊敬しているマリガンには前回のベン・ウェブスター&ベニー・カーター、今回の'Gerry Mulligan Meets Johny Hodges'60(画像1)はうってつけ、さぞやジャズマン冥利に尽きただろう。
ホッジス(1906-1970、アルト)はウェブスターに較べるとソロ活動ではいい作品がない。エリントン楽団に1928年加入、途中4年半ほどソロ活動で抜けたが没年までの40年間をエリントン楽団のスターとして活躍した。ウェブスターとの録音でも先輩を立てていいアルバムを作ったマリガンだが、ホッジスとはさらにいい。クロード・ウィリアムソン(ピアノ)、バディ・クラーク(ベース)、メル・ルイス(ドラムス)という都会的な洗練を感じさせるトリオもいい。ほとんど全編がホッジスの独壇場のバラード'What's the Rush'が溜め息が出るほど美しい。戦前最高のアルトと言われたのもわかる。
また、この年にマリガンは'Gerry Mulligan at the Village Vanguard'で念願のビッグバンドを成功させている。
'Jeru'62(画像2・コロンビア)はレーベルが違うとアグレッシヴに攻めるのか、これまで自分の単独リーダー作ではピアノレスでやってきたマリガンが初めてピアノを入れた(トミー・フラナガン)。意外なスタンダード'Get Out of Town'が聴き物だろう。
翌年の'Night Lights'63(画像3)はハービー・ハンコック'Speak Like a Child'68に先んじたソフトな金管アンサンブルでヒット作になった。ファーマーとブルックマイヤーを呼び戻し、タイトル曲ではマリガンはピアノを弾いている。