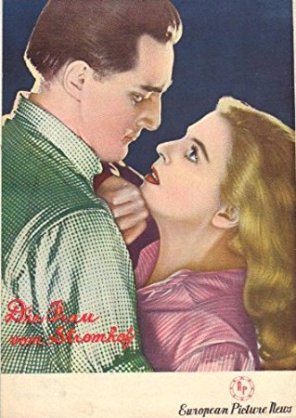映画日記2018年4月10日~12日/ジャン・ギャバン(1904-1976)主演作品30本(4)



『大いなる幻影』La grande illusion
113分 モノクロ 1937年6月9日(仏)/1938年9月18日(米)/日本公開1949年5月21日(リヴァイヴァル公開1976年10月、2001年1月、2018年2月)
監督 : ジャン・ルノワール
出演 : ピエール・フレネー
第一次大戦中、ドイツの捕虜収容所で出会った仏軍の大尉と中尉。大尉は貴族出身で、中尉は機械工だった。立場の違いから親しくなれずにいた2人だったが、ある晩収容所からの脱獄に成功し……。


俳優たちの存在感と名演には文句のつけようもありません。映画監督が自分の大先輩の大監督を俳優に使うて気の使い方には本作でも大変で、ルノワールはシュトロハイムにさんざん泣かされたそうですが、顎まで覆う高いカラーをつけて礼をするたびに上半身ごと傾ける、背筋の真っ直ぐなシュトロハイム独特の演技は本作でも実に決まっており、シュトロハイムはギャバンやフレネーと面談してフレネーには自分と同類の貴族性を認めるのですが、ギャバンやダリオも階級は同じだというフレネーにシュトロハイムは「フランス革命の賜物ですな」と答える。ギャバンとダリオの脱走のためにフレネーが仕組んだ行動とシュトロハイムとの対決は本作の見せ場で、『どん底』に続いてシャルル・スパークが共同脚本を書き、ジャック・ベッケルが助監督をしています。ギャバン出演作ではありませんが、イタリア・ロケの『トニ』'34ではルキノ・ヴィスコンティが助監督でしたからルノワールに師事した助監督は実に良い影響を受けたものです。本作のルノワールらしからぬ図式性は、しかし先のシュトロハイムとフレネーの職業軍人としての誇りにもあれば(『どん底』の貴族ルイ・ジューヴェが安宿「どん底」に溶けこむのとは対照的です)、ヨーロッパ・ロケの『さらば夏の光』'68撮影中にジャック・リヴェットの新作『狂気の愛』'68の試写会でジャンヌ・モローに手を引かれてご機嫌のルノワールに紹介されたという吉田喜重監督がのちにルノワールを論じて『大いなる幻影』ではルノワールは自分の信じていないものを描いてしまったのではないか、というの指摘の結末に表れており、雪山を国境の向こうを目指して進むギャバンとダリオはドイツ兵に発見されてしまいますが、ドイツ兵はギャバンたちが国境線を越えたのを視認して「撃つな。国境を越えた」と銃を下ろして引き返していきます。だが現実の戦争にはそんな国境など存在せず、それは戦争に限らず現実の人間存在全体に明確な区分などないというのが『素晴らしき放浪者』'32から『ゲームの規則』、『フレンチ・カンカン』'54や『大いなる幻影』のセルフ・リメイクと言える『捕らえられた伍長』'61にいたるまで無秩序で自由な人間ドラマを描いてきたルノワールの本心ではなかったか。この吉田監督の指摘は的を射ていると思います。アメリカでもヒット作になりアカデミー賞特別賞(外国語映画賞)候補に上げられて'60年代まで欧米でも世界映画ベストテンに数えられてきた本作と『ゲームの規則』の評価が逆転してきたのが'70年代以降の風潮で、ルノワール自身が主演した艶笑上流界悲喜劇で興行的にも同時代評でも散々の失敗作とされ、モリエールから始まってドストエフスキーで終わるようなヨーロッパ文明の内部崩壊喜劇である不吉な混迷に満ちた『ゲームの規則』はまったく『大いなる幻影』とは異なる映画で、それゆえルノワール自身が主演しなければ表現できなかった作品でした。本作のスパーク脚本は相変わらず巧みで、3年間引き受ける会社がなかった本作の企画がようやく映画化を実現したのもギャバン主演、スパーク脚本の『どん底』の成功があったからでしょう。庶民のギャバンと貴族のフレネーというのも『どん底』のギャバンとジューヴェの踏襲です。しかし『どん底』は人間の本質は貴族も庶民もない、その立場はかりそめでいつ変わってもおかしくないという話でした。スパークの脚本では本作は第一次世界大戦の映画だからヨーロッパ的礼節は生きていた、現代ではその礼節すらなくなってしまったと訴えている映画のように見えるのをどうもルノワールはあまり考えず、いつものひょうひょうとしたルノワール流の感覚が脚本の図式性に押さえこまれている印象を受けます。観直せばちゃんとルノワールらしい部分もあるのであながち失敗作とも言い切れない。また観直せばやはり感動させられるでしょう。ただ吉田氏の指摘は映画監督ならではの直観として正鵠を獲ていると思います。


『メッセンジャー』Le Messager
93分 モノクロ 1937年9月3日(仏)/日本未公開
監督 : レイモン・ルーロー
出演 : ギャビー・モルレー
妻の会社で何不自由のない生活をしていたダンジュ。彼は秘書のマリと恋に落ち、妻と職場を捨てる。しかし、再就職は難しく、ダンジュはひとり、ウガンダの鉱山で働くことになる。彼は現地で部下のロランと出会うが……。

そんな具合で本作はギャバンは映画の前半と結末に登場するだけで、ギャバンの別れた妻だと隠してジャン=ピエール・オーモンとつきあい始めてしまうギャビー・モルレーの恋愛が後半えんえん続くのです。ギャバンをだしにしたジャン=ピエール・オーモン(1911-2001)の売り出し用の映画としか思えません。オーモンは『白き処女地』にもケベックの山奥の村を出て都会で働き、クリスマス休暇で帰ってきた青年の役だったはずで、マルセル・カルネの『北ホテル』'38の主役のひとりでもあり、ハリウッド進出も果たし、トリフォーの『アメリカの夜』'73にも出演するなどそれなりに大成した俳優ですが、本作のように映画前半はギャバン、後半はオーモンとモルレーという具合にざっくり割れてしまった構成では観客は誰に感情移入したらいいのかわからない。べつに感情移入を排した映画でもいいのですが、誰の行動を追えばいいのかわからないようなドラマは小説であれ映画であれアニメ、マンガであれ観客・読者の関心を持続させてくれなくなります。本作の場合はたぶんギャバンは病気から回復したらアフリカから帰国してくるから三角関係の話になるんだろう、と漠然と予想、いや期待して観るのですが、一向に帰ってくる気配がないまま中途半端にオーモンとモルレーの恋愛が進む。ギャバンは結局アフリカから帰国してくる、しかも映画の残り時間がほとんどなく本格的な三角関係が描かれるとは思えない頃に帰ってくるのですが、いったいギャバンはオーモンとモルレーに接触してくるのかというあたりから先は書くと話を割ってしまうことになるので、「やがてオーモンとモルレーが真剣に恋に落ちた頃、帰国してきたギャバンは……」まででにごしておきましょう。いっそ最初から本作はジャン=ピエール・オーモンの主演映画で、オーモンとモルレーのロマンスに忍びよる前夫ギャバンの影、という趣向の映画と思った方がいいのかもしれません。だとすればギャバンの浮気と離婚、アフリカ落ちと長々描かれてからようやくオーモンが登場してくるのですから、何をかいわんや、脚本もしくは企画段階であまり出来の芳しくない映画になるのは決まっていたようなものです。さすがにデュヴィヴィエやリトヴァクはもちろんマルク・アレグレだってこんな不手際はやりません。ギャバンとしては出番は半分、ギャラは主演格と割り切って出演したか、またはルノワールの『どん底』の時にアルバトロス社作品にはもう1本出るのが契約条件だったのかもしれません。本作公開が'37年9月3日、ドイツ系大手映画社ウーファ映画社製作の『愛慾』高解像度が'37年9月24日というのもアルバトロス社=パテ映画社が先手を打って弱い作品を早々公開したように思えるのです。
●4月12日(木)
『愛 慾』Gueule d'amour
90分 モノクロ 1937年9月24日(仏)/日本公開1948年8月31日
監督 : ジャン・グレミヨン
出演 : ミレーユ・バラン
女たらしの下士官のリュシアン。彼は南仏カンヌで一目惚れしたマドレーヌに夢中になってしまう。しかし、彼女はつれなく彼を煙に巻くばかりだった。ある日彼女が親友のルネを弄ぼうとしていることを知ると……。



時代も'37年にもなって大手ドイツ系映画社のウーファ映画社で本作を製作しているのは、ナチス政権的には頽廃芸術もいいところで、よくまあウーファもグレミヨンもこんな映画を作っていたものです。本作は南仏プロヴァンスの地方都市オランジュの騎兵隊員で「Gueule d'amour (口説き上手、女たらし)」と誰からも呼ばれる町の名物色男のギャバンが郵便局でパリのホテル宛てに「至急金送れ」の電報の文面に苦心している美女バランに出会う。ギャバンはバランを食事に誘うがギャバンが席を少し外した間に女はギャバンの所持金を全部盗んで消えてしまう。ここからが無茶苦茶なのですが、ギャバンは騎兵隊を辞職してパリに出てバランを訪ねて熱烈に口説き、女たらしの過去を捨てて勤勉に働きバランに貢ぎますがバランはしょっちゅう行方不明になる。つまりバランはフランス各地にいるパトロン旦那の掛け持ちお妾さんをしているわけです。ギャバンはバランの住むホテルに乗りこみバランの母(マルグリット・ドゥヴァル)に軽くあしらわれた挙げ句、数いるバランのパトロンのうち筆頭の旦那でホテル経営者ジャン=ピエール(ピエール・エシュパール)を電話で呼びよせ、全員の前でバランは堂々とギャバンを侮辱する。ギャバンはパリで勤めていた印刷所を辞めてオランジュに帰りますが、たった2年で10歳以上老けたギャバンを酒場の女主人(ジャーヌ・マルカン)含めて街の人は名物男だった女たらしとは気がつかない。ギャバンは親友だった青年医師ルネ(ルネ・ルフェーヴル)に会いに行きますが、ルネが嬉しそうにギャバンに語る「往診で知りあって、半月前からデートしている彼女」はバランのことで、ギャバンはバランが自分の親友までパトロン旦那にしようとしていると知り……と、ここまでにしておきますが、もう鋭利な映像感覚といい情け容赦ない展開といい、確かに美女で悪女ではあるものの美貌もさして魅惑的とまでいかず悪女っぷりもちまちましていてせこいバランといい、そんなバランに惚れて振り回され泣きべそまでかくギャバンの情けなさといい、とにかく鮮烈な映像で見事に描いて見せつけられたものがサイレント時代のベタベタの悪女映画のように(思いつくのはセダ・バラ映画の『愚者ありき』'15とか'20年代イタリアの情痴映画ですが)まるで突き抜けた爽快さも耽美的陶酔感もなくひたすら不甲斐なくて、クレールのように造型的でもなければルノワールのように人間味に寄り添ったものでもない。この映画の場合は情痴メロドラマというテーマ自体を追究するのが映画の目的になっていて、ムードもサスペンスもペーソスも映画にまとわりついてくる情感を片っ端から削ぎ落として単なる情痴メロドラマを描いてみたらどんなものになるか、つまりデュヴィヴィエ映画なら必ず工夫を凝らしてきた要素は一切抜きの純粋情痴ドラマをやってみたのが本作『愛慾』の意図だったとしか思えないのです。ルノワールのイタリア映画『トニ』'34もそういう純粋情痴ドラマで見事に成功した作品で、ルノワール作品中もっとも不人気映画のひとつになりました。本作のグレミヨンについては賛否両論あるでしょうが、『どん底』にも出れば『望郷』にも出て『愛慾』にも出る(そしてどの映画も他の俳優ではこなせない存在感で演じきる)ギャバンの意欲的な姿勢に感嘆しない人はいないでしょう。そして次作が『霧の波止場』、次々作が『獣人』になるのです。まるでギャバンひとりが'30年代後半のフランス映画を背負って立っていたみたいではありませんか。ギャバンは'41年にドイツ軍のフランス侵攻を避けて先に亡命していたデュヴィヴィエ、ルノワールともどもハリウッドに迎えられますが、戦後帰国するまで亡命前の最後のフランスでの作品になったのも'39年7月に撮影を開始し、大戦の勃発で何度もの中断を経て'41年9月に完成したグレミヨンの『曳き船』'41.11でした。同作はグレミヨン流のみずみずしい情感あふれる秀作になっています。本作がアイディアの貧弱さや演出の拙さからこうした作品になったのではないのは『曳き船』からも明らかで、グレミヨンにとって本作が意識的な挑戦だったことがわかります。