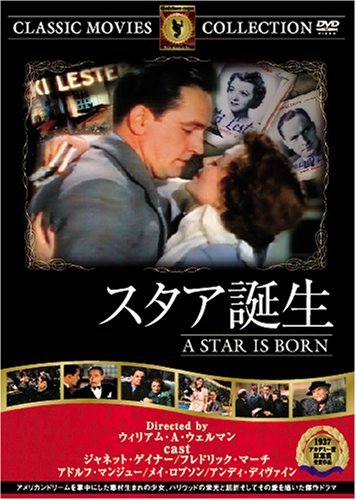
●5月14日(月)
『立ち上る米国』The Conquerors (RKO'32)*86min, B/W; 日本公開昭和7年(1932年)月日不明
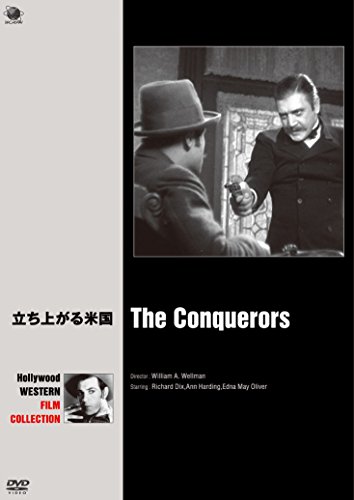
○あらすじ(同上) 1873年、銀行の取付けに会いその衝動のため父親を失ったキャロリン(アン・ハーディング)は、父親の銀行に勤めていた恋人ロジャー・スタンディッシュ(リチャード・ディックス)と結婚して多難な将来に直面した。二人は若者の情熱と愛と信頼をもって西部のネブラスカ州のフォート・アレンの町に移って新しい人生の第一歩を踏み出した。既に当時その町でも強盗団の跋扈甚だしく正義感に燃えたロジャーは遂に彼らと戦って傷ついたが病癒えて後市民の財産を保護するため小さな銀行の経営を始めた。強盗団も掃討されフォート・アレンの町は平和な繁栄を続け、キャロリンは男女の双子(ウォーリー・オルブライト、マリリン・ノールデン)を生んで一家は栄えたが、それから五年の後ロジャーの努力で始めてその町へ鉄道が引かれたとき、汽車に驚いた馬のため無惨ロジャーの息子はその若い生命を奪われ、彼ら一家の前途に一抹の暗影を投じた。軅て一人娘のフランセス(ジュリー・ヘイデン)も十八になって、ロジャーの銀行に勤めているワレン(ドナルド・クック)と結婚した。1892年、突如大恐慌が米国全土を襲った、ワレンの業務上の過失のため、ロジャーの銀行も閉鎖のやむなきにいたり、フランセスが一子ロジャーを生むと同時にワレンは自殺して果てた。その後不屈なロジャーの努力によって銀行も再興の道を辿り、若きロジャー二世(リチャード・ディックス)は欧州大戦に武勲を上げた。そして凱旋後は祖父の志を継ぎ銀行業に精励し、あらゆる困難を克服して進んでいくのだった。

公開時ポスターも雄弁な画像資料ですから感想文にはなるべく本国版、できれば日本公開時ポスターも添えるようにしていますが、本作に限っては原題、邦題、公開年、製作会社、俳優名、監督と思いつく限りで検索しても現行の日本盤単品DVDと本作収録のDVDボックスのパッケージ・ジャケットしか見つかりませんでした。「Conqueror(征服者)」というタイトルの映画は多数引っかかるのですが本作はスチール写真1枚ない。IMDBにも英語版ウィキペディアにも本作の解説項目はあるのですが画像図版はない。どうもここに上げた日本盤DVD2点しか映像ソフトもなく、日本盤が世界初かつ他にないソフト化らしいのです。これはめったにないことで、RKOはメジャー会社ですしアメリカは世界一の映画大国ですが、それだけ隠れてしまった映画も案外あるということでしょう。本作は『人生の乞食』がそうだったような社会派映画路線のウェルマンで、それを大ヒット作『シマロン』風の若夫婦の息子・娘世代からさらに孫世代で現代になる近代アメリカ三代記の形式で描いたもので、グリフィスの『国民の創生』'15以来クルーズの『幌馬車』'23、ラッグルズの『シマロン』'31と周期的に流行る(次に『風と共に去りぬ』'39が来ます)アメリカ人大好きの年代記もので市民階級のアップ&ダウンを描いたものですが、前後作の社会派メロドラマ作品『母』『飢ゆるアメリカ』『家なき少年群』ほどには成功しなかったようです。前年の『民衆の敵』が15万ドルの低予算(まだジェームズ・キャグニーやジーン・ハーロウのギャラも安かった)で製作され大ヒットしたのに対し、本作は62万ドルの製作費に対し23万ドルの赤字になったそうですから映画とはつくづく水物で、本作だってそれなりの映画ではあります。しかし'30年代前半のウェルマンは年間5~6本のペースで長編映画を作っていたので('30年代後半は2~3本ペースになり、'40~'41年度は軍事関係の職務で劇映画の監督は一時休業しますが)、本作もいささかダイジェスト風の作品になったのは仕方がないのでしょう。ポスターがまったく現存しないようなのはRKOピクチャーズがそれだけ宣伝に力を入れなかったということでもあり、『シマロン』の柳の下で営業できればよしとしていた節があります。ウェルマン自身の実力は同時期の成功作でも明らかですし、本作も会社企画をそつなくこなしてちゃんと腹六分目くらいにはなっていて、『シマロン』同様西部劇ジャンルの市民劇として売り出したようですがやはり西部劇のファンには『シマロン』みたいな映画は『シマロン』で十分で、カウボーイも保安官も列車強盗も利権争いもインディアンも出てこない西部劇はどうもなあ、ということだったと思われます。本作自体はそこそこ良い映画なのにウェルマンの器用さが貧乏くじを引かされたようなものだったのでしょう。
●5月15日(火)
『スタア誕生』A Star Is Born (セルズニック・インターナショナル/ユナイテッド・アーティスツ'37)*111min, Technicolor; 日本公開昭和13年(1938年)4月14日・アカデミー賞作品賞/主演男優賞/主演女優賞/監督賞/脚色賞/助監督賞ノミネート、アカデミー賞原案賞受賞・キネマ旬報ベストテン5位

○あらすじ(同上) 北ダコタの寒村に生まれたエスター・ブロジェット(ジャネット・ゲイナー)は夢見がちな乙女心に銀幕のスターを憧れていつも映画雑誌を手から離したことがなかった。愚鈍な田舎者の父親(エドガー・ケネディ)、腕白者の弟(A・W・スウェット)、うるさい叔母のマテイ(クララ・ブランディック)などの中で、若い頃この地方の開拓者であったレティー祖母さん(メイ・ロブソン)だけが彼女を理解し力づけてくれるのだった。そしてある時エスターは祖母さんに勇気づけられ、貯金をもらって夢の国ハリウッドへスターを志して出発した。しかしハリウッドで彼女を待っていたのは就職難だけだった。エキストラの日さえもなく持ち金も残り少なくなったころ、安宿で知合った人の良い助監督のダニイ(アンディ・デヴァイン)の世話である映画関係の宴会にお手伝いとして雇われた。その席で彼女は大スターのノーマン・メイン(フレドリック・マーチ)に会った。この有名なスターは飲酒癖のため名声を落とそうとしているので、プロデューサーのナイルス(アドルフ・マンジュウ)はいろいろと心配しているがききめはなかった。ノーマンは美しいエスターを見ると、同伴していたアニタ(エリザベス・ジェンス)の嫉妬も構わず彼女を家まで送ってやった。そしてエスターの夢が実現するときがきた。ノーマンの紹介でテストを受けた彼女は、ビッキィ・レスターの芸名で華々しく映画界に登場した。次いでノーマンと彼女の結婚が披露されたが、蜜月旅行の途中から呼び戻されたほど彼女の人気は高まっていた。だがノーマンの飲酒は依然として止まず、地位も名声も次第に低まるばかりだった。その年のアカデミー演技賞がビッキィに授与される席上へ、ノーマンは酔った勢いで自暴自棄の醜態を見せるようになっていた。ついに彼は療養所へ送られて疲れた体を治すことになり、映画界からは完全に忘れられて、ただビッキィの優しい愛情とナイルスの友情に守られるのみになった。ようやく退院した彼は宣伝部長リビイ(ライオネル・スタンダー)に罵倒されたことから再び自棄を起こして警察に留置されたが、ビッキィは彼の保釈を願って優しく介抱した。彼女はノーマンの健康を盛り返すために自分は引退しようとまで決心してナイルスに相談したが、隣室で漏れ聞いたノーマンはその夕方妻に淋しい微笑を見せて海岸へ遊泳に出たままついに再び帰らなかった。身も心も打ちひしがれたビッキィは元のエスターに返って田舎に引き上げようとしたが、その時祖母レティーはハリウッドに現れて彼女を励ました。やがて華々しく返り咲いたビッキィは新作の試写会の夜、マイクを通じて全国のファンに「私はノーマン・メイン夫人です」と涙ながらにあいさつするのだった。


カラー作品の効用は本作では実はけっこう線は太いですが大味で都合の良いプロットを気にさせない具合に働いており、これがB/Wだったらリアリズムの基準がぐっとシビアになり、もっと細やかなキャラクター描写が必要になったと思われるのです。大味とはいえこのプロットは細かなエピソードの積み重ねのあるストーリーを必要とするので、人物もそこそこ多ければシーンの数はかなり多く、キャラクター描写に割くような余分なエピソードは冗長になります。プロットを直接支えるエピソードだけでストーリーを構成するとなると人物は最初から一筆描きで印象を与え、ストーリーの中で徐々にその印象が補強されたり変化したりしていく具合に効率を図らなければなりません。アメリカ映画のどこが(総合的には)世界一かというと、映画に限らず20世紀文化自体がアメリカ主導でアメリカ発の文化がほぼ全世界を制覇したのですが、その第一の特徴はと言えば経済性が基準になっていることで、贅を尽くしたもので圧倒もすれば非常に簡素なものでコスト・パフォーマンスの高さを突きつめもしますが、映画について言えば話法の効率化が非常に重視される。アイディアにしてもマテリアルにしてもお金をかけた所はきっちり元を取り、時は金なりですから時間分十分なサーヴィスが提供されるのを観客も期待しますし、それを満たした映画を提供しないと映画社も生き残れない。小津安二郎がルビッチとともにもっとも影響されたと発言しているウェルマン作品は今では散佚して観ることのできない『つばさ』以前の洒落た都会映画のウェルマンでしょうが、『人生の乞食』のウォーレス・ビアリーのキャラクターは小津の『出来ごころ』'33以降の喜八(坂本武)ものの原型とも言え、ウェルマン作品の無駄のないテンポはサイレント時代の小津の教本だったのも興味深いことです。小津がトーキーにサイレント作品とは異なる時間感覚の可能性を見つけたのに対しウェルマンは現在観られる『つばさ』『人生の乞食』ではすでにトーキー以降と同じテンポ感になっていて、もともと場面場面をこってり描くより細かく場面を割っていくタイプで、場面単位ではけっこうあっさりした演出で進めていく。その辺が映画に濃厚な場面を求める現代の観客には昔の映画、単純、軽いと見られるかもしれません。本作のように描き方次第ではドロドロのメロドラマにもできる題材だとなおさらです。しかし本作が一定以上古びようがないのもそのドロドロがないからで、ドロドロを避けられたのもリアリティの次元ではB/Wよりも虚構の次元でドラマを描けもするカラー作品の幸徳で、これをB/Wにしたらワイルダーの『サンセット大通り』'50、マンキウィッツの『イヴの総て』'50、そしてワイラーの『黄昏』'51のようにシビアで痛々しくなりすぎて本作のような哀切ながら後味のすっきりした作品にはならなかったと思われます。有名作だしリメイクの圧倒的好評で何となく本作は未見の方もいらっしゃると思いますが、パブリック・ドメイン版の廉価版DVDならワンコイン価格で手軽に買える名作で、これは名高い映画なのもどなたにも納得のいく作品です。ウェルマンの代表作というと本作ではなく他に上げたいと思いますが、それはそれ、これはこれです。
●5月16日(水)
『翼の人々』Men with Wings (パラマウント'38)*101min, Technicolor; 日本公開昭和15年(1940年)2月7日・キネマ旬報ベストテン9位

○あらすじ(同上) 1903年12月、米国北カロライナ州キティー・ホークの田舎で、ライト兄弟が人類の夢を実現して初めて空中を飛行した。田舎新聞の記者ニック・ランスン(ウォルター・エイベル)はその記事を書いたが、かえって主筆ハイラム(ポーター・ホール)とその相棒ハンク(リン・オヴァーマン)に笑われたので、直ちに辞職して飛行機の制作に没頭した。彼の飛行機は見事に飛んだが、不幸にも墜落して尊い犠牲となる。彼の娘ペギー(ヴァージニア・ワイドラー)は父の血を受けて幼い時から飛行機に興味を持ち、友達の少年パットことパトリック(ドナルド・オコナー)とスコット(ビリー・クック)がその仲間だった。1914年欧州大戦開始の年、3人が苦心して制作した飛行機は当時のスピード記録を破り、パトリック(フレッド・マクマレイ)とスコット(レイ・ミランド)は飛行場で働くことになった。やがてパトリックは義勇軍として出征し、空中戦で幾多の功績をあげ、スコットはワシントンで陸軍技師として飛行機の設計にあたった。母(キティー・ケリー)を失ったペギー(ルイズ・キャンベル)は電話交換手となってフランスの戦線へ行き、パリでパトリックと結婚した。スコットも彼女を愛していたが、2人のために心から幸福を祈った。休戦と共にパトリックは米国へ帰ったが戦争の経験が忘れられず、ペギーが女の子を生んだ日にモロッコの戦線へ義勇軍として出発した。スコットは郵便飛行の開拓に身を捧げながら寂しく留守を守るペギーを慰めていた。足に負傷して帰国したパトリックはスコットの忠告を入れてフォーコナー飛行機制作会社の社長となったが、空への憧れを忘れ得ず、1927年大西洋横断飛行の懸賞に応募したが海中に不時着し、危うくスコットと助手のジョウ(アンディ・デヴァイン)に救われた。機器に頼る飛行術が発達したいまでは、パトリックのように勘と腕力に頼る飛行機は役立たなかったのである。彼が2人に救われた日に、リンドバークが大西洋へ向けて出発したのであった。1929年米国を襲った不況はフォーコナー飛行会社を破産させ、パトリックは再び活路を求めて外国へ行った。それから長い間、スコットは会社を甦生させるため爆撃機の政策を研究し、ペギーやジョウの外にハイラムやハンクの助けを得てついに完成した。彼の苦心は実を結んでその爆撃機は米国陸軍の軍用機として採用された。がパトリックの行方は沓として知れなかった。1938年のフォーコナー会社の爆撃機完成5周年記念の祝賀会当日、パトリックが外国で墜落惨死した電報が届いた。涙を隠して席にでたペギーとスコットは、今日の会社の隆盛こそ、その生みの親たるパトリックに捧げる最大の贈物であると語った。

時期的にも本作の'38年というと国威発揚ムードをぎりぎりかわしており、軍用機の需要で会社再建というのも戦争(というよりは空軍パイロット)好きの夫に戦死されたヒロインにとってはずいぶん皮肉でもあるはずですが、本作についてはそうした見方はうがちすぎで、ヒロインはより操縦性と安全性の高い軍用機の提供が夫の遺志にかなうと信じていると取る方が素直な見方でしょう。本作が9位に選ばれた昭和15年度('40年)のキネマ旬報ベストテン外国映画部門は以下の通りです。
1.『民族の祭典』(レニ・リーフェンシュタール)
2.『駅馬車』(ジョン・フォード)
3.『最後の一兵まで』(カール・リッター)
4.『コンドル』(ハワード・ホークス)
5.『美の祭典』(レニ・リーフェンシュタール)
6.『スタンレー探検記』(ヘンリー・キング)
7.『カッスル夫妻』(ヘンリー・C・ポッター)
8.『ゴールデン・ボーイ』(ルーベン・マムーリアン)
9.『翼の人々』(ウィリアム・A・ウェルマン)
10.『幻の馬車』(ジュリアン・デュヴィヴィエ)
昭和16年・17年度は戦争のため外国映画上映規制に伴い日本映画のみのベストテン、昭和18年、19年、20年度は戦局によりベストテンは行われませんでした。上記ベストテンを見ると『駅馬車』『コンドル』『翼の人々』(6, 7, 8位もアメリカ映画ですが)など健康で理想主義的なアメリカ大衆映画が大東亜戦争まっただ中、昭和16年12月には太平洋戦争という時局にあって日本の映画観客の良心を感じます(それでも1, 5位は『民族の祭典』『美の祭典』ですが)。『駅馬車』『コンドル』『翼の人々』が最後に観た外国映画になって敗戦までに亡くなった日本人も大勢いるということです。傑作中の傑作『駅馬車』『コンドル』にはおよばないにせよ、誠実な佳作の本作をベストテン9位につけた(キネマ旬報は批評家投票ですが)日本の映画観客の声には切実な思いを感じます。