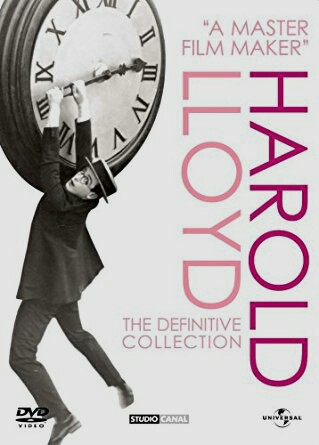

『田吾作ロイド一番槍』(別題『キッド・ブラザー』) The Kid Brother (ハロルド・ロイド・コーポレーション=パラマウント'27)*82min, B/W, Silent : https://youtu.be/vukF6jLaUiU
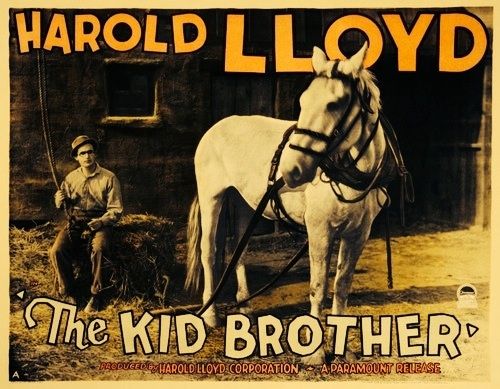
○西部の村で人々の尊敬を集める保安官ジム・ヒコリー。その三男ハロルドは頭の回転は早いが、ひ弱な青年で子供扱いされていた。そんなある日、村に医薬品の宣伝販売を行う旅回りの一座がやってくる。一座の娘メアリーと仲良くなったハロルドだが、一座の男たちは保安官のジムから村のダム建設資金を盗んで逃亡してしまい、メアリーのためにハロルドは……。

この作品がジョビナ・ラルストン(1900-1967)の6作目のロイド作品のヒロイン作で最後のロイド映画出演になり、ラルストンは同年のウィリアム・A・ウェルマンのアカデミー賞受賞作『つばさ』'27でビリング(配役序列)4番目の優雅で妖艶な副ヒロインを勤めて喜劇映画から離れることになります。『つばさ』の洗練された美女役のラルストンを観て『猛進ロイド』や『ロイドの人気者』の純情素朴で可憐かつ勝気なヒロインと同一女優とすぐに気づく人は、当時はともかく現代の観客にはほとんどいないのではないでしょうか。筆者もロイド作品、『つばさ』ともさんざん観ていながら今回のロイド長編感想文を書き始めてようやくラルストンの経歴を調べ、『つばさ』の副ヒロインの都会育ちの妖艶なおねいさんだったのには仰天したほどです。もっともラルストンはロイド映画の2代目ヒロイン初登場の『ロイドの巨人征服』の看護婦役からはかなりイメージが変化しており、ロイド映画ですから健全なものですが、本作でもびしょ濡れのジョビナをロイドが連れてくると家でパジャマ姿になっていた武骨な兄たちが恥ずかしがって逃げ回るくらいの女っぷりでなかなかのものがあり、そういえば本作は保安官時代という設定、メディシン・ショーという道具立てを取ってみればロイドのサイレント長編唯一の西部劇と呼べる作品であり、保安官への自警団によるリンチという内容では相当ぎりぎりの異色西部劇と言えるので、ロイドの奮闘が家族救出という献身的な動機に基づいている点で恋愛もの以外のロイド喜劇の努力が名誉欲や金銭欲だったりする(それもアメリカ的率直さなので批判には当たりませんが)のに対して爽やかなのは、そうしたキャラクター設定にあるとも言えそうです。本作がギャグが主体というより、ほどほどにギャグを散りばめて起伏に富んだストーリー展開に重点を置いているのもロイド長編としてはかつてないほどドラマティックで、かつ成功しており、喜劇映画としてのギャグの豊富さや抱腹絶倒というような要素は抑制して、じっくりと、かつサスペンスに富んだ異色西部劇になっている点が本作を、ロイド喜劇には似合わない褒め言葉ですが、渋い名作にしているのでしょう。サイレント喜劇のロイド、という点では『要心無用』、ロイドならではのロマンティック・コメディでは『猛進ロイド』、大学生という題材の青春コメディでは『ロイドの人気者』ですが、映画としての完成度は喜劇風異色西部劇の本作、とする見方もできると思います。これは喜劇としては衰退かもしれませんが、観客の関心がギャグよりもドラマに移っているのを鋭敏に作品に反映させたと見る方が良さそうで、それは次作『ロイドのスピーディー』にも言えます。
日本公開時のキネマ旬報では、本作は「『ロイドの福の神』に続くハロルド・ロイド氏主演喜劇で、永らくハル・ローチ撮影所のギャグ・マンたりしテッド・ワイルド氏が監督したもので、対手女優は例によってジョビナ・ラルストン嬢が勤め、ウオルター・ジェームズ氏、コンスタンチン・ロマノフ氏、エデイー・ポーランド氏、ラルフ・イアズリー氏等が助演している。」と沿革だけが書かれていますが、監督フレッド・ニューメイヤー(第1~3長編)、ニューメイヤー&サム・テイラー(第4~6長編)、テイラー&ニューメイヤー(第7、8長編)、テイラー(第9長編)と来て、サム・テイラーも脚本家上がりの共同監督でしたがテイラー主導時期に主力脚本家だったテッド・ワイルドが本作では監督昇進(J・A・ハウは監督補)し、次作でもワイルドが監督してサイレント長編の最終作になります。また本作はノンクレジットでルイス・マイルストン、そしてロイド自身が監督を勤めたパートを含むそうで、90分弱の長さはこれまでのロイド作品最長ですし、リアリティに満ちた西部の田舎町の場景、自警団による保安官のつるし上げのエキストラの多さとリアリズム的描き方などは脚本家上がりの監督ならではの構成力と第2班、第3班に演出を分担した形跡が認められます。ヒッコリー家でジョビナをめぐる兄たちの動揺とそれをからかうロイド、またほとんど固定カメラのラスト・シークエンスなどはロイド自身がさっさと監督して撮ってしまったのでしょう。ロイドは映画デビューの1913年~15年に短編26編、'15年に始まる放浪青年「ロンサム・リューク」シリーズには'17年までに短編77編(年間40編!)、'17年に始まる、ロイドのキャラクターを決定した「眼鏡と帽子」のハロルドの中短編は'21年までに95編が長編時代以前にあるだけに、短編単位のシークエンスなど自作自演監督などお手のものだったと思われます。クライマックスの悪党フラッシュとの繋船内での対決もロイド主導だったかもしれません。しかしチャップリン、キートンのように監督クレジットは自己名義にせず、ハル・ローチ・プロダクションでは主演俳優、ロイド自身のプロダクションで独立後は主演俳優兼プロデューサーでローチ時代同様に実質的には総指揮をしながら監督、脚本のクレジットはスタッフに与えたのは、それだけスタッフの功績を認めることでチーム力を高めたかったからでしょう。チャップリンなら全部自分の功績、キートンの場合は企画の自由は与えられておらず、またプロダクション側もキートンの監督としての実力を評価していたというより利用していた面があります。本作は'20年代前半までのとにかくギャグで押す喜劇からは明らかに変質したものですが、そうした作品はロイドはすでに何作も決定版を世に送っていたのですから、作風の変化もごく自然ですし、弱虫が奮起する展開はロイドの定番キャラクターで『豪勇ロイド』のリメイクとも言えて一貫性もちゃんとあります。名作、ただしやはりロイドの全盛期は長編第6作『猛進ロイド』か、ぎりぎり長編第8作『ロイドの人気者』という感じもするのです。
●6月11日(月)
『ロイドのスピーディ』 Speedy (ハロルド・ロイド・コーポレーション=パラマウント'28)*86min, B/W, Silent : https://youtu.be/QcgBK1y7dIo
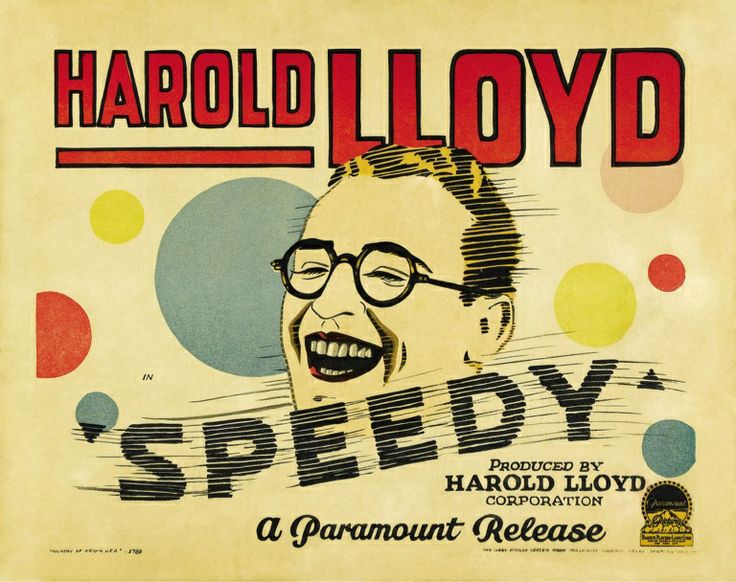
○野心家でお調子者のスピーディーは、いつも野球に夢中で仕事をクビになってばかり。恋人ジェーンとの結婚を夢見る彼だが、彼女の祖父が心配だった。鉄道馬車を運営する祖父は大手鉄道会社の買収工作に悩んでいたのだ。そんなある日、鉄道会社が力ずくで路線を奪おうと企んでいると知ったスピーディーは……。
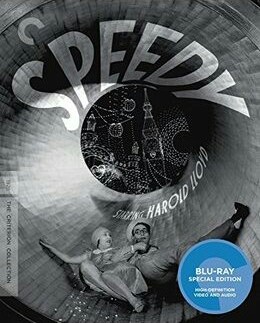

クライマックスは馬車奪還と目的時刻までに終点まで馬車を運行する大暴走なので、馬車奪還がまず小クライマックス、終点まで馬車を猛突進させるのが大クライマックスなのですが、'20年代も末近い頃にもニューヨーク市街で路面電車ならぬ路面馬車(二頭立ての貨物馬車ですが)が走っていたとは、これまでも他の映画で観ていたかもしれませんし本作だって学生時代に観ていたのですが、珍しい世相風俗として見たのは今回観直したのが初めてでした。先月スコリモフスキの映画を観直して初期作品はどれも路面電車を上手く使っていたので(これも1本、また間を置いて1本観ていた時は気づかなかったことです)、ロイド映画の路面電車は『要心無用』『猛進ロイド』に出てきますが本作は路面馬車自体が題材なので、『ロイドの人気者』でロイドが自称していた「スピーディー」というニックネームが映画前半ではタクシー運転手、後半では路面馬車という具合にうまく流用できたわけです。このあたりのつじつま合わせというか、連想形式のように類似した主題のヴァリエーションを並べてテーマの連続性と統一が巧みなのはロイドの場合後になればなるほど巧妙になっていて、スラップスティック喜劇としての起爆力は初級~絶頂期作品の方が高かったのですが映画作りのうまさで点を稼いでいるのはさすがです。これは徹頭徹尾スラップスティック喜劇俳優兼監督だったキートンにはできないことで、キートンが出演作の監督権を奪われたのもそうした資質が時流に合わないと見なされたからでした。コニー・アイランド遊園地のシークエンスはやや冗長さを感じますがアメリカ全土の映画観客にとっては大都会ニューヨーク、その名物遊園地コニー・アイランドとは憧れの場所だったでしょうし、これも貴重な世相風俗として歴史的映像的価値があるでしょう。ロイドとクリスティーが遊んでいるのはもちろん演技ではありますが、実在の遊園地で遊ぶ光景とは、手法的にはドキュメンタリーになります。つまり映画のシーンのためにせよ実際にロイドがコニー・アイランド遊園地で遊んでいるのが観られるので、アメリカ人の大多数は一生コニー・アイランド遊園地はおろかニューヨーク観光もする機会はありませんし、実生活ではお金持ちのロイドでも映画人ですからハリウッド近郊に住んでいて盛り場といえば西海岸ですからロサンゼルスです。コニー・アイランド遊園地のロケーションとベーブ・ルース絡みのシークエンスはニューヨーク撮影でしゅうが、映画全体は当然パラマウント社のハリウッド撮影所でしょうし、ベーブ・ルース以外のタクシー運転シークエンスや映画冒頭のロイドがクビになるカフェ、祖父ポップの家や中盤以降の路面馬車騒動は、ニューヨーク・ロケ時に撮影してきた路面馬車をそっくりそのままハリウッド撮影所内のオープン・セットのニューヨーク市街(日本では「江戸村」がそうですが、ハリウッドの撮影所には世界主要都市を再現したオープン・セットがいつでも使えるように建っているので、ニューヨーク市街などもっとも使用率の高いオープン・セットです)に違和感なく路面馬車のルートを敷設し(さすがに路面馬車を出す映画は少ないでしょうからオプションでしょう)、後半の騒動と馬車盗難~奪還、終点までの猛突進はすべてハリウッドの撮影所のオープン・セット内の撮影でしょう。中盤~後半にもあちこちニューヨーク撮影の部分がはめ込んであると思われます。日本公開時のキネマ旬報では本作は「『田吾作ロイド一番槍』についで製作されたハロルド・ロイド氏主演喜劇で、ロイド喜劇専属のギャグマンとして有名なジョン・W・グレイ氏がレックス・ニール及びハワード・ロジャース氏と合作した台本により『田吾作ロイド一番槍』『怪物団若返る』と同じくテッド・ワイルド氏が監督したもの撮影技師も『ロイドの初恋』『ロイドの福の神』『田吾作ロイド一番槍』のウォルター・ランディン氏である。助演者は新たにロイド氏に見出されたアン・クリスティ嬢を始め、トム・オブライエン氏、バート・ウッドラフ氏、ブルックス・ベネディクト氏等で本塁打王ベーブ・ルース選手も特別出演している。」とやはり、野球界の大スターのホームラン王ベーブ・ルース出演も本作の話題だったようです。
そう考えるとコニー・アイランド遊園地に向かう電車は名優犬キング・タットが出てきますから、実際の車中ロケとは考えにくいことになります。舞台がロサンゼルスやサンフランシスコなら近郊ですから、鉄道会社に交渉して、営業時間外を借りて犬やエキストラ俳優たちを乗せることもできるでしょうが、ニューヨークとなるとエキストラは現地調達できてもロイドとクリスティーと名優犬キング・タットは変えが利きません。ロイドとクリスティーはコニー・アイランド遊園地で遊ぶシーンのロケ、ついでにニューヨーク街中のデートのロケ、ロイド個人はベーブ・ルースと共演するロケがありますからニューヨーク・ロケは欠かせないとして、名優犬とはいえハリウッドからニューヨークとなると気候の違いだけでも難があるでしょう。ニューヨークとハリウッドでそっくりの別な名優犬を使った、というのも人材豊富なアメリカとはいえ考えづらいので、名優犬優先で実際にコニー・アイランド遊園地行きの車両そっくりの電車を用意して、乗り降りはロイドとクリスティーがニューヨーク・ロケで撮ったショットで車中はハリウッド撮影、と考えた方が良さそうです。また、タクシー運転手のロイドがベーブ・ルースを乗せるあのよそ見運転のシークエンスは、スクリーン・プロセスではないことに迫力があり、おそらく逆ハンドルの車を使い、右座席に本当の運転手がいて、ロイドのハンドルは作り物で、対向車や横断車や追い越し車は厳密に打ち合わせして、ロイドとベーブ・ルースの乗るタクシーと併走する車からタイミングの指示出しをしたと思いますが、スラップスティック喜劇とはアドリブ的マイム芸とこうした大掛かりな計算の仕掛けの両面があるのがチャップリンやキートン作品以上にロイド喜劇ではよくわかります。またこのシークエンスではサイレントながらベーブ・ルースのなかなかの役者ぶりが楽しめます。本作はロイドが最後のサイレント長編で再びダイナミックなスラップスティック喜劇を作って成功作になったことでも喜ばしく、実は次作『危険大歓迎』'29も一旦サイレントで完成され、試写会後に追加撮影と再編集でトーキー第1作として公開された作品でした。本作『ロイドのスピーディー』は『田吾作ロイド一番槍』同様に演出はトーキーに近づいていて、台詞字幕の代わりにサウンドで台詞が入っても違和感ない、自然な流れの映像でサイレント技法の円熟を究めた作品です。映画はトーキーになって沈黙恐怖症になってしまい、音のない場面や台詞のない演技が忌避されようになり、それが良くも悪しくもサイレント映画とトーキー以降の映画に断絶を作ることになります。次回からはトーキー作品のロイドで、またちょっと感想文に手こずりそうです(手こずるのはいつものことですが)。