映画日記2018年8月28日~29日/ カール・Th・ドライヤー(1889-1968)の後期作品(2)
前作で最後のサイレント作品になった第9作『裁かるゝジャンヌ』'28も監督カール・Th・ドライヤーはトーキー作品にしたい希望でしたが、機材面での製作技術上の困難と、まだヨーロッパ映画界ではトーキー作品への移行が本格化しておらず上映設備を導入する映画館も少なかったため結局同作はサイレント時代最後期を飾る映画史上の大問題作として名を残すことになります。フランスでカトリック教会や右翼ばかりか左翼からも怒りを買って相当箇所が宗教的・政治的理由から検閲でカットされたのも当然で、あのアナーキーな結末は当時~戦後の共産圏からどう受けとめられたのかも気になるところです。ドライヤーがサイレント時代にタイトル字幕製作・フィルム編集者として入社し、監督デビューしたのは母国デンマークの映画会社ノーディスク社でしたが、同社の社員監督だったのは最初の2長編『裁判長』'19、『サタンの書の数頁』'20だけで、フリーになったドライヤーは第3作はスウェーデン(『牧師の未亡人』'20)、第4作はドイツ(『不運な人々』21)に招かれ、第5作はひさしぶりにデンマーク(『むかしむかし』22)で映画を撮りますが、第6作のドイツ作品『ミカエル』'24、第7作のデンマーク作品『あるじ』'25で国際的な名声を確立したのは前回のご紹介通りです。ノルウェーで小品の第8作(『グロムダールの花嫁』'25)を撮った次にドライヤーはフランスの映画会社から超大作の歴史ヒロイン映画の企画を依頼され、マリー・アントワネットかカトリーヌ・ド・メディシスかジャンヌ・ダルクの三択だったそうですが、結果作られた『裁かるゝジャンヌ』がいかにとんでもない映画になったかも前回その一端をご紹介しました。『~ジャンヌ』は映画批評家からも観客からも絶賛され国際的に上映されながらあまりに膨大な製作費を回収できず製作映画会社倒産、という大赤字作品になり、ドライヤーは独立プロを設立して製作依頼を募るようになりました。ベルギーの亡命ロシア貴族子息の青年貴族ニコラ・ドゥ・グンツブルグ(1904-1981)男爵が自分の主演映画をという依頼でドライヤー・プロダクションが製作したのが4年ぶりになるドライヤー第10作で初のサウンド・トーキー作品『吸血鬼』'32(配給はフランスのトビス・フィルム)であり、次の17世紀初頭の魔女狩り時代を背景にした長編第11作『怒りの日』は『吸血鬼』から11年ぶりの'43年にヴェネツィア国際映画祭への出品と受賞でようやく一般配給上映されることになります。第二次世界大戦中に生活費のために映画会社の依頼を受けた長編第12作『二人の人間』'45は企画内容も仕上がりも映画会社側に改竄されたとしてドライヤーは自作と認めていないので、戦後の第13作『奇跡』'55、逝去4年前の第14作『ゲアトルーズ』'64がドライヤーの遺作となり、ほか'40年代~'50年代のドキュメンタリー短編8編がドライヤーの全作品になります。ドライヤー非公認の『二人の人間』を除けばドライヤーは『裁かるゝジャンヌ』以降の約40年で長編4作しか作っていませんが、そのどれもが10年に1作の極端な寡作を納得させる驚くような映画になっているので、今回と次回は果たして感想文の体をなすのかまったく自信がありません。観直してみて、またもやただただ圧倒されたとしか言いようがないのです。
●8月28日(火)
『吸血鬼』Vampyr - Der Traum des Allan Gray (Carl Theodor Dreyer-Filmproduktion=Tobis-Filmkunst'32.May.30)*72min, B/W; 日本公開1932/11/10 : https://youtu.be/q8JhOyzZS9k (Full Movie)
[ あらすじ ](同上) 夢想家であり、奇人であるアラン・グレー(ジュリアン・ウェスト)はある夜おそくクルタンピエール村の寂れた旅館へやって来る。その周囲の凄惨な光景が彼に強い印象を与えた。そして世にも不思議な夢を見る。――老婆(ヘンリエッタ・ジェラード)の姿をした吸血鬼がある村医者(ジャン・ヒーロニムコ)とその助手なる義足の男(ジョルジュ・ボワダン)とを自分の忠実なる家来にする。この吸血鬼はかつて世にあり紙時犯した罪悪のために墓場に入っても静安を得ることの出来ない女亡者で人間の生き血を吸わねば生きていられないのである。まず第一の犠牲者はある城主(モーリス・シュッツ)の娘であるが吸血鬼は例の義足の男を唆して城主を殺させる。その城主の客となったアランはある古い記録によって吸血鬼の存在とその魔力とについて学ぶ。殺された城主の二番娘ジゼール(レナ・マンデル)とアランとの間に強い愛情が生ずる。吸血鬼に見込まれた病めるレオーヌ(シビル・シュミッツ)は医者のたくらみの為に自殺しようとする。医者はアランを説きつけて輸血を承諾させたのであった。最後の瞬間に忠実な老僕(アルベール・ブラース)の感づくところとなりレオーヌの自殺の企ては遮られ毒殺の瓶は彼女の手からもぎとられる。その毒薬はかの吸血鬼がレオーヌに飲ませるべく医者に渡したものであった。老僕は記録を漁った結果、吸血鬼を退治する方法とレオーヌの生き血をすすった老婆が昔クルタンピエールに住んでいてずっと以前に死んだマルグリット・ショパンであることを知る。アランは吸血鬼に恐ろしい妖怪談を聞かされるが、それにも拘わらず老僕を助けてマルグリット・ショパンの墓を揆き死人の心臓に鉄棒を突き刺すことによって吸血鬼を退治する。そこで吸血鬼の魔力は失われ、レオーヌに祟っていた隠霊は消えてしまう。医者と義足の男はその罪によって殺される。アランは彼が医者の手から救い出したジゼールと共に夜の恐怖の去った輝かしい夏の朝を迎える。夢はここで終わっている。
キネマ旬報のあらすじは全編を夢の中の出来事としていますが、映画は物語上は次に主人公アランが怪しい老婆に呼ばれて影と離脱する男を目撃し、その男を追ううちに霧の中を迷い、一軒の館に辿り着きます。そこは先の老紳士の屋敷で、娘二人と使用人夫婦が暮らしていました。当主はアランが目撃した影に射殺され、姉の方は病に伏せっています。封筒を使用人が開けると吸血鬼に関する本で、使用人は食い入るように読み始め、それが字幕で示され、一家を襲った吸血鬼の呪いの悲劇の原因が判明します。姉を往診する医師の様子は明らかに怪しく、皆の血を採血して彼女に与えます。「精血を完全に吸い取ると、吸血鬼はあらゆる手段で犠牲者を自殺に追いやる」と本の一節が映り、姉は毒をあおろうとし、アランがそれを阻止します。翌朝、濃霧の中を散歩するアランがベンチで休むと、魂が離脱し、ある家の中に棺に横たわる自分をみる。ガラス越しに覗く隣室にはベッドに縛りつけられた妹の姿があり、幻の彼はそれを助けようとしますが動けません。「塵から生まれ塵に帰る」と内側に書かれた棺の蓋が閉まると、ショットは棺桶の窓から見たアランの死体の視点に切り替わり、教会に運ばれるまでの風景が映ります。棺を担ぐ列がベンチに眠るアランを過ぎるとそこで消え、アランの魂は舞い戻ります。一方、使用人は警官を呼んで墓地へ行き、過去に吸血鬼に囚われ昇天していないという老婆の亡骸の心臓に杭を打ちます。それとともに長女レオーヌの呪いは解け、アランは医師を追い、幻視した家に追いつめ、その義足の助手は階段を転げ落ちて死にます。医師は粉挽き小屋に逃げ込むが、水車や歯車が回り出し、老婆の手下だった医師は白い粉に埋もれて絶命します。アランは次女ジゼールを助け出すと、小舟に乗せて漕ぎ出します。本作は一応原作を19世紀のアイルランド作家シェリダン・レ・ファニュ(1814-1873)の短編集『In a Glass Darkly』1872から短編「吸血鬼カーミラ」を中心にドライヤーが脚本を書き、念頭にあったのは1927年からベラ・ルゴーシ主演でニューヨークでヒットしていた舞台劇『吸血鬼ドラキュラ』で、『裁かるゝジャンヌ』'28のあと'29年には脚本を仕上げ、'30年には大半の撮影を終えていたそうですからトッド・ブラウニングの『真夜中のロンドン』'28よりは後ですがブラウニングの『吸血鬼ドラキュラ』'31より早かったわけです。本作はまだサイレントとサウンド・トーキー技法の混在があり、音楽や効果音はありますが台詞のないシークエンスもあり、また書物の頁を映してタイトル字幕代わりにする手法も頻繁に見られます。これについてはドライヤーは本作では「本も登場人物の一つ」と見なしていたということによるそうです。サイレント作品にするかサウンド・トーキー作品にするかは'30年中の完成・公開ならヨーロッパではまだサイレント作品でも良かったからなのですが、結果的にヨーロッパでもトーキー化の完了した'32年公開になったため、サウンド映画ならではの効果とサイレント作品の手法が混在したのも本作の異様な雰囲気にはプラスに働いています。『裁かるゝジャンヌ』は顔のアップと背後の壁、という具合にB/W映像のほとんどが白っぽい映画でしたが、『ミカエル』'25と同作で撮影を担当したカメラマン、ルドルフ・マテは本作ではレンズの前にガーゼのフィルターをかける手法を考案し、幽体離脱の二重撮影の多用とともにガーゼのフィルター越しの白っぽい映像が本作を『裁かるゝジャンヌ』以上に白っぽい映像の映画にしており、老婆の手下の医師も脚本段階では沼地に沈む最後でしたが水車小屋の粉挽き車の小麦粉に埋もれて絶命する具合に変えたのは、偶然ロケ地で水車小屋を見つけたからだそうで(もっとも実際に使ったのは石灰だそうですが)、何とこの映画、俳優も城主とヒロイン(次女ジゼール役)だけ職業俳優で他の出演者は全員素人、壮絶な末期を遂げる医師も地下鉄駅でドライヤーがスカウトしてきたばかりか、小道具や多少の大道具はあったでしょうが驚きの全編ロケーション撮影だそうです。この映画の、とても現実のものとは思えないような映像が一切セットではないとはそれ自体も驚異的で、ドイツ映画の『カリガリ博士』'19や『ニーベルンゲン』'24、ハリウッド映画の『真夏の夜の夢』'35や『オズの魔法使』'39の人工的な異世界とは違った異様さがあり、ムルナウの『吸血鬼ノスフェラトゥ』'22やブラウニングの『吸血鬼ドラキュラ』のような吸血鬼映画を期待するとおよそホラー映画の要素も稀薄なのに、感覚的にまとまりのない悪夢そのものが迫ってくる気味悪さがあります。故・伊丹十三氏が監督長編映画第1作『お葬式』'84のスタッフ・キャストに本作を参考試写して観せたのはよく知られた話で、同作は古今東西の映画を参考にしたショットだらけですが、『吸血鬼』からは死体の視点からのショットをまるまる使っていました。『お葬式』をご覧の方は本作でそのシークエンスになるとびっくりなさると思います。映画でパクっていいこととまずいことがあるのがわかります。
●8月29日(水)
『怒りの日』Vredens dag (Carl Theodor Dreyer-Filmproduktion'43.Nov.13)*93min, B/W; 1947年ヴェネチア国際映画祭審査員特別賞受賞 : 日本公開2003/10/11 : https://youtu.be/6_SATxIRMts (Trailer)
[ あらすじ ](同上) ノルウェーの小さな村で暮らす牧師アブサロン(トルキル・ロース)の後妻に迎えられたアンヌ(リスベット・モヴィーン)は、アブサロンの息子・マーティン(プレーベン・レアドフ・リュエ)と惹かれ合う。しかし、彼女には魔女狩りの手が迫っており……。
老農婦マーテは魔女裁判の席上で、裁判官の司祭に「私を裁くならあんたも裁かれることになるよ!」と預言します。またマーテとアンヌのやり取りを聞いた観客はアブサロン牧師がかつてアンヌの母を魔女裁判で弁護したのを知っているので立会人になっている牧師がかつての裁判をむしかえされたくないためかえって傍観する一方なのを観ることになります。こうしたことすべてがアンヌを幻滅させ、マーティンとの逃避的な恋につながって行きます。マーテの処刑の後でますます露骨にマーティンと出かけるようになり、明るく若々しくなったアンヌを夫のアブサロンはマーティンの若さのおかげだ、と母の前で喜び、アブサロンの母はますますアンヌを憎みます。やがて司祭が病気になって危篤の報に牧師はおもむき、その晩は嵐になります。司祭は魔女マーテの言うとおりになった、と牧師に告げて逝去します。牧師館では二人きりになりたいアンヌとマーティンが起きて待っていますが、老母も居間から引きません。アンヌは先に寝ます、と引き上げ、残った孫のマーティンになぜアンヌを嫌うのか問われ、牧師の母ははっきりとあの女は虫が好かない、家に入れたのが間違いだった、と吐き捨てます。やがてマーティンと老母が寝室に引き上げてからアンヌは居間に戻ってきて、司祭の臨終を看取って帰ってきた夫アブサロンを迎えます。死と罪のことばかり考えて帰ってきた、という夫に、アンヌは私もずっとあなたの死のことばかり考えてきた、結婚以来ずっとあなたの死だけを考えてきた、と言い放ちます。ショックを受けた牧師は昏倒し、マーティンと老母が駆けつけてくると事切れています。そして、アブサロン牧師の葬儀の場で、アンヌは牧師の老母メレーテに悪魔の力によって夫を殺し、マーティンを誘惑した、と魔女として告発されます。ここまでで映画の9割強の展開をたどってきましたが、デンマーク近世版嫁姑話の本作の結末はおそらく原作準拠でもあるだろうし、この映画でもこれ以外には動かないだろうというほど力強いものです。17世紀初頭のデンマーク(キネマ旬報あらすじのノルウェーは間違い)という近世のプロテスタント国でもこうした中世のような魔女裁判が行われていたのを生々しく観ることができるのもこの映画の興味になっていますし、それが社会構造はほぼ近代的な市民社会になっている生活描写とないまって、歴史映画を観ている感じはまったくありません。それこそちょっと田舎に行けば今でもこうした魔女狩りが行われていそうな雰囲気といっていいくらい現代劇と同じ感覚で、それがかえって恐ろしい効果を上げています。本作のヒロインのアンヌはとりたてて賢くもなければ美人でもなく、おそらくこのようなシチュエーションでもなければ通常映画のヒロインには描かれないような人間です。「牧師の若い後妻」という属性以外生活に何もないような空虚さを絵に描いたような若い女性として描かれていて、いわばボヴァリー夫人以前のボヴァリー夫人ですが、そういった人間が陥る悲劇をきっちり定着させるには不寛容で嫉妬に満ちた狭い人間関係と、それがどのように噴出するかを明確な時代相の中に置いてみなければならない。この映画はまったく面白さを感じない人も多いでしょうし、結末には反感すら感じる人もいるでしょうが、個人の嗜好を超えた傑作というのも映画の中にはあり、『怒りの日』以降のドライヤー作品3作はいずれもそれに該当します。また、ヒロインの受難劇を追及してきた映画監督の第一人者と言えば溝口健二ですし、溝口は『怒りの日』以降のドライヤー作品は観る機会がなかったと思いますが、テーマについても演出技巧の面でも、本作と『ゲアトルーズ』は溝口に感想を訊きたかったと思えてくるような作品です。
●8月28日(火)
『吸血鬼』Vampyr - Der Traum des Allan Gray (Carl Theodor Dreyer-Filmproduktion=Tobis-Filmkunst'32.May.30)*72min, B/W; 日本公開1932/11/10 : https://youtu.be/q8JhOyzZS9k (Full Movie)
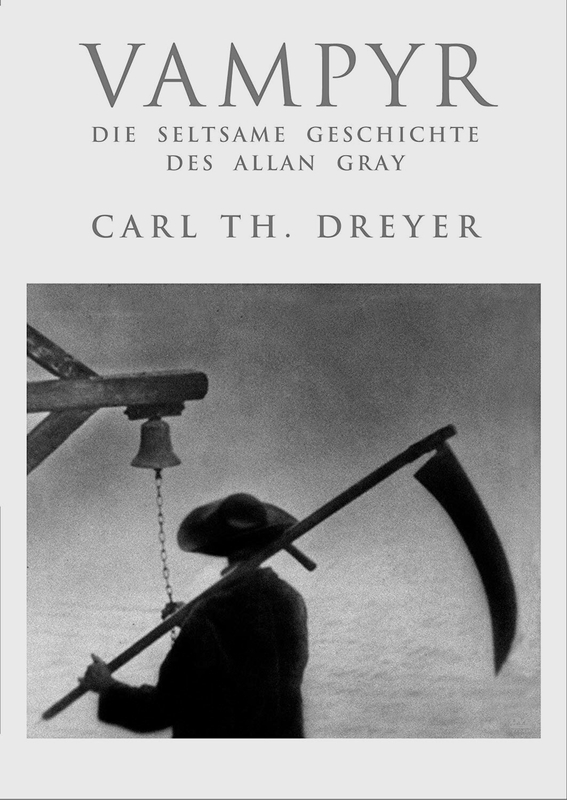
[ あらすじ ](同上) 夢想家であり、奇人であるアラン・グレー(ジュリアン・ウェスト)はある夜おそくクルタンピエール村の寂れた旅館へやって来る。その周囲の凄惨な光景が彼に強い印象を与えた。そして世にも不思議な夢を見る。――老婆(ヘンリエッタ・ジェラード)の姿をした吸血鬼がある村医者(ジャン・ヒーロニムコ)とその助手なる義足の男(ジョルジュ・ボワダン)とを自分の忠実なる家来にする。この吸血鬼はかつて世にあり紙時犯した罪悪のために墓場に入っても静安を得ることの出来ない女亡者で人間の生き血を吸わねば生きていられないのである。まず第一の犠牲者はある城主(モーリス・シュッツ)の娘であるが吸血鬼は例の義足の男を唆して城主を殺させる。その城主の客となったアランはある古い記録によって吸血鬼の存在とその魔力とについて学ぶ。殺された城主の二番娘ジゼール(レナ・マンデル)とアランとの間に強い愛情が生ずる。吸血鬼に見込まれた病めるレオーヌ(シビル・シュミッツ)は医者のたくらみの為に自殺しようとする。医者はアランを説きつけて輸血を承諾させたのであった。最後の瞬間に忠実な老僕(アルベール・ブラース)の感づくところとなりレオーヌの自殺の企ては遮られ毒殺の瓶は彼女の手からもぎとられる。その毒薬はかの吸血鬼がレオーヌに飲ませるべく医者に渡したものであった。老僕は記録を漁った結果、吸血鬼を退治する方法とレオーヌの生き血をすすった老婆が昔クルタンピエールに住んでいてずっと以前に死んだマルグリット・ショパンであることを知る。アランは吸血鬼に恐ろしい妖怪談を聞かされるが、それにも拘わらず老僕を助けてマルグリット・ショパンの墓を揆き死人の心臓に鉄棒を突き刺すことによって吸血鬼を退治する。そこで吸血鬼の魔力は失われ、レオーヌに祟っていた隠霊は消えてしまう。医者と義足の男はその罪によって殺される。アランは彼が医者の手から救い出したジゼールと共に夜の恐怖の去った輝かしい夏の朝を迎える。夢はここで終わっている。
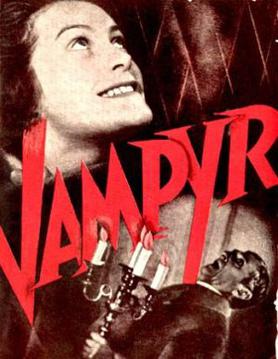
キネマ旬報のあらすじは全編を夢の中の出来事としていますが、映画は物語上は次に主人公アランが怪しい老婆に呼ばれて影と離脱する男を目撃し、その男を追ううちに霧の中を迷い、一軒の館に辿り着きます。そこは先の老紳士の屋敷で、娘二人と使用人夫婦が暮らしていました。当主はアランが目撃した影に射殺され、姉の方は病に伏せっています。封筒を使用人が開けると吸血鬼に関する本で、使用人は食い入るように読み始め、それが字幕で示され、一家を襲った吸血鬼の呪いの悲劇の原因が判明します。姉を往診する医師の様子は明らかに怪しく、皆の血を採血して彼女に与えます。「精血を完全に吸い取ると、吸血鬼はあらゆる手段で犠牲者を自殺に追いやる」と本の一節が映り、姉は毒をあおろうとし、アランがそれを阻止します。翌朝、濃霧の中を散歩するアランがベンチで休むと、魂が離脱し、ある家の中に棺に横たわる自分をみる。ガラス越しに覗く隣室にはベッドに縛りつけられた妹の姿があり、幻の彼はそれを助けようとしますが動けません。「塵から生まれ塵に帰る」と内側に書かれた棺の蓋が閉まると、ショットは棺桶の窓から見たアランの死体の視点に切り替わり、教会に運ばれるまでの風景が映ります。棺を担ぐ列がベンチに眠るアランを過ぎるとそこで消え、アランの魂は舞い戻ります。一方、使用人は警官を呼んで墓地へ行き、過去に吸血鬼に囚われ昇天していないという老婆の亡骸の心臓に杭を打ちます。それとともに長女レオーヌの呪いは解け、アランは医師を追い、幻視した家に追いつめ、その義足の助手は階段を転げ落ちて死にます。医師は粉挽き小屋に逃げ込むが、水車や歯車が回り出し、老婆の手下だった医師は白い粉に埋もれて絶命します。アランは次女ジゼールを助け出すと、小舟に乗せて漕ぎ出します。本作は一応原作を19世紀のアイルランド作家シェリダン・レ・ファニュ(1814-1873)の短編集『In a Glass Darkly』1872から短編「吸血鬼カーミラ」を中心にドライヤーが脚本を書き、念頭にあったのは1927年からベラ・ルゴーシ主演でニューヨークでヒットしていた舞台劇『吸血鬼ドラキュラ』で、『裁かるゝジャンヌ』'28のあと'29年には脚本を仕上げ、'30年には大半の撮影を終えていたそうですからトッド・ブラウニングの『真夜中のロンドン』'28よりは後ですがブラウニングの『吸血鬼ドラキュラ』'31より早かったわけです。本作はまだサイレントとサウンド・トーキー技法の混在があり、音楽や効果音はありますが台詞のないシークエンスもあり、また書物の頁を映してタイトル字幕代わりにする手法も頻繁に見られます。これについてはドライヤーは本作では「本も登場人物の一つ」と見なしていたということによるそうです。サイレント作品にするかサウンド・トーキー作品にするかは'30年中の完成・公開ならヨーロッパではまだサイレント作品でも良かったからなのですが、結果的にヨーロッパでもトーキー化の完了した'32年公開になったため、サウンド映画ならではの効果とサイレント作品の手法が混在したのも本作の異様な雰囲気にはプラスに働いています。『裁かるゝジャンヌ』は顔のアップと背後の壁、という具合にB/W映像のほとんどが白っぽい映画でしたが、『ミカエル』'25と同作で撮影を担当したカメラマン、ルドルフ・マテは本作ではレンズの前にガーゼのフィルターをかける手法を考案し、幽体離脱の二重撮影の多用とともにガーゼのフィルター越しの白っぽい映像が本作を『裁かるゝジャンヌ』以上に白っぽい映像の映画にしており、老婆の手下の医師も脚本段階では沼地に沈む最後でしたが水車小屋の粉挽き車の小麦粉に埋もれて絶命する具合に変えたのは、偶然ロケ地で水車小屋を見つけたからだそうで(もっとも実際に使ったのは石灰だそうですが)、何とこの映画、俳優も城主とヒロイン(次女ジゼール役)だけ職業俳優で他の出演者は全員素人、壮絶な末期を遂げる医師も地下鉄駅でドライヤーがスカウトしてきたばかりか、小道具や多少の大道具はあったでしょうが驚きの全編ロケーション撮影だそうです。この映画の、とても現実のものとは思えないような映像が一切セットではないとはそれ自体も驚異的で、ドイツ映画の『カリガリ博士』'19や『ニーベルンゲン』'24、ハリウッド映画の『真夏の夜の夢』'35や『オズの魔法使』'39の人工的な異世界とは違った異様さがあり、ムルナウの『吸血鬼ノスフェラトゥ』'22やブラウニングの『吸血鬼ドラキュラ』のような吸血鬼映画を期待するとおよそホラー映画の要素も稀薄なのに、感覚的にまとまりのない悪夢そのものが迫ってくる気味悪さがあります。故・伊丹十三氏が監督長編映画第1作『お葬式』'84のスタッフ・キャストに本作を参考試写して観せたのはよく知られた話で、同作は古今東西の映画を参考にしたショットだらけですが、『吸血鬼』からは死体の視点からのショットをまるまる使っていました。『お葬式』をご覧の方は本作でそのシークエンスになるとびっくりなさると思います。映画でパクっていいこととまずいことがあるのがわかります。
●8月29日(水)
『怒りの日』Vredens dag (Carl Theodor Dreyer-Filmproduktion'43.Nov.13)*93min, B/W; 1947年ヴェネチア国際映画祭審査員特別賞受賞 : 日本公開2003/10/11 : https://youtu.be/6_SATxIRMts (Trailer)
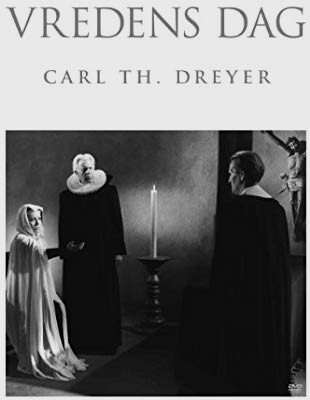
[ あらすじ ](同上) ノルウェーの小さな村で暮らす牧師アブサロン(トルキル・ロース)の後妻に迎えられたアンヌ(リスベット・モヴィーン)は、アブサロンの息子・マーティン(プレーベン・レアドフ・リュエ)と惹かれ合う。しかし、彼女には魔女狩りの手が迫っており……。

老農婦マーテは魔女裁判の席上で、裁判官の司祭に「私を裁くならあんたも裁かれることになるよ!」と預言します。またマーテとアンヌのやり取りを聞いた観客はアブサロン牧師がかつてアンヌの母を魔女裁判で弁護したのを知っているので立会人になっている牧師がかつての裁判をむしかえされたくないためかえって傍観する一方なのを観ることになります。こうしたことすべてがアンヌを幻滅させ、マーティンとの逃避的な恋につながって行きます。マーテの処刑の後でますます露骨にマーティンと出かけるようになり、明るく若々しくなったアンヌを夫のアブサロンはマーティンの若さのおかげだ、と母の前で喜び、アブサロンの母はますますアンヌを憎みます。やがて司祭が病気になって危篤の報に牧師はおもむき、その晩は嵐になります。司祭は魔女マーテの言うとおりになった、と牧師に告げて逝去します。牧師館では二人きりになりたいアンヌとマーティンが起きて待っていますが、老母も居間から引きません。アンヌは先に寝ます、と引き上げ、残った孫のマーティンになぜアンヌを嫌うのか問われ、牧師の母ははっきりとあの女は虫が好かない、家に入れたのが間違いだった、と吐き捨てます。やがてマーティンと老母が寝室に引き上げてからアンヌは居間に戻ってきて、司祭の臨終を看取って帰ってきた夫アブサロンを迎えます。死と罪のことばかり考えて帰ってきた、という夫に、アンヌは私もずっとあなたの死のことばかり考えてきた、結婚以来ずっとあなたの死だけを考えてきた、と言い放ちます。ショックを受けた牧師は昏倒し、マーティンと老母が駆けつけてくると事切れています。そして、アブサロン牧師の葬儀の場で、アンヌは牧師の老母メレーテに悪魔の力によって夫を殺し、マーティンを誘惑した、と魔女として告発されます。ここまでで映画の9割強の展開をたどってきましたが、デンマーク近世版嫁姑話の本作の結末はおそらく原作準拠でもあるだろうし、この映画でもこれ以外には動かないだろうというほど力強いものです。17世紀初頭のデンマーク(キネマ旬報あらすじのノルウェーは間違い)という近世のプロテスタント国でもこうした中世のような魔女裁判が行われていたのを生々しく観ることができるのもこの映画の興味になっていますし、それが社会構造はほぼ近代的な市民社会になっている生活描写とないまって、歴史映画を観ている感じはまったくありません。それこそちょっと田舎に行けば今でもこうした魔女狩りが行われていそうな雰囲気といっていいくらい現代劇と同じ感覚で、それがかえって恐ろしい効果を上げています。本作のヒロインのアンヌはとりたてて賢くもなければ美人でもなく、おそらくこのようなシチュエーションでもなければ通常映画のヒロインには描かれないような人間です。「牧師の若い後妻」という属性以外生活に何もないような空虚さを絵に描いたような若い女性として描かれていて、いわばボヴァリー夫人以前のボヴァリー夫人ですが、そういった人間が陥る悲劇をきっちり定着させるには不寛容で嫉妬に満ちた狭い人間関係と、それがどのように噴出するかを明確な時代相の中に置いてみなければならない。この映画はまったく面白さを感じない人も多いでしょうし、結末には反感すら感じる人もいるでしょうが、個人の嗜好を超えた傑作というのも映画の中にはあり、『怒りの日』以降のドライヤー作品3作はいずれもそれに該当します。また、ヒロインの受難劇を追及してきた映画監督の第一人者と言えば溝口健二ですし、溝口は『怒りの日』以降のドライヤー作品は観る機会がなかったと思いますが、テーマについても演出技巧の面でも、本作と『ゲアトルーズ』は溝口に感想を訊きたかったと思えてくるような作品です。