アンドレ・ジッド(17)その創作の特徴3
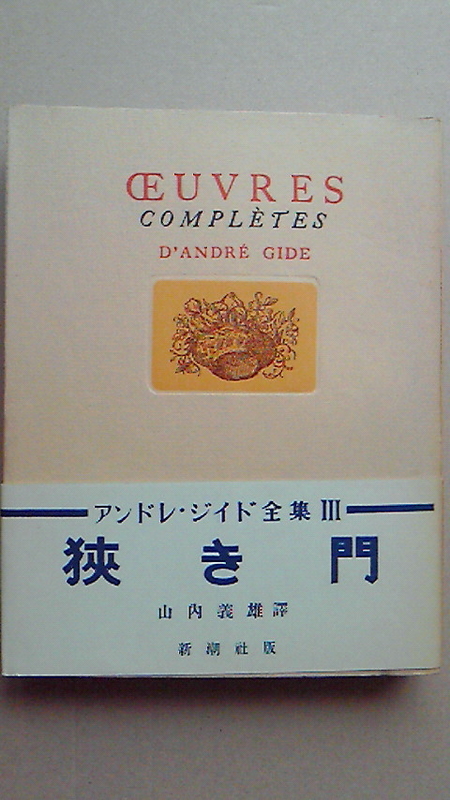
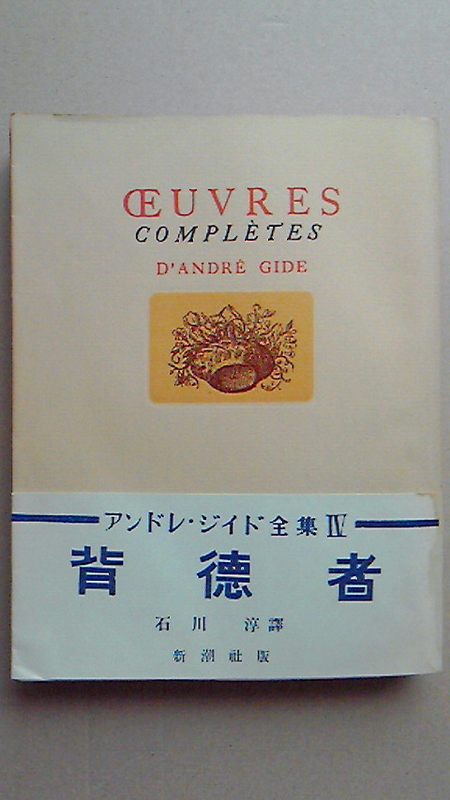
まず処女作『アンドレ・ワルテルの手記・詩』1891~1892年に始まる自伝的作品の系列があり、『ナルシス論』や『ユリアンの旅』、『愛の試み』1891~1893などのエッセイ風な詩的散文もその副産物であり、『地の糧』1897、『新しき糧』1935は小説の枠を踏み出した長編エッセイで、ジッドそのものが話者になっているのです。
順序からいうと『パリュウド』1895から始まる風刺作品(ソチ)の系列があり、これは作品そのものが小説形式に対する批評を意図しており、現在の文学概念ではメタフィクションと呼ばれるものです。『鎖を離れたプロメテ』1899、『法王庁の抜穴』1914と数少ないものの、ジッド唯一の長編小説(ロマン)『贋金つかい』1926は詩的散文とソチの混合によって生まれたといえるでしょう。
ジッドがロマンという時、それはレシ(中短編小説)と詩的散文・ソチすべての混合体を指しており、単に長さならば『背徳者』1902や『狭き門』1909、『イザベル』1911、『田園交響楽』1919、また後に三部作として纏められた『女の学校』1929・『ロベール』1930・『未完の告白』1936も長編小説として通用します。また『法王庁の抜穴』は長さでは『贋金つかい』に次ぐものです。ではなぜジッドのロマンはソチの延長であり、レシの発展ではなかったかが問題になります。
レシでも短編になるとジッドは極端に寓意的で、『エル・ハヂ』1897はカナンを目指す民族の偽預言者の悲劇、『蕩児の帰宅』1907は聖書の再話、『汝も亦…』1922は信仰の困難を語る手記、『テーゼ』1946はギリシャ神話が題材です。『汝も亦…』は男色論『コリドン』1911や実名自伝『一粒の麦もし死なずば』1920と共に詩的散文とされた方がしっくりきますが、『地の糧』がありながら『コリドン』や『麦』は創作からは外されているのです。