アンドレ・ジッド(20)その創作の特徴6
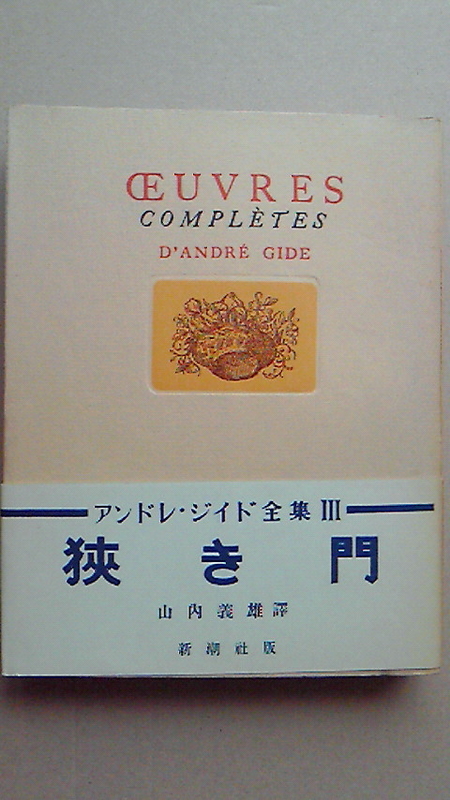
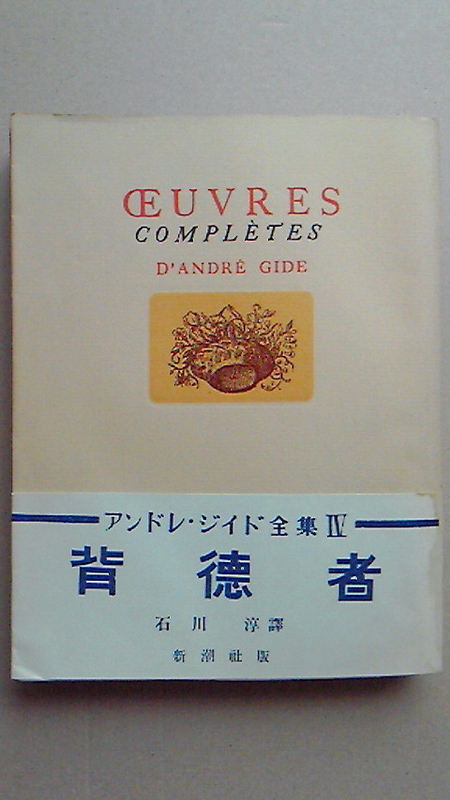
まず『背徳者』では自我拡張主義者の夫に振り回されて従順な妻は病死します。『狭き門』では主人公は従姉を熱愛しますが、従姉は献身と世俗の愛に迷い抜いて病死するまで主人公を拒絶します。『ワルテル』では従姉への求愛を親族から禁止された主人公が狂死して終りますが、『地の糧』以後のジッドは逆にヒロインを死なせる作家になるわけです。以上前回のまとめで、『狭き門』→『ノルウェイの森』、というニュアンスもそこにあります。
あり得たかもしれないジッド夫妻自身の運命を想像した点で、『ワルテル』『背徳者』『狭き門』は同一の背景から成り立った自伝的作品です。また『背徳者』は、暗示的な筆致ながら現代まで続くゲイ文学の最初の作品でした。単に主人公または登場人物がゲイの作品ならば古代ローマから中世、近世まで綿々と指摘できますが、ジェンダーの揺らぎがもたらす社会的不適合の問題を提出したパイオニアがジッドならば、その最大の業績は恋愛とキリスト教信仰の相克、ヒューマニズム、社会正義、19世紀文学と20世紀文学の橋渡しなどのジッドの一般的イメージよりもむしろジャン・ジュネやミシェル・フーコーの先駆者といえるラジカリズムにあるでしょう。たとえばジッドより36歳若いサルトルでさえ同性愛者を人格障害としか描いていないのです。
日本でジッドが宗教的で性的に潔癖な、思想性の高い禁欲的で甘美な恋愛小説作家、という支離滅裂な読まれ方をしてきたのもあながち的外れではなく、恋愛小説と最後につければ何でも流せる便器の蓋のようなものです。ヒロインは死に、主人公は生きるというのも恋愛小説の定石で、ジッドがしのびこませたゲイ文学の毒は青年読者には読み取れません。では、ジッドの試みは成功だったのか、失敗だったのかもにわかには断定できません。ほとほと食えない作家なのです。