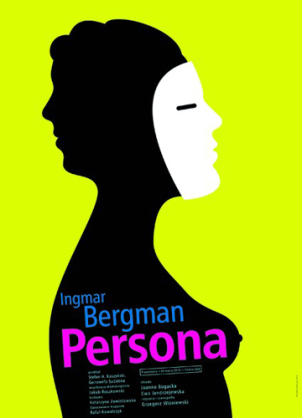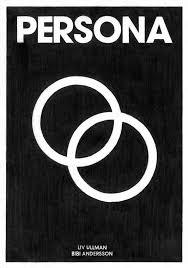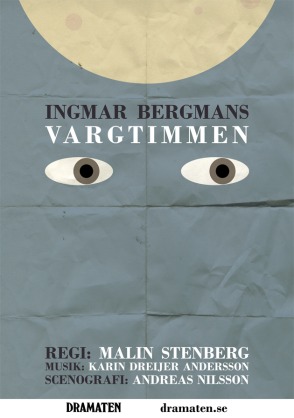1960年代半ばから映画のカラー化が標準になったのはカラーフィルムの低廉化も大きな要因ですが、より大きくは家庭用テレビのカラー化と普及促進によります。つまり新作映画もテレビ放映による2次収入を見越して予算が組まれ製作されるようになり、最初からテレビ局がスポンサーに参加して製作されるのも'70年代には珍しくなくなりました。テレビ放映された場合B/W映像は色彩溢れる家庭内にはなじまないものであり、深夜放映のように視覚が彩度の感覚を落としている時間帯の放映ならばまだしも十分に覚醒した状態では視覚的に刺激が弱すぎるか強すぎて感じられます。そのように新作映画のカラー化が急激に求められたのも1960年代の出来事でした(ただし
ベルイマン初のテレビ・ムーヴィー『夜の儀式』'69はまだB/W作品でしたが)。
ベルイマンの場合最初にカラー作品として考えられたのは1962年の『鏡の中にある如く』だったそうですが、主演のハリエット・アンデションが
精神疾患を病むキャ
ラクターとしてはカラー映像では健康的に映りすぎると判断され、続く『冬の光』『沈黙』の三部作ともどもB/W作品で統一されました。同時期には
アラン・レネが『ミュリエル』'62で、アントニオーニが『赤い砂漠』'64で、
フェリーニが『
魂のジュリエッタ』'65で初の長編劇映画を手がけており、
ベルイマンのカラー長編劇映画第1作も足並みを揃えることになりました。またこの時期
ベルイマン作品は製作ペースが落ち、'40年代、'50年代、'70年代と較べると'60年代は試行錯誤とともに作品本数も減少したのが'60年代後半の三部作を含む作品群からもうかがえます。身も蓋もない言い方ですが、率直に言って今回と次回にご紹介する作品は後になるほど箸にも棒にもかからなくなるのです。
●7月28日(金)
『この女たちのすべてを語らないために』For att inte tala om alla dessa kvinnor (
スウェーデン/スヴェンスク・フィルム'64)*80min, Eastmamcolor, Standard ; 日本未公開(映像ソフト発売)
・長編劇映画第26作にして初のカラー作品。脚本は
ベルイマンの原案を俳優エールランド・ユーセフソン(本作には出演せず)が執筆、スタッフは常連の撮影スヴェン・ニイクヴィスト、音楽エーリック・ノードグレーン、美術P・A・ルンドグレーンが勤める。意図してサイレント喜劇風にセピア色の背景色のタイトル字幕が多用され、冒頭から「この物語と似た実話があってもそれは偶然である」と断り書きが出る。世界的チェロ奏者フェーリックスの葬儀に音楽批評家コーネーリウス(ヤール・クッレ、『夏の夜は三たび微笑む』のキザな伯爵役)が現れ葬儀は献花式に移るが、未亡人姿の女性が半ダースあまり列席しているのが映る。タイトル「葬儀4日前」、フェーリックスの伝記執筆の申し入れにフェーリックス邸にコーネーリウスが乗り込む。フェーリックスは愛弟子(モーナ・マルム)とレッスン中で待たされている間にコーネーリウスはマネージャーの執事イルケル(アラン・エードヴァル)からフェーリックス夫人(エーヴァ・ダールベック)を紹介され、フェーリックスの公式愛人(ビビ・アンディション)に誘惑され、「葬儀3日前」「葬儀2日前」と進むうちに部屋係の召使い(ハリエット・アンディション)、生徒トラヴィアータ(イェールド・フリード)、伴奏ピアニストのベアトリス(バルブロ・ヨート・アヴ・オルネース)、フェーリックスのパトロネア(カーリン・カヴリ)らフェーリックスをめぐる愛人たちの抗争にタンゴを踊りまくり、ヴェランダから転落し、プールに叩きこまれ、階段から転げ落ち、火薬部屋で花火の爆発に巻き込まれる。コーネーリウスの目的は伝記執筆とともにコーネーリウスの自作曲の演奏をフェーリックスに乞うためと相談された執事はコーネーリウスを女装させ、フェーリックス邸からのラジオ中継が急遽決定する。世界4か国のアナウンサーが司会に乗り込んできてピアノの前奏が始まるやいなや
チェリストは発作を起こして倒れ、急死が確認される。葬儀の席でコーネーリウスはフェーリックスの伝記を読み始めるが夫人たちが次々に抗議して原稿は宙に舞う。その時学生風の青年が現れフェーリックスの得意曲をソロ演奏し始める。フェーリックス夫人と執事は退席し他の女性は聴き惚れる。コーネーリウスは青年に歩み寄り尊大に演奏の続きを命令すると、やにわにノートにメモを書き始める。技法はコマ送り、カラー映像とB/W映像の交錯、タイトル字幕の多用など(公式愛人からの誘惑には「検閲を配慮してこの場面はタンゴの映像で代用する」、花火のシークエンスは「この花火は何かの象徴かもしれない」と解説タイトルが入る)
スラップスティック喜劇の手法で遊んでいる。
ルイ・マルの『
地下鉄のザジ』'60、
ゴダールの『女は女である』'61と似た趣向だがさすがに『夏の夜は三たび微笑む』の監督だけあって堂に入っている。『沈黙』三部作の主要人物3~4人の
ミニマリズム映画の実験直後でやりたい放題やっていて単純に面白おかしい喜劇で開き直って痛快な快作になったが同時代評は悪評の嵐だったのも深刻三部作直後にこれでは冗談がきつすぎたのだろう。
ベルイマンの作品系列は『夏の夜は~』『魔術師』そして本作と深刻映画の合間に痛快喜劇を挟んでおり、本作の実験色の強さは次作『仮面/ペルソナ』からの'60年代後半作品に生かされるのだが、本作を最新作として観ると次に何が来るか予想もつかない迷走作品という悪評も仕方ない。チェロの巨匠フェーリックスの声や顔を完全に隠し通して描いているのも面白おかしい。
ベルイマンの作品系列で本作が『沈黙』三部作と『仮面/ペルソナ』の間にあるのも絶妙に思える。広義の喜劇(ハッピーエンドの結末)はともかく、純粋な喜劇としては本作が
ベルイマン最後の喜劇作品になるのだった。
●7月29日(土)
『仮面/ペルソナ』Persona (
スウェーデン/スヴェンスク・フィルム'66)*80min, B/W, Standard ; 日本公開昭和42年(1967年)10月
・本作からは第42作目の遺作『
サラバンド』2003まで(
モーツァルトの『
魔笛』を除き)原案・脚本ともに
ベルイマン単独執筆になる。撮影のスヴェン・ニイクヴィストは第41作『リハーサルの後で』
1984まで不動のコンビを組むが、音楽は本作から現代音楽色の強いラーシュ・ユーハン・ヴェルレと『沈黙』三部作以来のバッハ曲の使用に変わる。過去の
ベルイマン作品、またドキュメンタリー『フォール島の記録』'70で使われる映像を含む様々な映像コラージュに続き看護婦アルマ(ビビ・アンディション)が女医(マルガレータ・クローク)からこれからアルマが療養を担当する女優エリーサベット・ヴォーグレル(リヴ・ウルマン)の病状を説明する。ヴェテラン女優のエリーサベットは
ギリシャ悲劇上演中突然台詞を忘れ、
失語症と無感動状態が続いている。病室でエリーサベットは
ヴェトナム戦争の報道番組に見入り、画面には抗議行動の
焼身自殺僧の映像が映る。アルマは無言のエリーサベットを看護しながら自己紹介を続ける。また夫ヴォーグレル氏からの手紙を音読して手渡すが、エリーサベットは同封の少年の写真を破り捨てる。25歳のアルマは年上のエリーサベットと急速に親しくなり、過去の不倫経験と乱交体験、堕胎経験を打ち明けるが、翌日書きかけのエリーサベットの女医への手紙を見つける。そこには前日打ち明けたアルマの性体験が詳細に書かれていた。その日偶然グラスを床に落として割ったアルマはわざと破片をそのままにしておき、エリーサベットが踏んで声を上げるのを無表情に聞く。数日後、アルマはエリーサベットが無言でアルマを観察していると責める。エリーサベットはアルマを平手打ちする。アルマは湯を沸かしていた鍋に手をかける。やめて、と初めて言葉を発したエリーサベットをアルマは罵倒し、エリーサベットは無言で海岸に出ていく。アルマは許しを乞うがエリーサベットは応えず、アルマは海岸で泣く。部屋に戻ったエリーサベットはさまざまな子供の写真帳を眺める。エリーサベットを呼ぶ男の声がする。庭にいたアルマに男がエリーサベット、と呼びかけながら近づく。アルマは違います、と応えるがくり返す男のよびかけにはい、と応えて男に抱かれる。その後アルマは、エリーサベットが破った写真を隠し持っていたのを見つける。アルマはエリーサベットが
失語症に陥った経緯を解いて聞かせる。エリーサベットはかつて演劇関係者のパー
ティーで批評家に女優としても女性としても完璧だが母性には欠けると指摘されたことがあった。その後エリーサベットは息子を産んだが母親としての自信が得られないままだった。エリーサベットは顔を上げ、アルマは同じ話をくり返す。画面上で二人の顔が左右に合成され、アルマは私たちは同じじゃない、私とあなたとは違う、と告げる。エリーサベットはアルマの腕に噛みつき、アルマはエリーサベットを叩く。アルマはくり返しなさい、とエリーサベットに「無」と言いエリーサベットも「無」と言う。二人の女は寄り添って眠る。先に起きたエリーサベットがアルマを優しく撫で、アルマが起きるとエリーサベットは荷造りして去っていく。フィルムのリールが明滅して少年の影が映り、明かりが消える。冒頭で女医とアルマの対話シーンがある以外はほとんど映画はアルマとエリーサベットの二人、しかも台詞があるのはアルマだけ、という『沈黙』以上にミニマムを突き詰めた作劇。ただしアルマが二人分しゃべっているとも言えるので台詞自体は十分に多い。アルマは『魔術師』の道化師の不貞妻と同名、エリーサベットの姓ヴォーグレルは『魔術師』の一座の座長と同姓と
ベルイマンの過去作品に連想させる仕掛けがあり、また少年が鍵となっているのは『沈黙』を連想させてこの後の
ベルイマン作品でも同じ手口が使われる。カラー作品の後のB/W作品だからかB/W映像の効果が極端に強調されて、白衣と白い部屋着、肌の白さを強調したとことん白い映像が印象的。またアンデションとウルマンも適役だが心理学めいた謎解きや二人の女の関係の図式性は型通りで、徹底して二人の対立構図で押せばもっと面白くなったかもしれないと思わせる分企画倒れの観がある。好悪はともあれ女二人なら『沈黙』の姉妹の方が激しく対立していたと比較を誘われるのが弱い。説得力がないとまでは言わないが設定から期待されるほどの満足感は得られず、『沈黙』三部作の補足という程度の感じを受けるし三部作のどの作品と照らしても停滞して見える。水準は保ったが次作で一歩進まないと物足りない、と予感させる。そして
ベルイマン自身も次作からの三部作でこれまでにない混沌に走ることになる。
「ダニエル」Daniel (
スウェーデン/スヴェンスク・フィルム'67)*11min, B/W, Standard (短編) ; 日本公開昭和50年(1975年)9月
・8話からなるオムニバス映画『刺激』の第4話、
ベルイマン自身の撮影によるホーム・ムーヴィー。
ベルイマンの4人目の夫人でピアニストのケービ・ラレテイ(1922-2014、1969年離婚)との間息子ダーニエル・セバスチャン・
ベルイマン(1962-)の2歳の誕生日までの記録。愛らしい短編でホーム・ムーヴィー以上でも以下でもないが、こういうのもあるんだな、と一応書くと、案外『沈黙』や『仮面/ペルソナ』、次作『狼の時刻』の鍵となる少年のイメージは子息ダーニエルの誕生に由来しているのではないか、というヒントにもなっている。
●7月30日(日)
『狼の時刻』Vargtimmen (
スウェーデン/スヴェンスク・フィルム'68)*84min, B/W, Standard ; 日本未公開(テレビ放映昭和52年=1977年8月『狼の時間』)映像ソフト発売
・本作、『恥』'69、『情熱』'69はマックス・フォン・シードウとリヴ・ウルマン主演の孤島(フォール島)三部作と呼ばれるもの(『恥』『情熱』と違い本作のロケ地はまだフォール島ではないらしい)。'60年代の
ベルイマン作品は三部作で始まり三部作で締めくくられることになる。『狼の時刻』とは午前3時、
スウェーデンで言う丑三つ時を指す。冒頭「2年前、
バルト海の孤島で画家ユーハン・ボルイが突然失踪した。この映画はその妻アルマの回想と画家本人の日記に基づく」とタイトル。画家ユーハン(マックス・フォン・シードウ)は仕事が順調にいかず不眠気味だが毎日の戸外スケッチは欠かさない。ある日ユーハンの留守中に自称200歳、本当は76歳という老婆(ナイマ・ヴィーウストランド)が庭仕事中のアルマ(リヴ・ウルマン)にユーハンのスケッチ帳と日記帳の隠し場所を教える。ユーハンの日記には島に住むフォン・
メルケル伯爵(エールランド・ユーセフソン)が自分も妻(イェールド・フリード)もユーハンのファンでユーハン夫妻を夕食に招待すると申し入れられ、その数日後に
若い女に監視されていると話しかけられて危険が近づいていると告げられ、女に言われるままに服を脱がせたこと、島の管理人(ウルフ・ユーハンソン)につきまとわれ殴り倒したことが書かれていた。その時ユーハンが帰宅するが会話も上の空の様子で、ユーハンは金曜に伯爵の城に招かれたとアルマに告げる。城に招かれたのはユーハンの日記とスケッチ帳に描かれた人物ばかりで、アルマは伯爵夫人とユーハンの会話から
若い女性がヴェローニカ・ヴォーグレル(
イングリッド・テュリーン)という名と知る。余興に上演された
モーツァルト『
魔笛』の人形劇の後で芸術談義になり不機嫌になったユーハンは自分には芸術は単なる強迫観念だ、と場を白けさせ管理人に責められる。帰宅途中アルマはユーハンの日記を読んだと告白し、皆が自分たち夫婦を裂こうとしているようだけれど私はあなたから離れない、と言うがユーハンは答えない。ここで再び映画のタイトル『狼の時刻』が出る。帰宅したユーハンは暗闇の中で海辺の岩場でスケッチ中に起こったことについて話す。スケッチ中にまとわりついてきた少年にユーハンは逆上し、殴り倒して岩で撲殺する。ユーハンは死体を海に捨てる。一度浮いてきた死体は再び沈む。ユーハンがそこまで告白した時、管理人がまた伯爵がパー
ティーを開きます、と招待しにきて、伯爵と自分はユーハンを守る方法を相談したのです、と言ってピストルを置いて去る。その後、アルマがユーハンの日記帳を持ってきてヴェローニカとユーハンの関係について読み上げる。アルマとの結婚前ユーハンは既婚者のヴェローニカと不倫関係があり、その結果ユーハンは精神病院に数年間入院していた。夜明けの光が差し始める。ユーハンはピストルを取り上げて逃げるアルマを撃とうとする。アルマを追うユーハンはいつの間にか伯爵の城の中にいる。中年のメイドに誘われて広間に出ると僧服の伯爵がヴェローニカは長い間私の愛人だったからユーハンのことは何でも知っていると語り、ユーハンを招いて奥へ進むと壁を登る。ユーハンが進むと女性たちが
クラヴサンの演奏会を聴きいり、伯爵夫人がユーハンのアルマ狙撃を嘲る。老婆が顔の皮膚を剥ぎ、目玉のない別の顔が現われる。ワイングラスの中の目玉を見てユーハンは別の部屋に進み、女装させられたユーハンは鳩の群に顔を突つかれる。先にロウソクの光が見え、棺にかけられた布を剥ぐと全裸のヴェローニカが横たわっている。ユーハンはヴェローニカを愛撫し、ヴェローニカは突然笑い出して身を起こしユーハンにキスする。嘲る人々に取り巻かれ、少年の死体が浮かぶと、ユーハンは再び自宅にいる。アルマが顔を上げるとユーハンがいない。林の中を探すアルマ。腰を下ろすとユーハンの姿に気づく。ユーハンは男たちに襲われる。アルマは林の中を走る。自宅でカメラに向かって語るアルマ「夫婦は似てくるというが、似すぎてしまって夫を救う方法がわからなくなったのか、それとも私が嫉妬深かったのか」アルマは横を向き、「カット!」の声が響いて映画は終わる。本作は日本では'80年代までくり返しテレビ放映され、内容ともども吹き替えと短縮編集でわかりやすくなって
ベルイマンのオカルト映画として本作ならではのファンがついたが、吹き替えテレビ放映版でなく完全版で観ると上記あらすじの通り滅茶苦茶を通り越してホラー映画のラッシュフィルムそのものになっている。特に後半は時空間の連続性もなくなって何だかわからないうちに主人公は失踪し、その妻の懐述も全然解説になっていない。『沈黙』三部作になくて『この女たち~』『仮面/ペルソナ』で出てきたのはメタ映画としての要素だが、本作もそれを踏襲してフィクションの中にフィクションが展開される仕組みなので一元的に解釈できなくてもいいように作ったとも言えるが、それにしては次々現れるエピソードがわかりやすい悪夢的な象徴性があってこれでは図式に収まるものをわざわざ混乱して提示してみせただけではないか、という不審を抱かせる(実際音声まで調整された日本語吹き替え短縮テレビ放映版は明解なオカルト・ホラー映画になっていた)。孤島三部作のうちカラー作品は最後の『情熱』だけだがB/W作品の本作と『恥』はB/W作品として撮られた不満を感じさせる。得意のキャ
ラクターを演じるレギュラー俳優陣は本作も好演で特に謎の婆さん役のヴィーウストランドと人妻役のフリードがいいが主演のシードウとウルマンの二人は役柄を持て余し気味で、演出方針にブレがあり
ベルイマン自身が明確なキャ
ラクターをつかめなかったのではないか。次作『恥』、三部作最終作『情熱』とシードウ演じる主人公のキャ
ラクターがどんどん徹底したエゴイストになり、その分物語とプロットも単
純化していくのも本作の迷走あってではないか。本作は日本盤DVDに吹き替え短縮テレビ放映版(実質70分弱!)の特典映像があれば良かった。
ベルイマンの'60年代は「沈黙」三部作で始まり「孤島」三部作で終わるが、ともに全力の力作で
ベルイマンの典型的作風を感じさせるとはいえ作品の成功ではあまりに対照的な出来ばえを示したように思える。
*[ 原題の表記について ]
スウェーデン語の母音のうちaには通常のaの他に
auに発音の近いaとaeに近いaの3種類、oには通常のoの他にoeに発音の近い2種類があり、それぞれアクセント記号で表記されます。それらのアクセント記号は
機種依存文字でブログの文字規格では再現できず、
auやoeなどに置き換えると綴字が変わり検索に不便なので、不正確な表記ですがアクセント記号は割愛しました。ご了承ください。