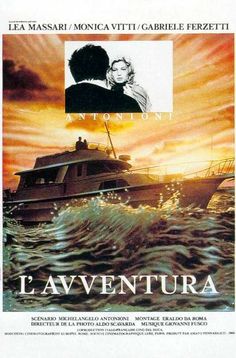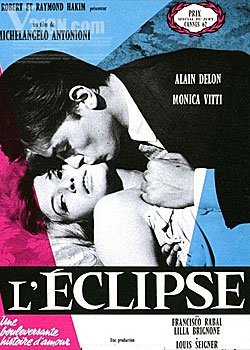アントニオーニの長編第6作『情事』は前作『さすらい』'57から3年ぶり、『女ともだち』'55や『さすらい』同様(ただしさらに深刻に)製作途中で予算不足のため撮影が中断し、新たに出資者を得て再開するも一時はスタッフとキャストのほとんどがアントニオーニへの不信感を募らせて完成すら危ぶまれるという逆境を越えて完成されました。同作は1960年の
カンヌ国際映画祭に出品され、盟友
フェリーニの新作の大作『
甘い生活』が圧倒的な好評でグランプリに輝く一方プレミア試写ではブーイングの嵐を受け、波乱含みの反響ながら審査員賞と映画テレビ作家協会賞を受賞し、審査員賞には「新しい映画言語の創造により」と但し書きがつきました。『情事』は一般公開されるや『さすらい』を上回る衝撃的でスキャンダラスな話題作として国際的にアントニオーニ初の大ヒット作となり、アントニオーニは一躍同世代の
ベルイマンや
フェリーニを抜いてフランスの
アラン・レネや
ジャン=リュック・ゴダールと並ぶ最尖端の
映画作家と目されるようになります。『さすらい』がアントニオーニ自身の離婚経験(突然家出した夫人から一方的に離婚を求められたそうです)から着想された映画だったように『さすらい』から始まる『情事(原題=冒険)』『夜』『太陽はひとりぼっち(原題=
日蝕)』の4作、または『情事』からの3作は四部作ないし三部作と考えられており(さらに次作『赤い砂漠』'64までを含める意見もあります)、『情事』から『赤い砂漠』までの
モニカ・ヴィッティ主演(『夜』のみ準主演)4作はアントニオーニの絶頂期を示した作品群でした。アントニオーニと同時代の
アメリカの前衛小説家
ジョン・ホークス(1949年デビュー作刊行)は「小説の本当の敵はプロット、登場人物、背景、テーマだという信念のもとに私は小説を書き始めた。こうした従来の伝統的小説観を捨てた時、重要になってくるのは全体的なヴィジョンや構造なのだ」(1965年のインタビューより)と発言していますが、「小説」を「映画」に置き換えるとこれはまるでアントニオーニや、ニュアンスの違いはありますが
ゴダールの映画について語っているようにすら読めます。しかしアントニオーニは自作はすべて楽観的な内容であってハッピーエンドであると答えており、
フェリーニがそう答えるならわかりますが、アントニオーニの場合はわからないぞこのイタリアの狸親父、と思わずにはいられません。『さすらい』は監督自身にモチーフがありましたが『情事』からは原案・共同脚本を
トニーノ・グエッラと組むことになります。『情事』以降の急激な抽象化はグエッラの持ち込んだ要素とも取れますが、他の映画監督の作品では過剰な自己言及性に現れてしまうことが多いグエッラの脚本作品のマイナス面はアントニオーニ作品には見当たりません(後のグエッラ脚本作品は
フェリーニ『81/2』もどきの「映画作りに悩む映画監督」の映画ばかりになり、また実際グエッラは
フェリーニの共作者にもなります)。またニューヨークのインディペント映画運動でリーダー的存在の
ジョナス・メカス(1922-、代表作『ウォールデン』'69、『
リトアニアへの旅の追憶』'72など)が
B級映画、ハリウッド古典とともにアントニオーニを絶対支持していたのは頼もしく、商業映画とインディペント映画の違いはありますがメカスのアントニオーニ評は
映画作家による
映画作家評では最も美しい文章です。
フェリーニの大衆的人気はイタリア人情劇としての抒情性でしたが、人種混交社会ニューヨーク(メカスも移民一世です)のアーティストにはアントニオーニのインターナショナルな感覚が映画の普遍性に見えたと思えます。おそらくそれはメカスが親しかったアンディ・ウォホールのようにポップ・アートの指向性と近いものでしたが、今日の観客にとってこれらのアントニオーニ作品ほど面白くない映画はないでしょう。
テオ・アンゲロプロス、
アンドレイ・タルコフスキーら(ともに
トニーノ・グエッラ脚本作品あり)の作風はアントニオーニの影響なしには考えられないにも関わらずアントニオーニ作品ほど評価の変動した映画は珍しく、その理由・原因は何処にあるかも考えさせられるものです。
●9月7日(木)
『情事』L'Avventura (イタリア=フランス/チーノ・デル・ドゥーカ,
ヨーロッパ映画, クール映画社'60)*143min, B/W; 日本公開昭和37年(1962年)1月/リヴァイヴァル公開昭和57年(1982年)6月
・前作から3年ぶりの長編第6作。
カンヌ国際映画祭審査員賞、映画テレビ作家協会賞、
新評論家賞、S.E.C.T.賞、ヌーヴェル・グラ
ティーク賞、ロンドン映画祭サザーランド賞、イタリア映画記者協会銀リボン撮影賞、外人記者会主演女優賞、ラ・カヴェーハ・ドロ主演女優賞、イル・サラチェーノ・ドロ主演/
助演女優賞、水晶の星主演女優賞受賞。脚本アントニオーニとトニーオ・グエッラ他1名、撮影アルド・スカヴァルダ(本作のみ)、音楽ジョヴァンニ・フスコ。「何といっても<情事>では姿を消したあの女が映画の主人公だった。ヒロインがいなくなっても映画は依然として続いている。ヒロインなしで映画はいかに持続できるか?ということが問題になるだろう。アントニオーニの沈黙はその内容に由来するものであり、その内容の一部である。アントニオーニの映画は通じるものを何も持たない、通じる必要性を感じない、人間としての本質が枯死した人びと、つまりわれわれを扱った映画である。アントニオーニの映画は、人間の魂の死を描いた映画である」(
ジョナス・メカス『メカスの映画日記』)。
ローマの上流階級の令嬢アンナ(
レア・マッサリ)は若い建築家の恋人サンドロ(ガブリエレ・フェルゼッティ)がいるが、サンドロはすでに芸術的意欲を失いアンナへの愛すらも不安定になっており、それを知るアンナの父(レンツォ・リッチ)はサンドロを快く思わず、アンナ自身もサンドロとの
破局を予感している。夏の終り、二人はジュリア(
ドミニク・ブランシャール)やレイモンド(レリオ・ル
タツィ)ら上流階級の友人たちに招かれて
シチリア島近くのエオリエ群島へヨット旅行に出かける。アンナはその旅行に親友クラウディア(
モニカ・ヴィッティ)を誘う。三人は気まずい零囲気の中でヨット旅行を続けたが、途中で
無人島に上陸した出発時、突然アンナの失踪に気づく。ヨットに同乗する友人たちとともにサンドロとクラウディアは懸命にアンナを探すが島にアンナの姿はない。翌日の捜索も無駄に終わり、事故の様子もない。アンナの父も警官隊を同行して来たが捜査は打ち切られる。ローマに戻ったサンドロとクラウディアはアンナの消息を求めて捜索を続ける。アンナの失踪は友人たちの話題にも上らなくなり、クラウディアとサンドロは不安の中でついに関係を持つ。アンナの行方の捜索はすでに二人の逢い引きの口実に過ぎなくなる。あるパーティの夜、友人たちは当然のように二人を
カップルとして迎える。その夜、酔ったサンドロは行きずりに娼婦を抱く。恋人の所在不明に不安の夜を明かしたクラウディアはサンドロが娼婦を連れ込んだ姿を見て立ち去る。クラウディアを追って出たサンドロは戸外のベンチに座り込んですすり泣く。サンドロを見つけたクラウディアは後ろから静かにサンドロの髪を撫で、肩に手を置く(スチール写真参照)。
この映画はいったい何だ、ヒロイン(アンナ)は結局どうなったのだ、こんな映画があっていいのかと
カンヌ国際映画祭プレミア上映では大ブーイングが起こり世界中の観客・批評家が驚いたわけだが、観直してみると実はアンナは失踪などしていないのがわかる。アンナの父や友人たちがサンドロと別れたいアンナの意を汲んでサンドロとクラウディアにはアンナの消息を告げず口裏を合わせているだけ、という事情が見えてくる。それが目くらましになっているのはあらすじには省いた細かいエピソードの数々で、小島に上陸するきっかけになった遠泳では本当かどうかわからないサメ騒ぎが起こるし、パー
ティーの前にクラウディアと街角で待ち合わせたサンドロは、建築現場でインク瓶を重石に置かれた図面に懐中時計の鎖を垂らして揺らし、偶然を装ってふざけ半分でインク瓶を倒して図面を汚し、若い
建築士に「わざとやったな!」と食ってかかられるのを何くわぬ顔でその場を離れるとちょうど隣の僧院から黒衣の僧侶たちがぞろぞろ出てくる。『さすらい』の散歩中の精神病院患者たちと出会って少女ロザーナが泣き出す場面の延長だが今回はサンドロ自身が挫折した
建築士だけに内面の頽廃はもっとひどく、これがラストシーンのサンドロのすすり泣きにつながるがクラウディアの慰めで立ち直るにはサンドロの腐敗は進みすぎており、おそらくサンドロとの関係を友人たちに感づかれた時点でクラウディアも友人たちからサンドロと同類の人間と割り切った距離を置かれてしまい、この二人は孤立してしまったのでおたがい以外頼る相手はなく、クラウディアの信頼にすら値しないと醜態を晒してしまった以上サンドロの居場所はない。メカスが主人公は不在のアンナだ、というのもついに姿を現さないことでアンナは映画の最後までサンドロとクラウディアにかけられた呪いになっているからだろう。アントニオーニはデビュー長編『愛と殺意』'50からひどい男(またはひどい目に遭う男)ばかりを描いてきたが『情事』『夜』『太陽はひとりぼっち』はそのピークで、作者自身はごく単純な着想から人間関係のヴァリエーションを描いているだけなのにメカスが指摘する「魂の死」の映画になってしまった。アントニオーニは恋人が去り、新しい
カップルが生まれてハッピーエンド(女が男を許す)で終わる映画、ととんでもない自作解説をしておりさすがだ。オリジナルは143分の本作は商業上・流通上の理由からアントニオーニ自身によって137分、120分と世界各国上映のたびに短縮されて行き(もともと短縮しやすい構成の映画でもあった)、1980年代には市販映像ソフトで103分まで短縮した版が流通したが短縮したからといってテンポが良くなる映画ではなく、かえって解りづらくなるだけだった。『さすらい』でアントニオーニはラストでびっくりさせる手口を覚えたが、以降アントニオーニ映画はラストのシークエンスで毎回とんでもないことをやる。このきっぱり左右に分割された『情事』の最終カットは世界中の映画監督が模倣することになる。
●9月8日(金)
『夜』La Notte (イタリア=フランス/ネビ・フィルム, シルヴァ・フィルム, ソフトディプ'61)*116min, B/W; 日本公開昭和37年(1962年)11月
・前作の翌年発表の長編第7作。
ベルリン国際映画祭金熊賞、国際評論家連盟賞、
ダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞監督賞、ナストロ・ダルジェント監督賞・撮影賞・
助演女優賞、
フィンランド・ユッシ賞海外女優賞受賞。脚本アントニオーニとトニーオ・グエッラ他1名、撮影ジャンニ・ディ・ヴェナンツォ、音楽ジョルジョ・ガスリーニ(本作のみ)。本作は
ジャンヌ・モロー(『
雨のしのび逢い』'60)、
マルチェロ・マストロヤンニ(『
甘い生活』'60)の2大スター競演のため
モニカ・ヴィッティは準主演、また
西ドイツ映画『橋』'59(
アカデミー賞外国語映画賞ノミネート、
ゴールデン・グローブ賞外国語映画賞受賞)の監督ベルンハルト・ヴィッキが俳優として出演。「<夜>は小説的映画の最も進んだ形である。アントニオーニは人物とその生活を語らずに"見せる"。……この映画でアントニオーニはどのような位置を占めるだろうか?彼は彼と同年のあらゆる偉大な芸術家と同じ位置を占める」(
ジョナス・メカス『メカスの映画日記』1962年2月18日)。
ある午後、作家のジョヴァンニ(
マルチェロ・マストロヤンニ)と妻リディア(
ジャンヌ・モロー)は病床の批評家トマーゾ(ベルンハルト・ヴィッキ)を見舞う。トマーゾは癌の末期にある。トマーゾは夫婦の結婚前からの親友で、以前トマーゾはリディアを愛したがリディアはすでにジョヴァンニの婚約者だった。彼女は作家夫人として何不自由のない毎日を送っていたが、ジョヴァンニとリディア夫婦を誰よりも親しく知るトマーゾの危篤は夫婦に得体の知れない不安をもたらす。トマーゾの老母の到着と入れ替わりに先にリディアは病室を辞去する。後から出たジョヴァンニは廊下で待ち構えたイン
フォマニアの精神病患者の女に抱きつかれる。夫婦の車はミラノの街を行き、ジョヴァンニの新刊小説のサイン会会場に着く。リディアはひとりミラノの街を歩きやがて郊外に出る。リディアは街のちんぴらグループの喧嘩を目撃し、ロケット花火の打ち上げに興じる青年たちを見る。サイン会を終えたその夜、二人は富豪の実業家ゲラルディーニ(ヴィンセンツォ・コルベーラ)のパー
ティーへ行く。ジョヴァンニはゲラルディーニから高給でパブリシティに雇用したいと申し出られる。会場でジョヴァンニはゲラルディーニの令嬢ヴァレン
ティーナ(
モニカ・ヴィッティ)に誘われて招待客たちと賭け
ボードゲームに興じる。一方リディアは病院へ電話しトマゾの死を知る。リディアは窓越しにポーチの隅で抱きあいキスする夫とヴァレン
ティーナを見る。突然のどしゃ降りの雨の中、プールサイドでの騒ぎから客のひとりにドライヴに誘われたリディアは口説かれるが無言で雨上がりの道を館に戻る。館では二人きりになったジョヴァンニがヴァレン
ティーナにまた会えるかと問うが、ヴァレン
ティーナは自分は誰からも知性を認められていないと言い、否定するジョヴァンニを一笑に伏して去って行く。朝が来る。夜を別々に過したジョヴァンニとリディアは邸の広大な庭の一隅に座る。リディアはぽつりとトマーゾの死をジョヴァンニに知らせる。そしてリディアは自分たちの間にはもう愛はない、と告げる。取り乱すジョヴァンニにリディアはバッグから取り出した、永遠の愛を誓う一通のラヴ・レターを読む。ジョヴァンニは衝撃を受け誰の手紙かと問い、あなたの手紙よ、とのリディアの返答に絶句する。ジョヴァンニは愛をとり戻そうとするようにリディアを激しく抱く。リディアは拒絶するが、それでもジョヴァンニはリディアを夜明けの草原に組み敷く。
前作『情事』の成功でアントニオーニは『夜』『太陽はひとりぼっち』と1年1作ペースで映画製作ができるようになる。しかも
ジャンヌ・モロー、
マルチェロ・マストロヤンニの2大スター競演はアントニオーニ映画では初めてで、
モニカ・ヴィッティは黒髪で準主演の金持ちの令嬢役。十分な予算とスケジュールの余裕と、スタッフとキャストも『情事』とは打って変わって成功作の自信があったか、前作の緊張感と対照的な余裕が映画全体をリラックスした雰囲気にしている。構成の分断化は『椿なき女』で始めて『女ともだち』で確立し、細かい枝葉のエピソードの累積による不穏なムードの創出も『さすらい』以降の手法だが、主演の二人が名優なのですんなり演技の一貫性が生まれてしまい『情事』までの出たとこまかせの不安感はない。モローがどしゃ降りの雨の中の車中で男に口説かれ逃れてくるシーンも外から窓越しに会話は一切聞こえないパントマイム演出でよく出来た恋愛映画風でありこのシーン自体の演出が悪いのではないが、アントニオーニらしくもない印象を受ける。モローとマストロヤンニが別々に体験するエピソードの数々も本作の場合は類型的で、『情事』のサンドロとクラウディアのように全然心が通じあわない恋人を描いた手腕が今回は主演俳優の上手さに相殺されてしまい、これほど世知に長けた
仮面夫婦なら別れ話にはなるまい、と思えてくる。いつものジョヴァンニ・フスコと替わって本作はイタリアの一流ジャズ・ピアニスト、ジョルジョ・ガスリーニが音楽担当、本作の大半を占めるパー
ティー場面で夜通し演奏するバンドとして出演。そつない演奏のテナー&ギター入り
クインテットだが典型的なヨーロッパの白人ジャズなのが本作の仕上がりと歩調を合わせているかのよう。
モニカ・ヴィッティが出てくると
ジャンヌ・モローやマストロヤンニと演技の質が全然違い、アントニオーニが『情事』からの4作でヴィッティの演技を求めた必然性がわかる。既成映画の「上手い」演技ではアントニオーニの狙いが浮かんでこない。メカスの評は本作では褒めすぎだが『情事』が偶然の産物ではなく監督自身の明確なヴィジョンによるものと証明してみせたのが本作の位置づけになる。本作は説得力を意図して成功しているからモローとマストロヤンニの競演を前面に、
モニカ・ヴィッティは一歩引いた配役なのも適切だが、懐疑的な批評家をも納得させる作品の次は予想がつく。そして次作はまたしても驚くようなものになった。
●9月9日(土)
『太陽はひとりぼっち』L'Eclisse (フランス=イタリア/パリ・フィルム, インテローバ・チネリツローマ'62)*124min, B/W; 日本公開昭和37年(1962年)12月
・早くも『夜』の翌年発表の長編第8作。
カンヌ国際映画祭審査員特別賞受賞。脚本アントニオーニとトニーオ・グエッラ他1名、撮影ジャンニ・ディ・ヴェナンツォ、音楽ジョヴァンニ・フスコ。原題直訳は「
日蝕」だが
アラン・ドロン主演のためドロン人気の高い日本では『
太陽がいっぱい』'60にあやかり『太陽はひとりぼっち』になった。悪くない邦題だが原題の簡潔なニュアンスの霧消では一長一短。「<夜>の後アントニオーニが何を作ろうとしていたのかは私にはわかっていた。だが<太陽はひとりぼっち>の後に彼が何を作ろうとしているのかはわからない。アントニオーニにひき返す道はない。そして人間には、出来ることと言えば自分の仕事を気にしながら(1)怒ること(よく考えたあげく)、(2)盲目的にどこへ通じるとも知れぬ道を進んでみること(
アナーキー、出たとこ勝負、偶然)、あるいは(3)孤独の中に潜むこと(禅、その他)、その心は救い難いが解決法はまだはっきりしていない」(
ジョナス・メカス『メカスの映画日記』1962年12月13日)。
女性歌手ミーナの歌うロックンロールの主題歌(年代は後だがエミー・ジャクソン、
青山ミチ、安西マリアらの「
涙の太陽」や
美空ひばり&
ジャッキー吉川とブルー・コメッツ「真赤な太陽」にそっくり)とともにクレジットタイトル、タイトルの最後はジョヴァンニ・フスコの不吉な7音の短いメイン・テーマ。ヴィットリア(
モニカ・ヴィッティ)は婚約者の作家
リッカルド(フランシスコ・ラバル)の家で一晩中話しあった翌朝、婚約を解消する。ヴィットリアは
リッカルドの著作のドイツ語翻訳者だが仕事からも手を引くと言い渡す。
リッカルドは出て行くヴィットリアを引き止め、別れの理由やその時期を問うが、ヴィットリアはわからない、と答える。押し問答のすえ
リッカルドを振り切って一人になったヴィットリアは母(リッラ・ブリグノン)を訪ねに
証券取引所に向かう。一刻ごとに様相を変える取引所の喧騒の中で株式仲買人ピエロ(
アラン・ドロン)を頼りに相場を張る素人投資家の母はヴィットリアの話を聞こうともしない。喧騒は大口投資家の急死の報で一旦1分間の黙祷に変わる。ヴィットリアは
リッカルドと昼食の約束があると嘘をついて
証券取引所から抜け出す。夜、隣人の女友達
アニタ(ロッサナ・ローリ)に
アニタの友人で
ケニア帰りのマルタ(ミレッラ・リカルディ)の家に誘われ、
ケニアの踊りを教わる最中にマルタのペットのプードルが逃げる。プードルを捕まえたマルタは夫が嫌がるからもう
ケニアには行けない、とつぶやく。帰宅したヴィットリアにアパートの外から
リッカルドが呼びかける。ヴィットリアは共通の友人
フランコに相談の電話をするが、
フランコは逆にヴィットリアを
口説き始める。翌日には
アニタの夫の
パイロットの操縦でローマ上空を小型飛行機で散策し、多少の気晴らしを得たヴィットリアがふたたび
証券取引所を訪ねると株の大暴落が始まっていた。ヴィットリアの母は投資資産を全部失い、大きな借金を背負ってヴィットリアを
リッカルドと別れなければ借金が頼めたのにと八つ当たりし、仲買人のピエロを責めるがピエロはこれまでの稼ぎもすべて自分の手腕ではないかと開き直る。巨額の全財産を一瞬で失ったピエロの顧客の肥った中年男(ルイ・セニエ)がカフェのテラスで
精神安定剤を飲み、茫然と紙に草花の絵を描いているのをヴィットリアは見つめる。先に出て行った母を心配してヴィットリアはピエロに頼み車で母の家に行くが母はまだ帰宅しておらず、ピエロはヴィットリアの子供時代の部屋でふざけてキスを迫るがヴィットリアはかわす。やがて落ち込んだ母が帰宅する。オフィスに戻ったピエロは顧客の来訪や電話のクレーム応対に追われ、呼んでいたコールガールの到着にオフィスを閉めて出るが、気が変わってコールガールを帰らせてヴィットリアのアパートに向かう。ヴィットリアはピエロの車の到着に気づき車から降りたピエロの様子を窓際でうかがうが、通りかかった酔っ払い(サイラス・エリアス)がヴィットリアを見かけてひやかし、気をとられたピエロは酔っ払いに新車を盗まれる。翌日車は酔っ払いの死体とともに湖から引き上げられるが、ピエロは車の修理代の心配ばかりをヴィットリアに愚痴る。この後ピエロがヴィットリアを訪ね、またヴィットリアがピエロに電話しと少しずつ二人は接近し、ピエロはピエロの生家にヴィットリアを招いて一夜を過ごす。恋人になった二人はピエロのアパートで戯れ、明日も明後日も明明後日もいつもの時間に会おうと約束し、抱擁しあって別れていく。ヴィットリアを見送ると、ピエロは外して置いた電話の受話器を戻す。ヴィットリアは公園を過ぎビルの街並を過ぎ、建築中の通りを過ぎ、歩み去っていく(1時間57分目)。映画のラスト7分間は主役の二人はもう現れない。夕暮れの街にバスで帰宅する人々、公園の水溜まりに浮かぶ塵の流れ、点灯する
団地の明かり、ビル街などさまざまな街の点景が台詞もナレーションもなく現実音だけを
サウンドに綴られ、点滅し点灯する街灯にハレーションする映像に再び映画冒頭のメイン・テーマが流れて終わる。
本作は『夜』の抑制が反動で爆発したかのような起伏の激しい作品になっている。『情事』の消極的な人物像から一転して
モニカ・ヴィッティも積極的に昔の男を振り新しい男に乗り換えるし、新しい男の
アラン・ドロンは欲望でぎらぎらした脂っぽい美青年で、
セミ・ドキュメンタリー的な第2作『敗北者たち』を除くとこうしたタイプの人物を描くのは今までのアントニオーニの映画にはなく、 はっきり俗人である点では『敗北者たち』の不良青年たちよりアンチ・ヒーロー性が強い。本作ほどくどいドロンのような現代的キャ
ラクターが映画の主役に描かれるのは後の
アメリカのビジネスマン映画まで待つことになると思うと意外な面でもアントニオーニの先取性があるのに感心する。しかしアントニオーニの場合は「こういうビジネスマンはこれまでの映画にはいないだろう」程度にしか考えていない直感的発想しかない。つまり「欲望ばかりの現代ビジネスマンの内面」など大して考えていない自然体の着眼点がさすがだ。
証券取引所での条件反射化した一挙手一投足から
プライヴェートでは当時の電話機だから女が来ている時は受話器を外しておく、などのせこい描写の積み重ねの非映画的リアリズムはアントニオーニの出自であるネオレアリズモの合目的性格のリアリズムを超えて現代美術のシミュレーション・アートの手法に近い。ヴィットリアは作家
リッカルドの翻訳者で恋人でいるうちに
リッカルドを別世界の人物のように感じ別れを決める。
ケニア帰りのマルタもまた別世界を見てきた女性とヴィットリアには見える。そしてピエロとヴィットリアには本来何の接点もない。アントニオーニによるとこれもまた新しい生き方を見つけた
若い女のハッピーな
恋物語で、結末ではもう二度と二人は逢わないがそれが二人にはハッピーエンドなのだということらしい。
アラン・ドロン演じるピエロも現代的な活力に溢れた肯定的人物として描いたそうで、同じ頃
ベルイマンは『情事』に向かっ腹を立てて『鏡の中にある如く』『冬の光』『沈黙』の深刻三部作を作っていた。
ベルイマン映画は悩める登場人物ばかりだが、アントニオーニといえば昔の恋人の夫殺しの企みから逃げる男の第1長編『愛と殺意』から間を置いて『さすらい』以降は当面の悩みから逃げる男の話ばかりなのに気づく。マストロヤンニが立派すぎるが『夜』もそうで、本作のドロンにはついに逃げたい悩み事すらなくなった。現代ビジネスマン映画ならともかく普通こういう人物は、特に無気力そのもののアントニオーニ映画の中では描きようがなかった。街の風景だけが次々と描かれる呆れたラストの7分間は『情事』のアンナ失踪からの2時間弱に匹敵するもので、ただし本作ではアントニオーニにより消されてしまったヴィットリアとピエロを探すのは登場人物ではなく観客の視線にしかなく、他ならないアントニオーニ自身に別れて以降のヴィットリアとピエロに関心はないのだから風景が待ちぼうけになっている様子しか描くものがない。124分の映画でラスト7分間もドラマと無関係なエピローグの風景映像が続く劇映画はこの時点では商業映画では皆無だったはずで、これ以降もアントニオーニ以外には即座に思いつかない。インディペンデントの実験映画なら別だが、他ならない
ジョナス・メカスがこの時点でのアントニオーニの極点と認めた重みは大きい。次作以降アントニオーニはカラー映画を手がけるとともにさらに作風を転換させていくことになる。