映画日記2018年11月10日~12日/サイレント時代のドイツ映画(4)

いろいろ見直してみた結果、当初ドイツ映画との隣接作品として取り上げるつもりだったスウェーデン映画の『霊魂の不滅』'21(シェストレム)や『魔女』'22(クリステンセン)、そして『彼女を巡る四人の男』の次作で初期フリッツ・ラングの総決算であり、表現主義映画の潮流にはっきり狙いを定めて国際的名声の確立に成功し、ラング作品としても初めて名作と言える会心の出来となった『死滅の谷』(ドイツ公開'21年10月、日本公開大正12年='23年3月)を当初は今回観直すリストに入れていたのですが、スウェーデン映画『霊魂の不滅』『魔女』はまた別の機会に、『死滅の谷』からは前述したように国際的監督となったハルボウ脚本によるラングの名作時代の始まりとなるので、もとより11月に毎日1本ずつ観るだけで'20年代ドイツ映画の全貌に迫るのは無理ですが、改めて観落とされがちな作品、これだけは外せない作品、里程標的作品をごくごく狭い範囲で絞りこみました。もっともラング作品はルビッチと並んで出自の類縁性や対抗意識はあっても表現主義映画とは本質的に異なる指向にあると思われるので(ラングは『カリガリ博士』の監督予定が流れて以来マイヤー脚本に食指は動かしませんでしたし、ラング改稿前の『カリガリ博士』のマイヤー脚本をアマチュア並みと批判しています)、エルンスト・ルビッチ同様フリッツ・ラングもドイツ映画の潮流とは平行してキャリアを築いていた監督と思われるのです。ここではラングの試行錯誤がドイツ映画の暗中模索と重なっていた『彼女を巡る四人の男』'21までを興味の対象とするゆえんです。『カリガリ博士』のヒロイン、リル・ダゴファーが真に魅力的なヒロインを演じたのは同作でも『蜘蛛 第1部 : 黄金の湖』『ハラキリ』でもなく名作『死滅の谷』なのを思うと残念ですが、前置きだけでも'21年のドイツ映画で最高の作品は『死滅の谷』だろうことを触れておきます。
●11月10日(土)
『彼女を巡る四人の男、または闘う心』Vier um die Frau : Kampfende Herzen (監=フリッツ・ラング、Decla-Bioscop'21.2.3)*84mins, B/W, Silent; 日本未公開

……と一回読んで理解できる人はいないのではないかと思えるくらい下手な紹介に嫌気が差すようなあらすじしかまとめられませんが、人物の正体と人間関係が見えてくるまでがこの映画も長いのです。『蜘蛛 第2部:ダイヤの船』は複数の悪党団が抗争したり手を組んだり仲間割れしたり慌ただしいので主人公ケイ・ホーグ側との区別をつけるのすらやっとでしたが本作は「四人の男」(夫、元恋人、その双子の弟、脅迫者)、『彷徨える影』よりさらに入り組んだ人間関係を理解する頃には映画は中盤までさしかかっている、という具合ですが、『蜘蛛』より数段手際はこなれていますし、また『彷徨える影』より欠損部分が少ないですし、ヒロインの遊び人の有閑マダム仲間なども出てくるので勘所はサスペンス風味のメロドラマなのが早いうちからわかるので観客を引っ張る力はありますし、後にラングはサスペンス/スリラー映画をどっさり撮りますからこういう陰謀ものは最初から好きだったのがわかって感心します。ただし本作はアメリカ映画でもフランスやイタリア映画でも色気や洒落っ気が出てきそうな、サスペンス風味であっても本来ならシチュエーション・コメディめいた設定と筋書きなのにそういうユーモアや情感はほとんどありません。謎めいた人間関係がもつれにもつれる様をひもといていくのが興味の中心になっている映画なので、他は当時のドイツ文化圏の富裕階級の最新ファッションが見所といったところです。これは『ドクトル・マブゼ』'22でより鮮明になりますが、個人よりも都市を描こうという指向が本作あたりから芽生えてきています。本来原作戯曲(原作『彼女を巡る三人の男』なのに本作が4人なのは、ヴェルナーの役割をヴェルナーと映画用の創作人物、双子の弟ウィリアムに分けたからになるそうです)もハルボウ脚本も意図しだだろう艶っぽい話の割にまるで艶っぽくないのはおそらくラングの演出意図でしょうし、人物の織りなす幾何学的構図を興味の焦点にしたのでしたら成功かもしれませんが、情感やユーモアを持ちこまなかったことで魅力が増したか半減したかは本質的にはメロドラマの本作の場合には判別が難しい気もしてきます。'87年ブリュッセルのF・W・ムルナウ財団による『ハラキリ』『彷徨える影』と本作のラング作品3作のレストア修復彩色版はレストアの威力で美しい画質と丁寧で適切な音楽が楽しめる最上のヴァージョンですが、ラングと双璧をなす同時代のドイツ映画監督ムルナウの諸作と比較すると贅沢な不満ながら、ラングのサイレント時代の初期作品にはアイディアは豊富で映像は鋭利ですが潤いは乏しく感じられます。冴えた映像感覚や技法ではドイツ映画界でも一歩リードした存在で、1作ごとに試行錯誤を重ねながら進展を果たしてきたのは本作の洗練されたサスペンス技法からでも感じられますが、次作で一気に飛躍する予兆はここまでの作品からは見られないので、『死滅の谷』がいかに画期的作品だったのかがうかがえます。
●11月11日(日)
『破片』Scherben (監=ループ・ピック、Rex-Film GmbH, '21.5.27)*50min, B/W, Silent; 日本公開大正12年(1925年)4月17日(尺数不詳) : https://youtu.be/NuZahIcfuKo
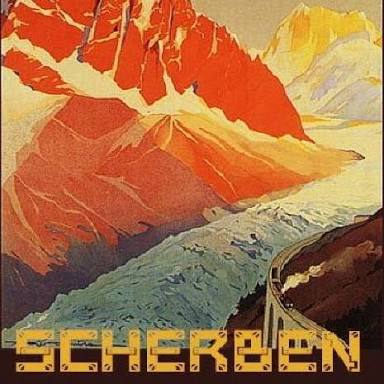

……カール・マイヤーは共作者のハンス・ヤノヴィッツともども『カリガリ博士』が出世作になった脚本家で、ヤノヴィッツも『カリガリ博士』によって一本立ちの中堅脚本家になりますが、実際『カリガリ博士』のシナリオ決定稿をまとめたのはフリッツ・ラングでしたし、マイヤーとヤノヴィッツはカリガリ博士を社会的陰謀を一身に体現した象徴的人物としてその陰謀を描き、露見し、処刑されて秩序が回復するまでを描いた社会的メッセージの強い反体制的内容を意図したが、映画会社の自主規制で改変されたと主張しており、一方当初監督予定だったフリッツ・ラングは(ヒット作『蜘蛛 : 黄金の湖』の続編『蜘蛛 第2部 : ダイヤの船』の同月公開の企画が急遽上がって、『カリガリ博士』は同じ会社の先輩監督ロベルト・ヴィーネに譲りますが)プリプロダクション段階でマイヤー&ヤノヴィッツ脚本を「アマチュア並み」と一蹴、現行の映画化された決定稿に改稿したいきさつがあります。マイヤー脚本はヴィーネが『カリガリ博士』の次作に発表した『ゲニーネ』やムルナウの『フォーゲルエート城』'21で表現主義映画の脚本家と見なされるようになったのですが、一連の表現主義映画でもっともアヴァンギャルドな手法をとった作品が'12年発表、'17年初演の表現主義舞台劇『朝から夜中まで』の映画化('20年製作、'21年完成)だったように、表現主義芸術運動そのものは'10年代初頭から文学、美術、音楽、演劇運動などに起こっており、映画が表現主義を摂取するのは長編映画時代の到来と第1次世界大戦後の景気回復と表現の自由化を待たなければならなかった事情があります。ドイツ映画は『カリガリ博士』の成功をドイツ映画ならではの屋外ロケ条件の不足、他のヨーロッパ映画と較べても低予算でスタジオ・セット撮影にせざるを得ない条件に見合った、E・T・ホフマン流の怪奇譚の伝統と結びつけた、小規模ながら鬼面人を驚かす風の路線で国際流通商品を目指すことになりましたが、カール・マイヤー自身はもっとオーソドックスな指向を持った脚本家だったのがうかがえるのが「室内劇映画」三部作です。マイヤー脚本から最高の映画になったのがホテルの玄関番老人の退職日の絶望を描いた『最後の人』、浮気夫の回心と夫婦愛の回復を描いた『サンライズ』という人物・舞台・事件ともに限定されたシンプルなもので、それをムルナウという天才監督が取り上げた時に傑作になったので、「室内劇映画」三部作はもっと悲劇性を強調した連作ですしループ・ピック、パウル・レニらはサイレント時代の終わりとともに逝去してしまった(事故死ですが、ムルナウもそうでした)中堅監督ですが、脚本の意図をよく酌んで、演出やセットは奇をてらわない、端正といっていいものです。『破片』の場合は屋外シーンと屋内シーンの対照があり、必ずしも室内劇映画という感じがしないのはヴェルナー・クラウスの見回る鉄路や、娘の不貞に絶望した母がさまよい出てすがる雪の中の十字架像、妻を探し回る主人公といった具合に悲痛な重要場面が屋外でもありますし、また徹底した冷血漢に描かれた監督官の描き方はあえて何の反応もしない人物としか描かないことで十分描かれているのですが(フルサイズのショットなのに激昂した踏切番に迫られて咥えた煙草がぽとりと落ちるだけでも強い印象を残します)、無字幕映画にしたことで生まれた効果が非常に大きい反面、娘がこの冷血漢の監督官に連れて行ってとすがる場面には心理的な辻褄あわせを考えないわけにはいきません。通常ならばこれは娘の側の未練に見えますがこの映画の設定ではそれは不自然なので、辻褄あわせをすれば娘が監督官の誘惑に身を任せたのも、連れて行ってとすがったのもこの山奥の親子三人だけの生活への倦怠、嫌厭から家庭崩壊のきっかけを作ったと解釈もできるので、そうなると映画への解釈全体も変わってきます。冒頭の食卓シーンはドイツ映画では珍しく幸福でおいしそうな家庭の食事シーンに見えるからですし、心理的解釈とすれば監督官は権力者といえども泊めてもらった職員の娘を犯すとは軽率に過ぎますし、また娘の行動は母の死に取り乱したごく衝動的なものと取る方が流れとしては自然で、最初は母の死に自責の念と父からの懲罰を恐れて監督官にすがり、拒否されると父に監督官に犯されたと告白した、というのが必要最低限の台詞字幕があれば容易に伝わったはずです。サウンド・トーキー映画で台詞がないのと、人物が会話しているのに無字幕で通したサイレント映画ではまったく違うので、本作は「1日目」~「5日目」の章タイトルと結末の唯一の字幕「私は人殺しだ」が効いていますが、実験的な無字幕手法を地味な題材で描いて異色作を目指した作品として成功しながらも、映画の柄の小ささは否めないものになっています。しかし『カリガリ博士』の脚本家が表現主義を乗り越えてなお実験性を追求したインパクトの強い映画という工夫がこういう試みで、しかも三部作構想のヴァリエーションを考案したのは、外見上はまったく反表現主義といえるほど地味な作品だけにこの時代のドイツ映画の探求心の旺盛さを感じさせます。
●11月12日(月)
『裏階段』Hintertreppe (監=レオポルド・イェスナー/パウル・レニ、Hanns Lippman-Henny Porten Produktion'21.12.11)*44min, B/W, Silent; 日本未公開 : https://youtu.be/bLXFFqrQMEk (English Version)


……実際の着想・執筆順はわかりませんが、『破片』は家庭悲劇、本作は情痴悲劇、『除夜の悲劇』'23は再び家庭悲劇(大晦日の日、口うるさい不仲な老母と妻の板挟みになって苦悩した夫が自殺するまで)という配置になっています。ループ・ピックの『除夜の悲劇』は大手のウーファ映画社作品になったので比較的明快なホームドラマ悲劇が回されたのかもしれません。もとよりこの三部作は明るい内容ではありませんが、『破片』と『裏階段』は陰惨な度合いが強く、独立プロダクション製作ならではの妥協のなさがあり、その実績を持ってウーファ映画社での『除夜の悲劇』が実現したとも言えそうです。主な舞台となる屋内裏階段の表現主義的セットと反表現主義的な現実的内容の破滅メロドラマが乖離していること、しかし本作への評価基準には表現主義映画へのアンチテーゼを示した意義を抜きにはできないことが批判的評価を招いたのですが、ヒロイン女優のヘニー・ポルテン自身のプロダクションによる製作であることは郵便配達夫役のフリッツ・コルトナー、恋人役のヴィルヘルム・ディーテルレの演技とともに賞賛されており、人物の性格や心理も『破片』より素直に観客に説得力のあるものです。恋人役のディーテルレの登場は映画冒頭と結末だけですから女中役のヒロイン、ヘニー・ポルテンと彼女に思いを寄せる郵便配達夫フリッツ・コルトナーだけで映画の大半は占められ(本作も『破片』同様登場人物に役名はありません)、サイレント映画のリアリズム演技の好例となっていますが、日常的な題材からごく自然なリアリズムのドラマ映画を作ったフランスのルイ・デリュックの『エルノアへの道』'21、『さすらいの女』'22、『洪水』'23と較べると映画全体にまだ誇張が感じられる。デリュックの映画は港町の頽廃したバーを描いた『狂熱』'21以外は当時全然評判にならず、現在でもフランス映画の先駆者としてシンボル化されている以外大して観られていないのですが、マイヤーの「室内劇映画」三部作と似た指向を持った(ただしデリュック作品はフランス撮影の利点を生かして徹底室内劇『狂熱』以外はロケーション撮影に徹した風通しの良さがあります)が予算と規模を拡大し、見世物的派手さに向かいつつあった(その第1人者がフリッツ・ラングで、『裏階段』の2か月前に公開された『死滅の谷』は絶讃を浴び、以降ラングは素晴らしい成果を上げていきますが)ドイツ映画の潮流の中で、最小キャストかつシンプル、かつ低予算の『裏階段』にはそうした反動性で逆説的にインパクトを狙ったものという指摘も賛否両論を呼び、また無字幕映画の効果の大きさは『破片』よりさらになだらかでしみじみとした味わいのある一方、あらすじでシノプシスによるとして「」でくくった部分はディーテルレとコルトナーの二人の男それぞれのキャラクター、それに対するヒロインのポルテンの心情の要でもあり、女の奪い合いという単純な対立ですから漠然とした口論でも十分に通じますが、シノプシスによるような意図であればこれを無字幕で通したのは明らかな無理があります。表現主義映画に代わる新機軸として打ち出された無字幕サイレント長編映画の趣向の面白さと手法的強引さの両方が感じられる、しかしこれも『破片』ともども成功した佳作と言える作品でしょう。なお無字幕映画の系譜は次回以降も、アルトゥール・ロビソン『戦(おのの)く影』'23、カール・グルーネ『蠱惑の街』'23、ループ・ピック『除夜の悲劇』'24、F・W・ムルナウ『最後の人』'24をご紹介する予定です。