映画日記2018年11月25日~26日/サイレント時代のドイツ映画(9)

●11月25日(日)
『伯林=大都会交響楽』Berlin: Die Sinfonie der Grobstadt (監=ワルター・ルットマン、Fox Europa'27.9.23)*65min, B/W, Silent; 日本公開昭和3年(1928年)9月14日(尺数不詳) : https://youtu.be/0NQgIvG-kBM

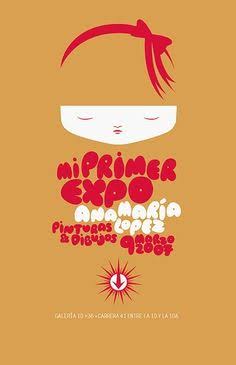
『警察調書 暴行』Polizeibericht Uberfall (監=エルノ・メッツナー、Deutscher Werkfilm'29.4.9*検閲により「犯罪奨励作品」として上映禁止)*22min, B/W, Silent; 日本未公開 : https://youtu.be/us4hRcf2GKc

[ 解説 ]「音楽派映画」、「純粋映画」と呼ばれた作品。劇性を排除し、ドキュメンタリー画面のモンタージュによって、大都会の姿をリズミカルに描いた前衛作品。(無声)
[ あらすじ ] 列車が暁の靄を破ってベルリンに入り、時計が五時を示す。次第にベルリンの町が目醒め、それが漸く活気を帯び出して来、子供が学校に行き、ブルジョアが朝の運動に馬を森に駆ける…といった具合に、様々な画面の積み重ねによって、ベルリンの1日を映し出す。
――貨物列車の疾走に始まり列車の視点から郊外からベルリン市内への視点移動で午前5時からの朝模様を描く第1幕、通勤時間帯の8時前後の通勤通学・店や工場の始動を描いた第2幕、午前中の盛んな市民活動を描いた第3幕、正午が来て昼食が始まり、そのまま午後のベルリン市内を描く第4幕、街灯が灯り、夜のベルリンの盛り場や街並みが描かれる第5幕、と本作は1日のベルリンを描いているのですが、手法としては羅列に留まることがしばらく観ていると気になってきます。列車駅、バス停、市街の自動車交通と来て開店するパン屋、八百屋、雑貨屋、婦人服店、宝飾店、時計店という具合に、午後にはフットボール、サッカー、テニス、ボートレース、競馬、競輪、競泳……という具合に運動種目が続き、夜になればレストラン、カフェ、オーケストラ劇場、オペラ座、映画館、ナイトクラブ、カジノ……と確かにベルリンという大都市のカタログにはなっていて、そこに世相風俗映画としての興味とドキュメンタリー映画的価値はあるでしょうし、映像も鮮やかですが、細部の総合が果たしてベルリンという大都市全体の実体を把握した映画になっているかは大いに疑問があるので、そこらへんに「絶対映画」についてのルットマンの履き違えがあり、ジガ・ヴェルトフのドキュメンタリー映画や、もっと言えばドキュメンタリー映画の祖ロバート・フラハティとも'20年代に前衛映画から出発したヨリス・イヴェンスとも違う、平坦な羅列的ドキュメンタリーでしかない不満があります。
その点ではルットマンの盟友的位置から出発したハンス・リヒターは画家出身でもあって、「朝食前の幽霊」(「朝飯前」ではなく、午前中という意味で、映画内では午前10時~正午までを時計が刻みます)は10分もない短編ですが、4つの帽子が空を舞う冒頭からさまざまな変なトリック映像が続き、最後は男4人が野外の四角い小テーブルに向かってちょこんと腰を下ろすまで、ダダイズム的な奇想に的を絞った実験映画の短編ですが奇想の連続に無理がなく、一貫した発想の連続性が感じられる好編になっています。またエルネ・メッツナー(1892-1953)は美術セット・デザイナーで、ルビッチやヴィーネ、グルーネ作品を経て『喜びなき街』'25以来のパプスト作品のセットも担当していましたが、'27年~'28年にかけて6本の短編を監督しており、その中で新即物主義の短編映画の傑作と名高いのが、実際の新聞記事の映画化で、交通事故に遭った男の落とした硬貨を拾った男がとんだ災難に巻きこまれる偶然また偶然の顛末をきびきびと描いて実験映画色を忘れて手に汗握るサスペンス短編になっている『警察調書 暴行』で、大がかりな『伯林=大都会交響楽』よりもずっと映画として筋の通った好短編になっているのは皮肉な気もします。ルットマン作品では観るべき面は素材でしかなく、映画としての工夫は素材の網羅性でしかない。実験映画らしい「絶対映画」をそうした作業による否個性的製作方法に求めたのだとしても、リヒターのすっとぼけた味やメッツナーの密度の濃い反ドラマ的偶然劇の方が面白いという皮肉があり、『伯林=大都会交響楽』は歴史的作品としての意義にとどまり、ルットマンの同作の可能性の部分は現在見るとすべてヴェルトフの『カメラを持った男』に包括されてしまっているように思えます。
●11月26日(月)『帰郷』Heimkehr (監=ヨーエ・マイ、UFA'28.8.29)*115min, B/W, Silent; 日本公開昭和5年(1930年)4月2日(尺数不詳)キネマ旬報ベストテン(外国無声映画)3位 : https://youtu.be/3KNqGS87S7U (English Version)

[ 解説 ]「アスファルト」「ヴァリエテ」と同じくエリッヒ・ポマー氏指揮になった作品でドイツ新進作家レオンハルト・フランク氏の原作舞台戯曲『カールとアンナ』に材を取りフレッド・マヨ氏とフリッツ・ヴェンドハウゼン氏が脚色し「アスファルト」「ヴェリタス」のヨーエ・マイ氏が監督したものである。俳優としては「真紅の文字」「肉体と悪魔」のラルス・ハンソン氏、「アスファルト」「メトロポリス」のグスタフ・フレーリッヒ氏、「ハンガリア狂想曲」のディタ・パルロ嬢が主演している。カメラは「アスファルト」のギュンター・リッタウ氏が担任。(無声)
[ あらすじ ] 荒れ果てたシベリアの平原の一部、干からびた潅木林の真中に一軒の小屋がある。ここに捕虜の身をはるかに逃れて二人の若者リヒヤルト(ラルス・ハンソン)とカール(グスタフ・フレーリッヒ)が暮らしていた。無限とも思われる淋しい生活に二人の友情は鉄よりも固く結びついた。リヒヤルトはカールに自分の結婚生活をそして愛する妻のことを幾度となく物語った。ついに二人は故郷に対する強い憧れから砂漠を横切ろうと企てた。だが彼等の折角の努力もコザック兵の発見する所となりカールは身を以て逃れることが出来たがリヒヤルトは捕えられ刑罰としてシベリアの鉛鉱に送られる。カールが帰郷した時、戦いは終わった。リヒヤルトの妻アンナ(ディタ・パルロ)が遠く捕われの身となった良人を待って儚い日をすごしている所へ訪れたのはカールであった。彼はリヒヤルトとともに過した年月を彼女に物語る。その友情の物語がカールとアンナに他人でない感情を湧かさしめる。その気持がだんだん濃くなってゆく。リヒヤルトの行方は杳として不明で何の便りもない。二人の若い男女は胸に湧き立つ熱い血潮と懸命に戦っていたが或る夜、町へ遊びに出た帰途カールとアンナは最初の臆病な抱擁を交わす。一方ロシア革命のため自由の身となったリヒヤルトは耐え切れぬ思いを抱いて故郷へ急いだ。長い旅路を終えて我が家の扉を開いたリヒヤルトの眼に映ったものは余りにも悲しい光景だった。アンナはすでに自分の妻ではない。そして相手の男というのは親友カールであった。これがあらゆる艱難の年月を経た後のリヒヤルトの帰郷であった。突然襲い来る烈しい怒りに彼の手はピストルに延びた。が彼はやがて武器を静かに置いた。彼は友の手とかつては己が愛妻たりし女の手とを握った。そして彼は故郷から永遠に立ち去ってゆく決心をする。悲壮なリヒヤルトの出立だった。彼を乗せた船が新たな生涯に彼を運び去ってゆく時カールとアンナとは感謝の涙にくれるのであった。
――と、まあ内容は第1次世界大戦版の「リップ・ヴァン・ウィンクル」なのですが、結末ではアンナの夫リヒャルトが船員になって、戦友カールが急いで出航直前の貨物船にリヒャルトを引き止めに行くと、リヒャルトはカールに船の甲板で「I don't want a woman who don't want me !」(英語字幕)と男なら(womanをmanに変えれば女性でも)誰でも人生一度は言ってみたい台詞を決めます。それに続く、だからアンナは頼んだぜ、というやり取りは二人の仕草でわかります。本作は台詞タイトル、説明タイトルとも字幕タイトルは最小限に切り詰められている(全編を通じて10数枚に満たない)のがこの結末まで観てハッと気づくほど自然に無字幕映画の成果が取り入れられており、登場人物の会話内容は映像を観ていれば自然に伝わってくるのでサウンド・トーキーでなくても演出は自然にトーキー作品と変わらないものになっていて、サイレント映画技法の完成型がすでに演出としては理想的なトーキー作品と近く、しかも音声抜きに作品内容を十分に伝えるものになっている好例となっています。本当にポイントだけの台詞を台詞タイトルで示しており、またそれ以外の会話はイエス・ノーのやり取りや笑い声、嗚咽といった具合に演出でもそれ以上の音声化される声は映像で表現できる演出にされているので、トーキー映画とサイレント映画の並立論が提唱されたというのも本作やマイの次作『アスファルト』、時期を同じくするパプストの『パンドラの箱』『淪落の女の日記』などのそうした成果があったからでしょう。パプスト作品も『喜びなき街』'25、『心の不思議』'26、『懐しの巴里』'27、『邪道』'28と徐々に完成度を高めてきたので、ハリウッドでムルナウが撮った『サンライズ』'27、シェストレムが撮った『風』'28とともにこれらはサイレント映画の頂点を示すものであり、そうした名作と較べるとサウンド効果を優先した企画が横行した初期のトーキー作品がアメリカ映画の新作の質が急落した、と思われたのも当然という気がします。アカデミー賞の第1回は'27~'28年度作品が対象で第1回だけ芸術作品部門とヒット作品部門に分かれ、『サンライズ』と『つばさ』'27が受賞しましたが、サイレント映画の受賞は同年だけで第2回はアメリカ映画史の汚点『ブロードウェイ・メロディー』'29とひどいトーキー作品が最優秀作品賞に選ばれたので、第3回『西部戦線異常なし』1'30、第4回『シマロン』'31、第5回『グランド・ホテル』'32以降ようやくトーキー作品もサイレント円熟期の水準に追いついた、と言えます。この頃になるとアメリカ・ヨーロッパ映画はサウンド・トーキー映画でも立派な作品を作れるノウハウが行き渡ったのですが、ドイツ映画は'33年のナチス政権成立で映画統制が敷かれることになり、映画統制下では国際市場に売り出せる企画が激減してドイツ国内向け映画、国策映画が大半になってしまい、ユダヤ系人種の多かった映画界では映画人のハリウッドへの移住者(自発的亡命者)が1,500人に上る事態になります。話を本作に戻すと、英題『Honecoming』でアメリカでも好評だった本作は日本ではさらに国際ヒットしたマイの次作『アスファルト』の大ヒットですぐに引っ張り出されてきて公開された形で、『アスファルト』は当時新進の人気作家だった川端康成(日本映画黎明期に『アマチュア倶楽部』'20の企画・文芸顧問を勤めた谷崎潤一郎同様、ムルナウ『最後の人』の影響を素早く受けた独立プロ映画『狂つた一頁』'26の脚本家でもありました)が熱狂絶賛の映画評を発表したほど日本では爆発的人気を博し、マイの映画はむしろ古風な人情メロドラマですし技法的にも洗練されてはいますが中庸で、ラングやムルナウ、パプストのように鋭い感覚が光るものではありませんが、人間ドラマを適切な情感をこめて描く手腕は確かで、『アスファルト』のヒロイン女優も絶賛されましたが本作のディタ・パルロも『アタラント号』や『大いなる幻影』のヒロインがこんなだったのかと思うくらい艶っぽく、グスタフ・フレーリッヒも『メトロポリス』のお坊ちゃんぶりはこういう風にもなるのかというくらい天然色男ぶりが戦線でひどい目になっている夫リヒャルト側の目線で観る観客には腹が立ってくるほどです。ラルス・ハンソン演じる夫リヒャルトの苦悶もマイの後輩の精鋭監督なら切り込みすぎてしまうあたりを過不足なく描いて自然さと説得力があるもので、ヴェテラン中のヴェテラン監督ならではのうまい映画になっています。ラング、ムルナウ、ヴィーネ、グルーネ、ループ・ピック、デュポン、パプストらの'20年代ドイツ映画(加えてたぶんアメリカのスタンバーグ作品)の成果を第1世代のマイが巧みに消化したのが名作『帰郷』『アスファルト』と言えそうで、ドイツ映画らしい実験性は微塵もありませんが、マイの場合普通の人情メロドラマだったのがかえって良かったということでしょう。