映画日記2019年5月4~6日/蔵原惟繕(1927-2002)と日活映画の'57~'67年(2)


鈴木清順(1923-2017)『~13号待避線より~その護送車を狙え』(日活'60.1.27)*79min, B&W : https://youtu.be/Njj2m2E14cQ (Full Movie)
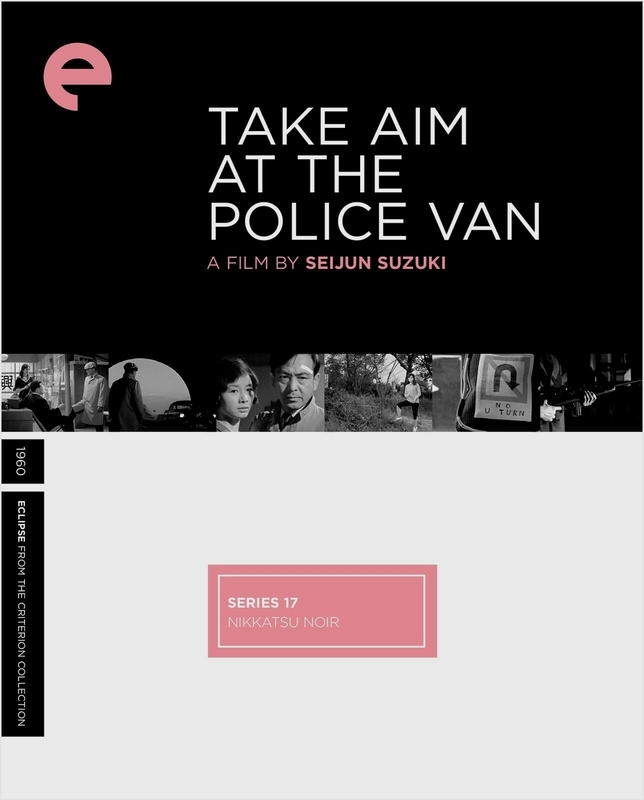

[ 解説 ] 島田一男の原作を、「暗黒街の対決」の関沢新一が脚色し、「素っ裸の年令」の鈴木清順が監督したアクション・ドラマ。撮影は「おヤエの初恋先生」の峰重義。
[ あらすじ ] 護送車が襲われた。二人の囚人が即死し、犯人は逃亡した。死んだ囚人は冬吉(岩崎重野)と竜太(上野山功一)である。護送責任を問われた看守長の多門(水島道太郎)は、六カ月の停職命令を受けた。彼は犯人の追求に乗り出した。第一の手がかりは、車に乗っていた囚人の五郎(小沢昭一)だ。彼は保釈金をつんで出所していた。ストリッパーの恋人津奈子(白木マリ)と熱海にいた。多門も熱海に出向いた。津奈子とマリ(久木登紀子)が旅館でショーを開いている最中、マリが殺された。マリは死んだ竜太の姉だった。多門はストリッパーを斡旋している浜十組を訪れた。浜十(芦田伸介)は入院してい、娘の優子(渡辺美佐子)が現われた。美しく、好意的だった。五郎の車が崖から落ちた。現場には彼の鞄があった。――多門の下宿に、上京した優子がやって来た。優子の情熱を帯びた視線が多門にはまぶしかった。ある時、多門は一台のトラックを追跡したが、いつのまにか数人の男に囲まれていた。浜十の乾分赤堀(安部徹)もその中にいた。気がついたところは病院の一室だった。優子がいた。現場にいた彼女が、工場の非常サイレンを鳴らして救ってくれたのだ。五郎の死は偽装だった。現場にあったライターに、五郎の指紋が残っていたのだ。優子の部屋に現われた赤堀を多門は倒した。多門は五郎とその黒幕がいるという御殿場に優子と急いだ。――女体密輸の黒幕は、優子の父親の浜十だった。
――本作はいきなり囚人移送車襲撃から始まって、この囚人暗殺事件がないと担当刑務官の水島道太郎が事件の真相を追う主人公にならないから仕方ないのですが、どうも口封じのため殺されたらしいとしか動機がはっきりしない。同房だった囚人の小沢昭一はあとで偽装暗殺され実は人身売買組織の一員だったのが判明しますが、小沢昭一から洩れたのを恐れて殺されたのか組織の一員で裏切りを恐れて殺されたのかわからない。また小沢昭一の恋人のストリッパー役の白木マリの同僚ストリッパーが殺されますが、殺された囚人の妹であるとともにストリップ一座は人身売買組織の末端の水商売女性集めに従事していたらしいので、これも殺された動機がはっきりしないというか、主人公が白木マリを突きとめ妹の所在に感づきそうになったから殺され、またストリップ一座を管轄するヤクザの親分の娘の渡辺美佐子に水島道太郎が近づいたので渡辺美佐子まで狙われるほど内部抗争が激化したとしか思えないので、主人公が越権捜査(刑務官には警察権はありません)を始めたために一連の事件がドミノ倒しのように発生したというのが合理的解釈になるので、そう思うと本作は実にとんでもない話です。人身売買組織摘発にしても主人公には捜査権限がないので、ストリッパー殺害のあたりで地元熱海の警察に委ねるのが現実事件では限度と思われる。そこが実話と「実話調」の違いで、主人公があくまで黒幕の正体に迫るまで越権捜査を止めないがために事件は転がり続けるので、一つひとつの事件の真相や動機はますますはっきりしなくなる。組織の内部抗争と渡辺美佐子の関係も実ははっきりしないので、渡辺美佐子が水島に好意を見せ始めたので親分の娘でも危険視して渡辺を狙う一派が内部抗争を始めたように見える。そんな具合に辻褄合わせしようとすればするほど無理の連続を積み重ねて出来上がっているのが本作ですが、観ている最中には渋滞感はちっともなく事件また事件の連続なので、実は主人公視点の実話調を生かして全然リアリズムではないホラ話を観せられていたのに気づくのは観終えてしばらく経ってからです。鈴木清順の'60年代作品は傑作揃いですから本作が話題になることはめったにありませんし、以降の傑作と較べると本作はまだ助走段階でもありますが、全盛期の傑作からさかのぼってこの作品を観てもちゃんと納得のいく作風なのはさすがで、また本作の辻褄の合わなさも現実事件ではごく普通に起こり得ると思えば何ら作品の瑕にはならないのではないでしょうか。
●5月5日(日)
蔵原惟繕(1927-2002)『ある脅迫』(日活'60.3.23)*65min, B&W : https://youtu.be/vbQt82tWF5M (Fragment)
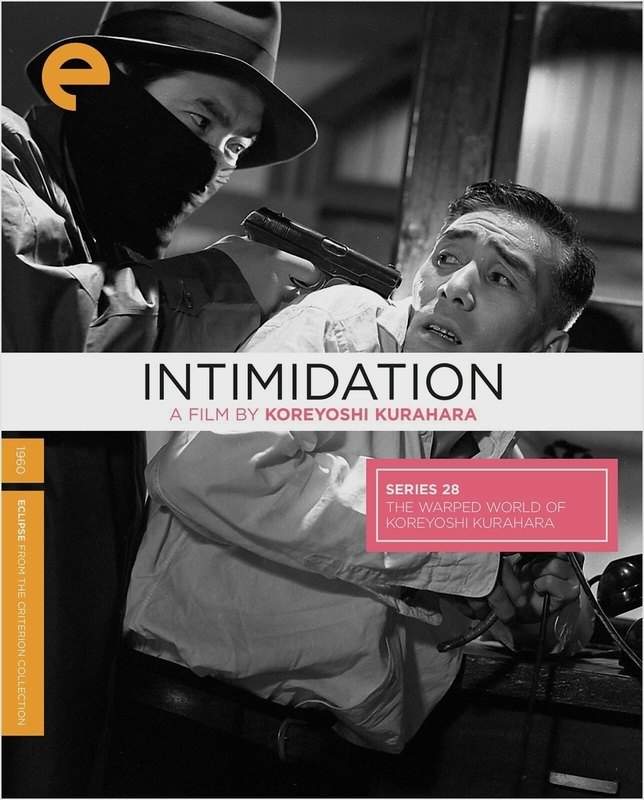

[ 解説 ] 多岐川恭の原作を、川瀬治が脚色、「われらの時代」の蔵原惟繕が監督した推理映画。撮影は「~キャンパス110番より~学生野郎と娘たち」の山崎善弘。
[ あらすじ ] 北陸××銀行直江津支店次長滝田恭助(金子信雄)は、本店の業務部長に栄転することになった。彼の妻(小園蓉子)は頭取の娘で、このことも出世を早める原因らしかった。滝田の送別会で、一人離れて座っている男があった。中学時代に滝田と同級だった庶務係の中池(西村晃)だ。滝田の妻はもとはといえば中池の恋人だった。それを滝田が奪ってから彼の人生街道が開いたのだ――。宴会の帰途、滝田の前に立った男がある。ヤクザの熊木(草薙幸二郎)だ。滝田が女(白木マリ)を養うために印鑑を偽造、浮貸しをしている秘密を握っているのだ。三百万円よこせと脅迫した。そして、拳銃を渡して金庫破りをすすめた。ある夜、レインコートを着、ハンチングと黒いスカーフで顔を隠した滝田は、小使(浜村純)を縛って銀行へ押し入った。宿直の中池が帰って来た。滝田は拳銃をつきつけ、金庫の前に中池を引っ立てた。しかし、中池は滝田の正体を見破っていた。滝田は急に笑い出し、防犯週間だから銀行ギャングの予行演習を考えついたのだと言った。この場は何とかつくろったが、熊木が三百万円を待っている。二人は断崖の上でもみあい、足をすべらした熊木は悲鳴を残して落ちていった。翌日、滝田は中池に呼び止められた。中池は自分が熊木を使って脅迫させていたのだと言った。――妻や子と任地へ向う滝田は汽車に乗っていた。しかし、隅の方の席には中池が座っていた。「これからあんたの行くところへはどこまでもついて行く。銀行はやめたよ」と滝田を見上げて言うのだった。
――あらすじを知らない方が本作は意外な展開が楽しめ、さらにキネマ旬報のあらすじでは省略されている痛烈なオチで映画は締めくくられるのですが、何にしても同級生の出世男の金子信雄と万年平社員の西村晃という、性格俳優の名優ながら映画の主役には絵にならない二人のしがらみ劇を小品心理スリラーの佳作に仕上げた本作の企画は大したもので、原作自体も今ならテレビの2時間ドラマですらも地味すぎると判断されるような渋い話です。しかも舞台は新潟県直江津市(当時)の銀行の地方支店と、直江津市は現上越市で新潟県では由緒ある(「山椒大夫」の舞台!)町ですが都会派サスペンスでもない。また本作では脅迫が事件の焦点で、最初の脅迫者ともみ合いになり海岸の岩壁にずり落ちた脅迫者を金子信雄は見殺しにしますが、脅迫者殺害容疑がかかるわけではないので焦点が殺人に切り替わる展開でもありません。最大のサスペンスは金子信雄が脅迫者に強要され自分の銀行に夜間に強盗に入る場面で、金子は宿直の西村晃を飲み屋の座敷に誘い酔いつぶさせて浜村純(!)の小使一人の銀行に覆面とサングラスで押し入るのですが、サングラスを落として割ってしまう。しかも長いつきあいの西村晃が酔いつぶしたはずが宿直に遅れてやってくる。なおも強盗を遂行しようとするも西村に正体がバレてしまった金子は抜き打ちの防犯訓練だと誤魔化し、支店次長とは言え銀行側が金子の言い分を認めて称賛するのもサスペンスものならではの展開ですが、金子が訓示で当直の西村の遅刻を非難するのも皮肉なら結局脅迫者に渡す金を用意できなかった金子が脅迫者との格闘で脅迫者を断崖から落ちるのを見殺しにするのも悪夢めいていれば、ほっとしていいのか未必の故意の殺人の嫌疑を恐れることになるのか不安を抱えたまま栄転異動が迫る寸前に真の脅迫者が姿を現す悪夢の連続は、一つひとつの事件が不発に終わる地味な悪夢だけに逆に累積効果は大きく、犯罪映画が悪夢に接近した例としてアメリカのフィルム・ノワールの古典、エドガー・G・ウルマーの『恐怖のまわり道』'45やジャック・ターナーの『過去を逃れて』'47に近似しており、これらの犯罪らしい犯罪の起こらない悪夢的異色フィルム・ノワールの評価はアメリカ本国でも'80年代以降定着したもので『恐怖のまわり道』『過去を逃れて』(ともにアメリカ国立フィルム登録簿選定登録作品)とも日本劇場公開は映像ソフト発売に伴う2012年(平成24年)です。本作の世界初DVD化がアメリカ盤で2011年と思うと、『ある脅迫』はウルマーやターナーの作品を知らずに偶然作られた日本映画の突然変異的悪夢系フィルム・ノワールの佳作ということになり、それもメイン作品ではなく併映用中編、メイン作品にはなり得ない渋く地味な企画と渋く地味な性格俳優のW主演、しかも地方都市のごく限られた人物配置と舞台設定という具合に条件がそろったからこそ狙ったわけでもないのにアメリカのマイナーな低予算犯罪映画そっくりな佳作が生まれたと見られ、こういう映画があるから量産時代の日本映画は底が知れない。日活映画で蔵原惟繕監督作という先入観があってもなくても本作が今なお面白い映画として観るに値するゆえんです。なお本作の結び、オチというかサゲはご覧になる方によって是非が分かれるようなもので、蛇足と取るか見事などんでん返しと見るか、いずれにせよ観客を最後に煙に巻いて終わる結末(原作由来にせよ)には違いなく、これもあり(悪夢度アップ)なのではないでしょうか。
●5月6日(月)
蔵原惟繕(1927-2002)『狂熱の季節』(日活'60.9.3)*76min, B&W : https://youtu.be/-JXvrq0o1E8
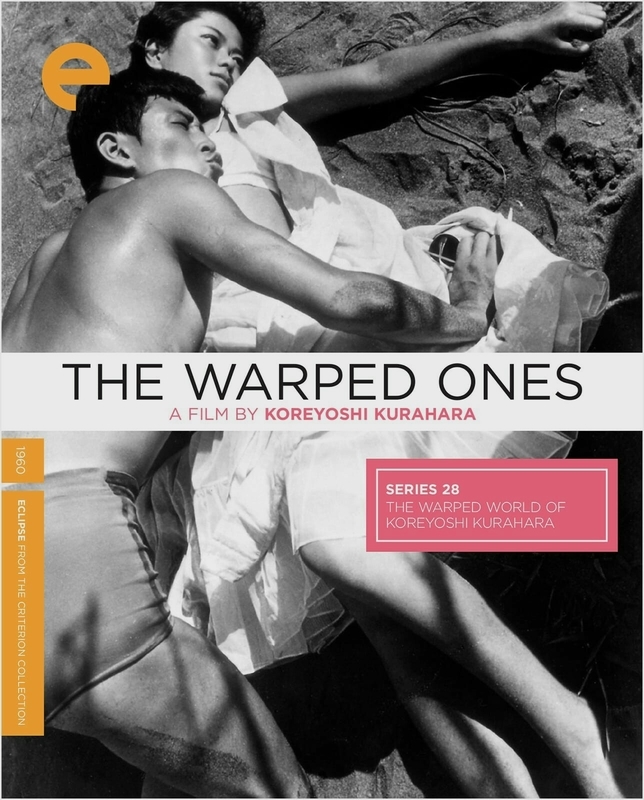

[ 解説 ] 河野典生の「狂熱のデュエット」を、「青年の樹(1960)」の山田信夫が脚色し、「ある脅迫」の蔵原惟繕が監督したもので、現代の若者たちを描く。撮影は「刑事物語 小さな目撃者」の間宮義雄。
[ あらすじ ] 二人の少年、明(川地民夫)と勝(郷英治)が少年鑑別所の門を出た。外は真夏だった。車を盗み出した二人は、ユキ(千代侑子)をさがして繁華街を飛ばした。ユキは外国人相手のパンパンで、明とは古いつき合いだった。白人を連れ立ったユキをみつけると、二人はホテルにパトカーを呼んだ。寸前、ユキは白人の財布を持って逃げ出した。その金で三人は海に向かった。海岸で明は一組のアベックに目をとめた。明を鑑別所に送り込んだ新聞記者の柏木(長門裕之)と恋人の文子(松本典子)だった。柏木を倒すと、明は文子を草むらの中で犯した。車を売った金で三人は安アパートを借りた。勝とユキは愛し合った。バーで明がビート・ジャズに酔っていると、文子が妊娠を知らせて来た。柏木の変らない愛情が苦しい、と文子は言った。勝は土地のやくざ、関東組に入った。ユキと世帯をもちたいからだった。文子は明に、柏木を汚してくれと頼んだ。傍のユキがニヤリと笑った。ユキは柏木を誘惑し、妊娠した。勝は怒らなかった。関東組の幹部になって楽をさせてやると慰めた。夜、明は文子のアトリエに入った。文子と柏木が帰って来た。精神的な平等を得た二人は幸福そうだった。明の姿を見た文子の心に、殺意が湧いた。事故を装って眠っている明をガス死させようとした。しかし二人の出ていった後、明は何事もなく目覚めた。明がアパートに帰ると、血だらけの勝がかけこんで来た。やくざのボスを殺して幹部になった、と叫びながら勝は死んだ。ユキは子供を始末することにした。明とユキが医者をたずねると、柏木と文子に会った。突然、明は青ざめる柏木にユキをおしつけ、文子を自分の方に引き寄せた。狂ったように笑う明とユキ、硬直したように立ちつくす柏木と文子、そのまんなかには、現代の虚無がビート・ジャズにのって吹きまくる。
――この作品は蔵原惟繕が脚本に山田信夫、撮影に間宮義雄を迎えたことでも画期的な意義があったもので、蔵原監督・山田脚本・間宮撮影のトリオは'62年の『銀座の恋の物語』(3月)、『憎いあンちくしょう』(7月)、『硝子のジョニー 野獣のように見えて』(9月)の3作を送り出すことになります。本作の続編と言うべきやはり河野典生原作による蔵原監督・山田脚本の『黒い太陽』'64.4は川内民夫が再びジャズ狂の「明」として登場し、『狂熱の季節』では在日黒人兵役のチョイ役だったチコ・ローランドとともに主演する幻滅とディスコミニュケーションの逃亡劇ですが、撮影は金子満司に代わっている。『黒い太陽』も見所の多い作品ですが川内民夫の「明」のキャラクターが下敷きなだけに『狂熱の季節』を先に観るのが順当ですし、『狂熱の季節』の時代の最先端を行くタイトルデザイン処理、圧倒的な美術、シャープな構図やB&W映像の露出の妙(特に逆光処理の腕前)、手持ちカメラ撮影の素晴らしさなど間宮カメラマンの成果の上に『黒い太陽』の映像もあるので、原作者からの意見もあったでしょうが昭和35年の日本の黒人ジャズのリスナーの感覚を正確にとらえている。ラップやヒップホップどころではないやばい音楽だったのが伝わってくる。石原裕次郎を発掘した水の江滝子(1915-2009)は太陽族映画の生みの親でもあるすごいプロデューサーでしたが、さすがに本作や『黒い太陽』など太陽族映画の究極型といえる作品は別のプロデューサーがついている。裕次郎も本格的なジャズ歌手の才能がありましたが、本作が数年前に作られていたとしても裕次郎主演の企画にはまずならなかったでしょう。しかし『狂った果実』の裕次郎が正統に発展したら本作になる可能性は十分にあったので、本作は川内民夫という共感しづらいキャラクターを演じて光る主演のためにマイナーな作品の宿命がつきまとい、さらにあまりに感覚的に反市民性の領域に踏みこんでしまったためにまともに観客の不快感を刺戟する映画になっており、主人公の行動原理に観客がついて行けないため映画全体が散漫に見えかねない、という不利も抱えています。松竹の大島渚や吉田喜重らは極度に方法的な自覚や反ヒューマニズム意識があったので、観客を市民的な共感に誘いながら市民的倫理の欺瞞の攻撃にまわる、強靭な論理性がありました。本作と同年の大島の『青春残酷物語』(6月)や『日本の夜と霧』(10月)、吉田の『ろくでなし』(7月)や『血は渇いてる』(10月)はフランスのヌーヴェル・ヴァーグへの明確な回答で、フランス映画には感覚はあっても論理や思想性は欠落しているではないかと日本のインテリ監督(大島・吉田は東西の日本の国立大学の主席卒業者でした)が反撃したものです。しかしあからさまな背徳性を許容する主人公の無軌道な行動をひたすら感覚だけ、しかも観客がまるで共感できない主人公の視点から徹底的に一貫して描いた本作は破壊力にかけては内外に匹敵する同時期の映画が見当たらないほどで、『ある脅迫』本作と連続する蔵原惟繕作品を観ると資質・指向性ともに'60年の2作『気のいい女たち』『伊達男たち』以降のクロード・シャブロルが真っ先に思い浮かびます。蔵原惟繕の食えないところは翌年には『破れかぶれ』『この若さある限り』『海の勝負師』『嵐を突っ切るジェット機』とあっけらかんと青春・アクション映画に戻ってしまうところで、さらに昭和32年('62年)には『銀座の恋の物語』『憎いあンちくしょう』『硝子のジョニー 野獣のように見えて』とメロドラマにもアクション映画にも傑作を連発する(『何か面白いことはないか』'63、『執炎』'64、『黒い太陽』'64と続きますからさらにややこしくなりますが)。ただし山田信夫脚本だけはある反骨精神がそれらメロドラマ作品にも筋を通していて、シャブロルには『銀座の恋の物語』や『憎いあンちくしょう』は撮れまいと思うと、以降も嫌みな映画を作り続けたシャブロルと照らして才能の生かし方というのが考えさせられる。やがて蔵原惟繕は『キタキツネ物語』'78や『南極物語』'83に行きつくので、『狂熱の季節』の監督だったこと自体が偶然だったように見えてしまうのです。