文学史知ったかぶり(18)
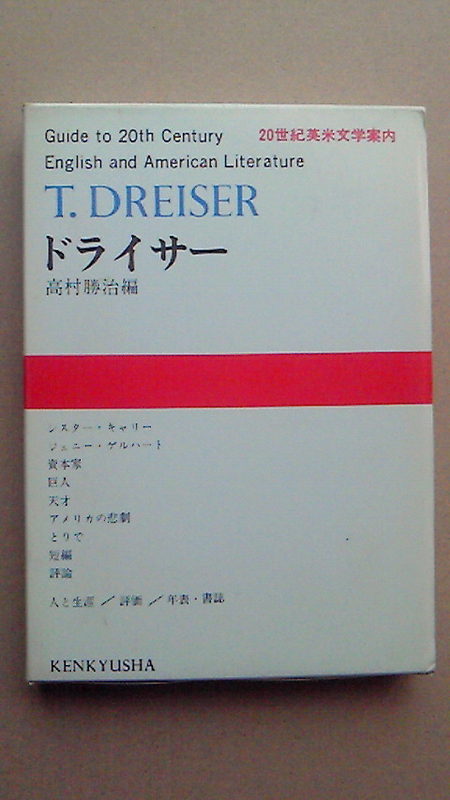
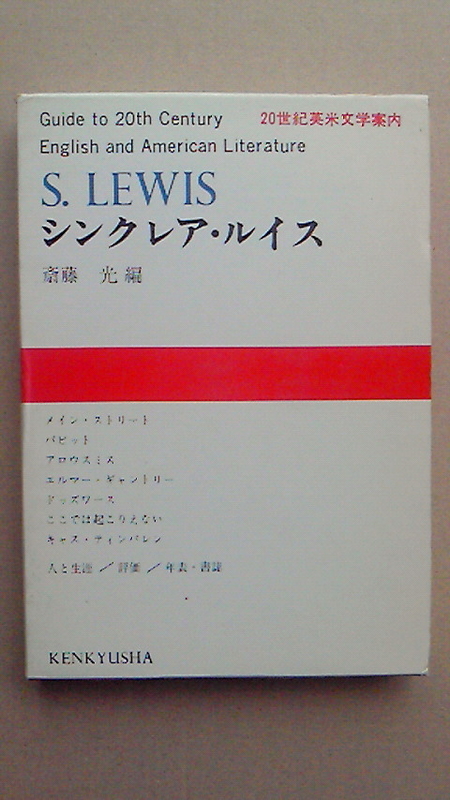
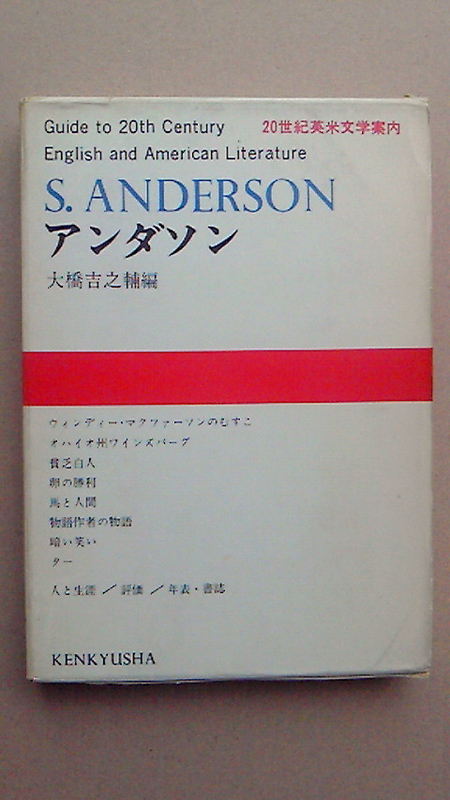
島崎藤村を始め、日本の自然主義小説家はアメリカの自然主義小説家とほぼ同年配でした。徳田秋声の『奔流』が1916年、藤村の『新生』と田山花袋『残雪』が1918年、岩野泡鳴の『五部作』の完成が1920年、近松秋江『黒髪』が1922年、正宗白鳥の『人を殺したが』が1925年ですが、これら自然主義小説の円熟と新人作家たちの台頭はアメリカ同様重なっており、佐藤春夫『田園の憂鬱』が1918年、島田清次郎『地上』と中戸川吉二『反射する心』が1919年、また宇野浩二『苦の世界』が1920年、藤澤清造『根津権現裏』と松永延造『夢を喰う人』が1922年発表で、はっきり昭和以降の方向性を備えた作品が現れています。
アメリカと日本は自然主義小説の輸入国家として類似した現象を起した、と見ることができるでしょう。どちらも原産国であるフランスから20年以上遅れて初期の試みがあり、初めは幼稚かまたは自然主義小説としての意図を外れた作品しか生みだせなかった。それがやがて自然主義小説の体をなしたものにはなったが、フランス本国の自然主義小説とは異なる性質の達成をたどることになった。
そこまでにほぼ一世代の年月がかかったため、アメリカでも日本でも自然主義小説の円熟と新人作家たちの台頭は同時期に起ったのです。新人たちの有利な点は前世代の自然主義小説家たちがそれぞれの国に見合った現代小説のスタイルを開発していてくれたからで、自然主義小説運動とは自然主義に偏らず輸入文化によるスタイルの革新であり、日本でもアメリカでも最初の小説のモダニズム運動と呼べるものでした。