●2月16日(金)
『マリヤのお雪』(第一映画社嵯峨野撮影所/松竹キネマ'35)*72min(オリジナル80分), B/W; 昭和10年5月30日公開 : https://youtu.be/UOMBpT8qnbc


○あらすじ 明治十年、西郷隆盛が熊本城から逃れ人吉にたてこもり官軍と対決しようという頃。戦禍から逃れる人々の中に賤しい稼業の女マリアのお雪(山田五十鈴)がいた。彼らは官軍に捕えられ、お雪は官軍の士官朝倉(夏川大二郎)に惹かれた。短いひと時であったが二人は進軍ラッパによって別れねばならなかった。数日後人吉に戻っていたお雪の前に現れたのは薩軍の捕虜の中から逃れてきた傷ついた朝倉であった。お雪の友達おきん(原駒子)は彼を訴えて賞金を得ようとしたが、お雪はそれを止めて彼を逃がしてやるのであった。モーパッサン原作「脂肪の塊」の翻案もの。
(津村秀夫『溝口健二というおのこ』長崎一編・溝口健二監督作品総リストより)


本作『マリアのお雪』と次作『虞美人草』はその直後に画期的作品『浪華悲歌』と『祇園の姉妹』が製作されたため注目されることの少ない作品ですが、冒頭いきなり民家街に大砲がどっかんどっかん炸裂する西南の役の真っ只中から避難のために逃げる乗合馬車の中でモーパッサンの「脂肪の塊」のまんま(ただし本作では酌婦は山田五十鈴のお雪と原駒子のおきんの二人)、乗り合わせた商家やその夫人たちに「こんな汚らわしい女たちと同乗できるか!」と侮辱されるシチュエーションになります。ところが馬車が官軍の手中に落ち、士官朝倉(夏川大二郎)が娘を連れてこい、という段になると先ほどまでお雪やおきんを侮辱していた商家の父母たちが「おっ父つぁん達を助けると思って行っておくれ」と自分たちの娘を差し出そうとする。威勢のいいおきんが立腹して「あたしが行ってくるよ!」と喧嘩腰で朝倉の部屋を訪ねるが追い返されてしまう。そこでもの静かなマリアのお雪が代わりに行って、静かに朝倉と酌を交わしているうちに朝倉も無理は言わなくなり、「時と場所が違えば俺とお前の縁も違ったろうに」と朝倉が詠嘆し、お雪は無事に帰ってきます。士官を演じる夏川大二郎の髪型が前髪を下ろした二枚目然としているのが可笑しいですし、原駒子演じる気っ風の良いおきんだって魅力的なのに山田五十鈴のお雪への態度とはえらく違うのが気まぐれですが、そこはドラマならではということにしましょう。後半は馬車が再び薩摩軍に救出されて薩摩軍から皆が一行か、という身元確認にまたまた商家の人々がお雪とおきんを「無関係です。汚らわしい」と先ほどの恩も忘れて侮辱する。「脂肪の塊」はこれが結末ですが、川口松太郎の翻案では薩摩軍の捕虜になって逃げ出してきた朝倉とお雪・おきんとの再会、女の意地を踏みにじったと朝倉を恨んで密告しよう、それをお雪に止められてそれならばと朝倉に砲銃を向けるおきんと、あんたも私もあの人に惚れたんじゃないか、もう二度と会うことも叶わない人じゃないかとおきんを抱きしめるお雪、銃を落としてお雪にすがりつくおきん、さらに続く砲火の響きと藪の中の小川の情景で小舟で去っていく朝倉を見送るお雪の立ち姿に室内楽アレンジの「アヴェ・マリア」が流れて(笑)映画は終わります。長回しのショットの中の人物の出入り、前作で最後のサイレント作品『折鶴お千』にもあったトランジション・ショット(同一カット内で時間的に前後の飛躍が描かれる。のちにベルイマンやフェリーニが多用)が本作にもありますが『折鶴お千』よりもわかりづらい用法なのはトーキー作品だからかもしれません。本作もなかなか面白い映画ですが、依田義賢を専属脚本家に迎えた次々作『浪華悲歌』で溝口の作風が変わった、と言われるのは本作が歴史ものだからというのもありますが、全編がセット撮影で非常に様式性を重視した人工的な作りに見えるのが主な原因ではないかと思われます。トーキー作品ならではの音声が伴ってこそ生きる場面も多いのですが、フィルモグラフィーを見るとサイレント時代から溝口健二は文芸ものの映画化作品が目立ち、本作はトーキーですが『浪華悲歌』以降のトーキー作品よりも『折鶴お千』以前のサイレント作品に近いのではないか、という印象を受けます。また評価の高い名作『瀧の白糸』'33(第51作、キネマ旬報ベストテン2位)から後、'36年の第58作『浪華悲歌』(ベストテン3位)、『祇園の姉妹』(ベストテン1位)まではスランプ期と言われていますが現在『折鶴お千』、本作、『虞美人草』などを観るとスランプどころか観応えもちゃんとあって、ただし当時あまり評価されず、後世スランプ期とされたのはサイレントとトーキーの過渡期的な内容だったからでしょう。題材、脚色、演出、撮影、また俳優たちの使い方でもそうで、原作選びと脚色の次元でもありますが舞台背景に奥行きがなくキャラクターも類型的になっています。サイレント映画ではそれが作品世界のリアリティに貢献し類型以上の効果を発揮しもしますが、トーキー作品では類型がそのまま類型として顕れてしまい映画の広がりを制約してしまう。『瀧の白糸』の焼き直し(同じ泉鏡花原作だから似てもきますが)のような『折鶴お千』がサウンド版サイレントの成功作で、より面白くなるはずの題材のトーキー作品『マリアのお雪』が『折鶴お千』ほどは情感の深い作品にならなかったのもこの題材は本来サイレント向きで、仕上がりにサイレント臭さが残るトーキー作品になっているからでしょう。最初からそう観れば、本作はほとんど観られないサイレント時代の溝口作品を知る手がかりにもなる興味があります。
●2月17日(土)
『虞美人草』(第一映画社嵯峨野撮影所/松竹キネマ'35)*73min(オリジナル75分), B/W; 昭和10年11月31日公開 : https://youtu.be/VTeFgyMhB9s


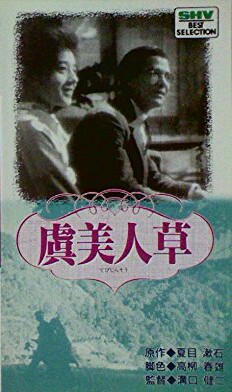
○あらすじ 大学の助手小野三郎(月田一郎)は恩師の娘小夜子(大倉千代子)という婚約者がありながら、英語の教師としてかよっている甲野家の娘藤尾(三宅邦子)の色香に迷ってしまう。驕慢な藤尾は兄欣吾(武田一義)の親友宗近(夏川大二郎)という婚約者がいたが彼を嫌っていた。藤尾の激しい情熱と藤尾と結婚させようとする藤尾の母(梅村蓉子)の共謀に負けそうになった小野は、小夜子との縁談を断ろうと決心して友人浅井(根岸東一郎)に使いを頼むが、宗近の忠告によって理性をとり戻す。小野を失い、宗近にまで去られた藤尾は、毒をあおって生命を断つのであった。夏目漱石名作の映画化。
(津村秀夫『溝口健二というおのこ』長崎一編・溝口健二監督作品総リストより)


いや、明治ものとはいえ『瀧の白糸』『折鶴お千』のようにはいかなかったのは心底メロドラマ作家だった泉鏡花原作と醒めた意識のメロドラマである『虞美人草』の違いか、戦後でも現代作家原作の『雪夫人絵図』'50(舟橋聖一原作)、『お遊さま』'51(谷崎潤一郎原作)、『武蔵野夫人』'51(大岡昇平原作)がいまいちで、次の『西鶴一代女』'52から古典を原作にした傑作が次々生まれたのを見ても、溝口には題材と効果がねじれている現代文学のあり方がうまくつかめなかったのではないか。一見本作は原作小説に忠実な映画化に見えます。映画が小野の婚約者・小夜子(大倉千代子)と小夜子の父で小野の恩師との談話シーン(とフラッシュバックによる恩師の小野が苛められっ子の貧乏学生時代に邂逅した時の回想。回想内で二重のトランジション・ショットがあり、回想の回想になっています)から始まり、後は藤尾の母が藤尾に荷担して宗近の親に婚約解消させようとする陰謀、小野が友人浅井に頼んで小夜子との婚約解消しようとする失敗と藤尾の兄欣吾(武田一義)の怒り、などなど類型的な周辺人物ばかりが予想される通りに動いて、藤尾は座敷で花を生けているだけだったりするのも原作通りです。デート場面などもそうですが、『マリアのお雪』と同じくセット撮影ばかりでかつカットをあまり割らないため人工的な効果は出ていますが、適度に飛躍的なカットを挿入するなり適切なロケ撮影でムードを切り替えるなりといった変化に乏しい。原作小説ではやはり藤尾は登場シーンが少なく大した行動はしないのですが、耽美的な文体で長々と藤尾の情念を描いていて義理や世間体がどうあろうと小野をものにしてやる、と粘っている藤尾の執念が周囲の人物を踊らせている図式はわかる仕組みでした。しかし映画では原作小説の耽美性による説得力を描くには原作にないエピソードの追加による三宅邦子演じる藤尾の魅力の強調が必要だったように思えます。それも誰もが読んでいる漱石の『虞美人草』となると創作エピソードは難しかったか、原作小説の設定通りの人物配置を次々描いていく、その結果最初は小夜子がヒロインであるような始まり方をして実はそうでなく、実は、と人物たちを順ぐりに描いていき、藤尾の母を演じる梅村蓉子の達者な策謀家ぶりとか小野(月田一郎)のぼんくらぶりに勝る友人浅井(根岸東一郎)のうすのろぶり、藤尾が嫌がる理由が弱いほど明らかに小野よりいい男の宗近(夏川大二郎)など小夜子役の大倉千代子が可憐で藤尾役の三宅邦子も単に一途なだけに見えてくるとなると、結局真に責められるべきは優柔不断で事態をややこしくした小野なのではないか、と思っているうちに原作の藤尾は服毒自殺して終わります。これがどう描かれるかで映画がうまく決まるかと言っていいと思いますからまだ観たことのない方がたの楽しみのために具体的に触れるのは止めておきますが、これは苦心した結果こうした描き方になったのか。それともどうせ原作準拠と思って観る観客相手だからと投げ出してしまったのか。結末で決めてみせる前に力尽きてしまったのか。これはこれで決めたつもりなのかよくわからない。脚本段階からこうだったのか演出効果からこうなったのかもよくわからないのですが、次作の会心作『浪華悲歌』の見事な締めを思うと本作では溝口の切歯扼腕が見えるようで、構想はすでに溝口自身が原作の次作に飛んでいたのかもしれません。また明治もの映画としては本作は本作なりによくまとまった出来で、もし2時間前後の長さをかけてよりじっくりと描かれていたらもっと良かったのにと思われる作品でもあります。