映画日記2018年11月7日~9日/サイレント時代のドイツ映画(3)

本題のドイツのサイレント時代の映画ですが、ドイツは開国以来日本と関係の深い国で狭い国土や地方分権制度からの中央集権化まで政治体制的にも類似した歴史を持った国でしたが、完全な内陸国と列島国というまったく対照的な地誌的条件が対照的でもあれば似通った面もある文化を作り出した、とも言えます。孤立した列島国の日本では外来文化はひとまず片っ端から摂取せねばならず自国向けの加工産出はそれからで、一方国境の向こうは他国だらけの内陸国ドイツでは農林水産業のうち水産は河川・湖養殖か輸入頼りで農林は奮わずとにかく輸出入が産業の基本になったので、日本もドイツも別々の理由から文化もナショナリズムと無国籍性の混淆した何だか変なものになったので、この時代のドイツ映画の強みは他のヨーロッパ諸国はもちろんアメリカ映画ですら作れない、極端に実験的な映画を娯楽映画の枠組みで平気で作ることができたことでした。むしろ実験性そのものがドイツ映画の売り物になる娯楽的要素だったので、輸出率が高かったために今日でも現存する代表的作品で'20年代ドイツ映画をたどれるのは羨ましいことで、映画輸入国ではあっても輸出国ではなかった'20年代日本映画が散発的にしか残っておらず、数少ない現存作品を観る限り当時の日本映画の水準も国際的なレベルに達していたのが認められるのを思うと、これらのドイツ映画に対応していた日本映画が漠然と想像される("イマジナリー・ライン"うんぬんを難じるイメージの貧しい観点では見えてこないでしょうが)のです。
●11月7日(水)
『ゲニーネ』Genuine, die Tragoedie eines seltsamen Hauses (監=ロベルト・ヴィーネ、Decla-Bioscop'20.9.2)*44min(Fragment & Abridged), B/W, Silent; 日本公開大正11年(1922年)10月20日(尺数不詳) : https://youtu.be/1agMYcNNJPY


[ 解説 ]「カリガリ博士」と同じく原作はカール・マイヤー氏、監督はロベルト・ヴィーネ氏である。場面構成、背景、演技等すべて表現派様式を取り入れたもので、主演は「マダム・ルカミエー」等出演のドイツ名優フェルン・アンドラ嬢である。無声。
[ あらすじ ] ゲニーネ(フェルン・アンドラ)は美しい女であったが血液宗教の女優であった為、血を欲求する女であった。彼女は奴隷市場でメロ(エルンスト・グロナウ)という風変わりな老人に買われ、篭の鳥の様に可愛がられたが血液に対する欲求が激しくなった。この不思議の家に唯一人出入りする理髪師グイヤード(ヨーン・ゴットウット)の甥フロリアン(ハンス・ハインツ・フォン・トワルドウスキー)はゲニーネを一度見て以来全く彼女の美に打たれ、彼女の命ずるままにメロを刺し殺した。メロの血潮に狂喜した彼女が、やがてフロリアンの血潮も彼女が欲する様になったのを知って彼は危うく逃れ帰ったが、その夜から怪しい熱病に犯された。メロの孫パーシー(ハラルト・パウルゼン)が久し振りにこの家を訪れた時、ゲニーネは彼に対して初めて恋を知った。パーシーの友人(ルイス・ブロディ)がメロの手記により彼女の素性を知り、真の人間に救いあげようとした時、失恋したフロリアンはゲニーネを殺し自分も相重なって死んだ。
――ドイツでは心理学・精神分析学が早くから発達したため(今日のような精神医学に変わるには脳生理学による脳内分泌物の薬物コントロールという「医学化」が必要でしたが)、実際に臨床治療を受診できるのは一部の富裕層でしかなかったこともあり、民間の心理学・精神分析学への理解は性的なニュアンスの強い変態行為=変質的嗜好者の判定・解明といった通俗的なもので、『カリガリ博士』や『ゲニーネ』はそういう観客の理解の次元に立った映画です。先に『他人とは違って』'19のような真摯に社会的偏見に抗議した映画も作られていたのをご紹介しましたが、『カリガリ博士』の「夢遊病者を実行犯にした殺人狂の存在を妄想して怯える精神障害者」、『ゲニーネ』の「人血嗜飲症の狂人の美女に魅了され破滅していく男たち」があんまりな設定なのは「マザーコンプレックスの青年が過保護な母親を殺して母親との二重人格が発現した時には女性嫌悪の殺人狂になる話」と同じくらい俗悪な心理学・通俗精神分析学の低俗化なのですが、映画では時代の思潮を反映した低俗な発想は俳優の肉体と映像の具体性によって説得力を持てば差し支えないのも事実です。『ゲニーネ』は企画・製作・撮影自体は『カリガリ博士』に先立って行われていたにしてもポスト・プロダクションは『カリガリ博士』製作・完成・公開後なので、撮影された素材に多少なりとも追加撮影し、編集による脚本構成の改変やアイリス、フィルター処理によって『カリガリ博士』の次作らしい作品に仕立てた映画でもあります。日本公開時にも本作は手法の不統一やテーマの分裂から『カリガリ博士』には及ばないものとされ、フリッツ・ラングは『カリガリ博士』でのヴィーネの功績と成功を称えながらも『ゲニーネ』の失敗を暗に着想の二番煎じとにおわせています。奇矯な老人メロとゲニーネの関係にカリガリ博士と眠り男チェザーレとの関係との対応があり、またゲニーネがフローリアンを籠絡してメロを殺させたあとはこの二人の関係が軸になるかと思いきや第3の男パーシーの出現でゲニーネは更正に向かうも、パーシーはゲニーネの正体を知った友人に警告され、失恋したフローリアンはゲニーネと無理心中する、と後半は吸血嗜好の異常性癖からテーマの離れた割と普通の破滅メロドラマになるので、テーマの分裂と手法の不統一を難じる評価はそこにあるとおもわれます。しかし悪趣味老人メロの隠居屋敷のこれでもかというくらい悪趣味な室内装飾(引きこもり小説の先駆、ユイスマンス『さかしま』1884の頽廃貴族青年の贅を凝らした地下室装飾描写の影響もあるでしょう)のインパクトと、それをとらえた現存プリントの鮮明な画質もあって、演出は『カリガリ博士』以前のヴィーネがドイツ映画のそれまでの主流だったという文芸メロドラマ路線の監督だった出自のわかる舞台劇映画風の平坦なものながら、ヒロインの吸血嗜好美女ゲニーネのメイクや衣装はのち'70年代末の女性パンク・ロッカーのスージー・スーやニナ・ハーゲンがそのまま真似たような、今時で言えばゴスの元祖を意図せずやっており、映画としての生の力は『カリガリ博士』よりもこちらの方が勝っているのではないかと感じさせる強引さがある。欠損部分を字幕やスチールで何とかつないだ短縮版なのも映画の未完成感を強めているのですが、良くも悪くもきちんとまとまっている『カリガリ博士』以上に扇情的で猟期性が露わで、変な映画を観た印象が尾を引くのは出来をうんぬんできる次元ではない不完全版映画の『ゲニーネ』の方なので、本作が修復復原版が作られて初DVD化されたのは2014年とごく近年のことで、これを公開時に観たラングや田中純一郎氏(『日本映画発達史』)が失敗作と片づけたのもわかりますが、今観てもなお面白い俗悪な楽しさはヴィジュアル面だけ取っても『ゲニーネ』の方にあります。それは本作がより冗長で散漫な完全版プリントで残されていたとしても変わらないと思われるのです。
●11月8日(木)
『巨人ゴーレム』Der Golem, wie er in die Welt kam (監=パウル・ヴェゲナー/カール・ボエゼ、UFA'20.10.29)*87min, B/W, Silent; 日本公開大正12年(1923年)10月26日(63分版) : https://youtu.be/ArHM_UArtPI (English Version)


[ 解説 ] 表現派映画の一偉彩である。(無声、五篇)
[ あらすじ ] 昔ある都の一偶ゲトという一区域にユダヤ民族が囚われ既に大虐殺に遭おうとした時一族の博士の頭たる男(アルバート・シュタインリュック)がゴーレムという不思議な土偶を創造し其に生気を与え其の都の王(オットー・ゲビュール)を救わしめ一族の解放を得た。その祝賀の宴の最中に博士の下僕(エルンスト・ドイッチ)がゴーレムを悪用した為、ゴーレムは手のつけられぬ乱暴を演じた。しかし無邪気な子供の悪戯から不図ゴーレムは生気を失い一族は事なきを得た。
――実際の映画があっけないものなのでゴーレム製作の試行錯誤や娘ミリアムと騎士フローリアンの恋など絡めても仕方のないようなものなので、本作はゴーレムに扮したパウル・ヴェゲナー(泥人形だから全身白塗りで体と一体化したような分厚い白塗り衣装を着ています)の元祖ゴーレムぶりを楽しめばいい映画で、ゴーレム製作過程まではともかく、ゴーレム製作完成以降はゴーレム不在の場面はつなぎみたいなもので、最小限のドラマ要素しかないのも仕方ないでしょう。『カビリア』の超巨大セットとエキストラの物量作戦は超巨大セットを建築できるだけの巨大オープン・スタジオを建設できるイタリアの日照に恵まれた気象条件に支えられていましたし、ほとんどが田舎の雪山場面に目まぐるしい機関車のモンタージュで占められた『鉄路の白薔薇』は超スローテンポのシンプルな父子義娘の三角関係ドラマに超高速モンタージュ(ほとんどフィルムのコマ単位)の偏執的な映像技法の徹底自体が見所でした。『カリガリ博士』とともに映画史上ホラー映画の創生の役割を果たしたとされる『巨人ゴーレム』は、巨人と邦題こそあれ製作者のラビよりは大柄なもののラビの助手や騎士フローリアンのような長身の男性と背丈は同じくらいですが、泥人形ですから体幹が太く衣装が一体化しているので肥満ではなく全身が寸胴型で、カリガリ博士が催眠術による夢遊病者の操作殺人者ならばこちらは古代ユダヤ律法の信仰能力による人造人間の製作というアイディアで、名作『フランケンシュタイン』の雛型にもなればデュヴィヴィエ版の続編をヒントに日本版ゴーレムの『大魔神』三部作(大映'66)という、これは本当に迫力のある名作を生みました。また胸元に手のひら大の五芒星(ペンタグラム)がはめ込まれると命を得る、外されると泥人形に帰るのも愛嬌のあるアイディアで、城門中で大暴れしたあと城門を開けて外に出て、子供たちが草むらの中で遊んでいるのに歩み寄る。分別のつく子供たちはみんな逃げ出すがあどけない幼女だけがぽつんと残って、向き合ったゴーレムに手に握った玉(果実?)を差し出してにっこりする。ゴーレムの表情が少しだけ和らいで幼女を抱き上げ、幼女はちょうど目の前の五芒星を抜き取ってしまう。ゴーレムは硬直して幼女はすとんと落ち、そのままゴーレムは倒れる。発見した民衆がゴーレムのまわりに集まって祝い、五芒星がアップになってエンドマーク、と、実に素朴な伝承説話のような話です。構成面ではホラー映画の源流でしょうし映画史上最初の人造人間もの、感情も感覚も疲労もない人造人間の創造の着想という意義も大きいですが、ゴーレム出現以降はゴーレムだけに目を奪われるのは映画としては真っ当な作りですし、胸元の五芒星が唯一のパワー源というのもさまざまなヴァリエーションを生んで無数の後継作品に転用されるアイディアです。『カリガリ博士』同様「最初に」画期的なアイディアを広めた作品という意義が大きく、ニューヨークのユダヤ系移民地区ではイデッシュ語(ユダヤ語)字幕版の特別上映が歓迎されたそうで(移民一世にはイデッシュ語しか話せない世代もいる時代でした)民族的な意義もあるでしょうが、本作は表現主義的なハッタリよりも民話的な素朴さに本来の良さがあるような小品と見た方が正当でしょう。
●11月9日(金)
『彷徨える影』Das wandernde Bild (監=フリッツ・ラング、May Film'20.12.25)*67mins, B/W, Silent; 日本未公開 : https://youtu.be/KgojfUY276w

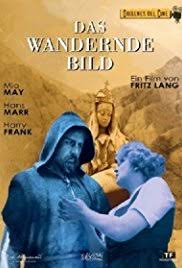
第2部後半はダイナマイト犯で雪の岩山を警官に追われるジョンの逃亡追跡劇と、山小屋からの救助活動がパラレルで描かれ、救出された二人は山頂に追いつめられたジョンに投降を呼びかけるため駆けつけますが、ジョンはゲオルクに襲いかかり格闘中に足を滑らせて山頂から転落死します(この兄弟は一人二役ですが、この格闘シーンは山頂という仰角の構図にロングで代役を使ってうまくこなしています)。ゲオルクは山小屋に戻り、ヒロインは夫の実家に戻ります。吹雪の日に実家の義妹は嵐の晩に難産で産褥で亡くなり、赤ちゃんだけでも避難させましょうと新生児を里に届けるため嬰児を抱いたヒロインの山を下りる姿が、ふと山小屋から出た主人公には「マリア像が動いた」奇蹟と見えて主人公も里へ下りハッピーエンドになり、当時の映画の宣伝資料から採られた愛の奇蹟を祝うシノプシス字幕で映画は終わります。何だか無理矢理こじつけたような帳尻合わせのような結末ですが、北欧映画に流行していたキリスト教的神秘主義のドイツ表現主義版かもしれません。本作からラングはおたがい再婚同士の夫人、テア・フォン・ハルボウ(1888-1954)との共同脚本でドイツ時代最後の『怪人マブゼ博士』'32までの全作品を作るようになり、本作が女性映画になったのも、これまで自作脚本ばかりで映画を作ってきたラングにとってハルボウとの脚本で新しい試みをしてみたかったのでしょう。本作はもともとフラッシュバック構成だった映画が、欠損部分のシノプシス字幕補填によってなおさらわかりづらくなってしまった不運がありますが、当時のドイツ映画としては画期的にロケーション撮影が多く、バイエルン・アルプスの雪山や湖が鮮明な画質とあいまって素晴らしい効果を上げており、'30年代ドイツの山岳映画や'50年代ドイツの郷土映画の先駆を指摘されてもいます。身近では主人公が全盲になってスイス山中に隠居生活を送る『鉄路の白薔薇』第2部「白の交響楽」に先立つもので、ラングとガンスの影響関係はまったく考えられませんが、本作きりで組んだ名カメラマン、グイード・ゼーバーの手腕が大きいでしょう。ドイツ映画が生んだカール・フロイントとルドルフ・マテの2大カメラマンも日差しに乏しいドイツ映画の室内セット撮影に対応したカメラマンでしたから、本作きりのゼーバーの起用はまさに千載一遇のチャンスでした。室内セットでは逆光の照明が多いので人物の表情が暗いのは『死滅の谷』以降ますます目立つ技法になっていきます。本作がラングの表現主義映画という定着した評価はタイミング的には該当するでしょうし、ストーリーからは感じられますが、映像作品の実物を観ると表現主義っぽさは飛躍の多さから来る偶然の産物からの印象ではないか、と思えます。バイエルン地方はカトリックだからマリア像があるのですが、自由恋愛主義者の主人公がマリア像に誓いを立てるというのは挫折感のすえとは言え飛躍がある設定上の無理もあります。もっともドイツ表現主義映画の大半は本質的には題材や物語はそれほど重要ではありませんし、本作は犯罪や過去の因縁絡みとは言え異常性を描いた映画ではないだけ良識的な作品です。ラングとしてもデクラ社ではなくヨーエ・マイの独立プロでマイ夫人を主演に作った映画だからこそできた意欲作だったはずで、完全版だったらもっと良い作品だったか、あるいは冗長な仕上がりだったのかわからないのがもどかしい映画ではあります。