市島三千雄の詩(前編)
角川文庫『現代詩人全集第二巻・近代2』(昭和37年=1962年4月15日刊)
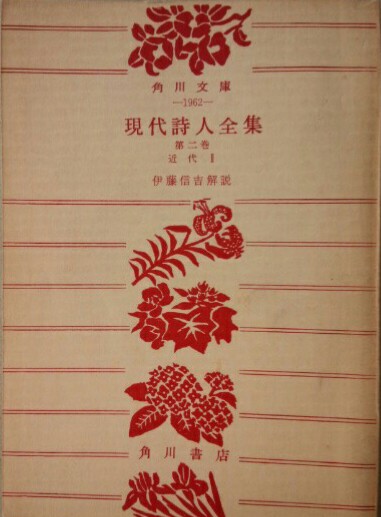
(市島三千雄<明治40年=1907生~昭和23年=1948年没>)

市島三千雄(明治40年=1907生~昭和23年=1948年没・新潟生れ)は詩誌「日本詩人」への投稿詩を萩原朔太郎に見出だされてデビューした詩人です。新潟商業中退後、家業の洋品店を経営しましたが、その後上京。大正14年(1925年)2月に詩誌「日本詩人」への投稿詩が萩原朔太郎の推薦で入選、「市島三千雄は一種の天才である」と賞賛を受けました。その後新潟の詩友と同人誌「新年」を創刊。大正15年(1926)年8月以後は同誌への発表が中心となります。これがかつて知られていた市島の全履歴になります。角川文庫『現代詩人全集第二巻・近代2』(昭和37年=1962年4月15日刊)に収録された11篇・15ページが最初にまとめられた市島三千雄集で、その後発見された初期詩篇2篇が長い間全作品とされてきました。萩原をして「一種の天才である」と言わしめたデビュー作「ひどい海」「あしくくたばる」の2篇が名高く、萩原は市島独特の泥臭さに惹かれたと思われます。
その後長い間市島三千雄は忘れられた詩人になっていましたが、平成3年(1991年)に郷土の詩人・樋口恵仁によって全19篇(初期詩篇3篇・後期詩篇5篇を角川文庫版に増補)の『市島三千雄詩集』(越後屋書房・7月15日刊)が私家版で刊行されました。以後新潟での郷土詩人としての盛名が高まり、新潟の詩人・齋藤健一氏を中心とした「市島三千雄を語り継ぐ会」が起こり、平成29年(2017年)には同会によって新たな私家版『定本市島三千雄詩集』(喜怒哀楽書房・11月10日刊)が刊行され、翌平成30年(2018年)には「ひどい海」を刻んだ詩碑が建立されました。角川文庫版に収録されていたのは「日本詩人」へのデビュー作(大正14年=1925年2月)から同人誌「新年」に発表された無題詩の最終作(昭和2年=1927年7月)までの2年半、市島の18歳から20歳までの作品で、『市島三千雄詩集』に追加されたその後の詩篇も5篇のみですから、41歳の逝去まではほとんど詩作はなく、2年半のみに集中して作品を発表したことになります。初期作品で早くから知られた2篇と角川文庫に収録された11篇を前後編にわたってご紹介したいと思いますが、山村暮鳥が亡くなった直後、八木重吉の短い詩歴とほぼ同時期、大手拓次が詩集の刊行がかなわずほとんど知られずに同人誌発表を続けていたのと同時期に、詩の表舞台とはまったく関わりなく特異な詩作をごく短期間だけ綴っていた存在として、ひっそりと読み継がれるにふさわしいような作風の詩人です。同時代との詩との関連は次回にして、まず大正15年12月までの作品(これでちょうど前半相当)をご紹介します。
*
「痩せてゐて悪知恵がある」
市島三千雄
痩せてゐる
其の上惡知恵があつて
母はいつも泣く
上等なペンと時計を賣つてくれた
試験の點を言はれてのち、一時間の課業をつぶして
先祖代々の履歴をぬいて、母をぬいて先生にしかられて
其の意氣を持つて其の意気を持つて
此の暴風(あれ)た堤を横にくたばれ
貧弱に痩せてくたばれ。
「屋根と夕焼け」
市島三千雄
うわさの中に私はいました
だまつてまた自分をうわさしながら私もいました
どうとうわさが笑ひました
みんな好氣な眼で人氣を一層あげました
色々の口が同んなじうわさをしました
黄色い石の三角のピラミッドが
赤く埃をまく口のように並んだ瓦の屋根――
無数の口とこの夕焼。
「ひどい海」
市島三千雄
雨がどしや降ってマントを倍の重さにしてしまうた
つめたい雨が一層貧弱にしてしまうた
波がさかさまになつて
廣くて低い北国が俺のことを喜ばしてゐる
臆病なくせにして喜んでゐる
なんと寂しい。灰色に火がついて夕方が来たら俥(くるま)が風におされて中の客はまたたく間に停車場に来た
貧弱が一里もちよつと歩んでしまうたら
靴に水が通って氷るやうで
貧弱が泣きそうになつてひどい海からの風を受けなければならなかつた
おつかないおつかないと北國をこはがつた
白いペンキが砂に立つて。その燈臺がたふれさう――
日本海が信濃川を越えた
漁獵船の柱が河上へ走つた
あれもこれも貧弱に北の冬に負けてゐる
その内俺は泣いてしまつてあやまつたあやまつたと風にお許しを請うた
うすい胸が風に壓搾されて死ぬよな気持が俺を一層と弱蟲にさせた
北国は殺すとこだと自らに故郷をいやがつた
貧弱に貧弱に痩せてぼんぼん泣いてしまうた
(「日本詩人」大正14年=1925年2月)
「あしくくたばる」
市島三千雄
ねむい野原に
樹は青いいきれた臭氣をはなつて
三角にあばらの出た俺はむせてむせて窒息の状となつてしまうた
しなだれかかる草の上に病氣的胸を延ばして
ひからびる真似をした蛇が中毒意見をトグロ形に巻いてしまうた
なんて醜い権化だらう
日も乾いて湖水の蒸気が上つて
ガマノホも。蘆。藻はものうい戀愛を粗末に無視してしまうた
「抱き合うたあと」の疲れで瞼(まぶた)を重もうして
日影生の毛髪をさらす
あついいきれの午前についきんちやうを切らして――
片方の足は延ばし他はちぢめて
永遠に痩せつつ見にくく痩せて
とび出る目玉をとぢて
ネッキストの濃艶
女蛇を夢むやう。可愛さうあばらを刺して
ああ縊死(いし)、縊死のためにつひつひ縊死をしてしまはう。みにくい下品に顏反(そむ)けられる程
痩せて痩せて乾物とならう。
(「日本詩人」大正14年=1925年2月)
「●無題(燈臺も…)」
市島三千雄
燈臺も気象台も人々を逍越してゐるから
そして二人共長く離れて砂丘にある
赤い旗は象形文字的であるし船に見せてゐる
漁師は同化(な)れてゐるから無意識である
砂丘は広大で赤い旗が動くばつかりで気象台は西洋館であるし
濱は、ペンキで明るさが一層良くなる
濱は旗で、防波堤より寂しくなるのである
遠くから見てゐるそして下りて上るのである
焼場の黄ろい煙が風になって來るのであるし郭と港が連鎖して赤い報告機は何もならない
砂よけ塀が長城となるし
砂丘が月の脈で
晝となると廃物となるのである
鴎は砂丘が嫌ひで他に何も居無いで浜丘は風が有る
雲はいつも港に來てしまふのである
雲は空の半面に席を置くのであるし防波堤が一里も出る
皆んな突堤に出てしまふ突堤にかたまつてゐる小さくやっと見える
気象臺の旗は無用なのである晴天であると實に動くのである
砂丘が變化無しにつづいてゐる
トロンコの線路が町のはじにある
駄菓子屋が気象臺の麓にやつとある旗は浜を寂しくするし草の音を生かすのである砂丘は眩(まぶ)しい程光らないのである気象臺は遠くにある。
(「新年」大正15年=1926年8月)
「●無題(開場の…)」
市島三千雄
開場の挨拶と共に山の中間につまらないものひらいて
その「くわらつ」としたのも後になる
惡い少女は丸いものを上る
其處は転(ひつ)くり返つたのである
自分の所有物の處分に困つて居るどころかもう歸つてきた様子を規めてゐる
地球儀全體が秋なのだらうかが箒草の中を入つて行つて方向を變へて南から北へ出てしまふ
帰つて來たとによつこり顔を出す
ぢや無い矢張遠くの陸の上僕に見えない
地圖を廣ろげてから街へ行かう
惡い少女はほんたうの晴着をきて立つたのである
山から海岸へ、髪を氣にして「くわらつ」とした明るい庭へ走つて行くのは夏季時の惡い少女だつた
玉を少女は行つて海の飛台は下へ行つて秋浪に被(かぶ)りさう
宇宙へ落ちてしまふ氣
暫(しばら)くの間海を忘れる
萬億の中の一人ぼつちを見る
一面の甘蔗原(かんしやばら)の中と天を見上げての差違と
それから又オーストラリアへ來てしまつた
惡い少女はズボンをはいて「ぱつつり」躰で悪い爲の労働をする
中央の湖、水溜りを見下して變つてゐるやうな氣がしてならない
日本の岸に見える白い鹽水
どうして鹽水に蝶の卵が孵化するわけがない其の儘にして置いて水が動いてゐる景色
夜もあり昼もある
日本の蟲卵と蟲卵をくらべる
枝についてゐるのを見てゐる
明けなのだらうか暮れてゐるのだらうか。
(「新年」大正15年=1926年10月)
「●無題(誰の為に…)」
市島三千雄
誰の爲に生まれて來た乙女
秋風に點が進んで遠く行きに追って行く
皆んながこのことを話してくれない
客觀の中に入つて咲いた薄紅
生きてゐる乙女のうなじ
氣分の中に實(みのり)が、にすかしてグラウンドのトラックが、なぜ乙女は口を窄める
或る時は高樓街道路を見下ろせば片隅に歩んでゐる乙女
一面に向つて石を敷く都市進行計畫
上から郊外付近を写した写真
やつぱり郊外の秋だつた
こんな物質は見えない
なぜ陽はてらない、覗き込む奥底の道路に疎(まば)らの我が家があるとは
僕は泣きつつも飛び出したし
地球の晴れ晴れしてゐるのを知つてゐるのに
赤い切れの乙女がいい
此の時土臺の傾いた家の一族のひつそり
土の文明に對するをどうしよう
僕は歩んでいくだらうに力める
秋風と緑野(リヤノ)の獵地の異國
あの乙女とは何んだらう
僕は斷定が好き
箱を積み上げた無意識から生じた
をさまりかえつてゐる都會
僕は都會と何んとも思つてゐない
底にあるのが何であらうば
動けないものなんか
(「新年」大正15年=1926年11月)
「●無題(私生子は…)」
市島三千雄
私生子は眞白ろけで下品でない
弱蟲であるから性欲が無い腰が細くて着物は袋なのである
私生子は何時とは知らず自分の話を知つてしまふのである
偉いから泣かないそして自分ばつかり思つてゐる。母には一度も言はないのである
母が啜つて泣いたし着物に樟腦の香ひがしたから私生子は黙つてしまふのである
そして母と子の間が瑞々しくて母は少しも訓へない
私生子は蟲の様なのである
夜時々眠られない目がさえてしまふ自分の存在がわかつてやつとのことで寝てしまふし
沈黙で私生子に視られたから系統の話は大嫌ひなのである
結婚することが出來なかつたから私生子は移轉するそして行衛知れずになってしまふ
母が氣が利いて居たけれど相手にされぬよな氣持がしたし
私生子は田舎が駄目であつた
何處へ行ってしまふかわからないそして家が残つてしまふのである
何時もぼんやりとしてしまふし金を貯蓄する勇気が脱けて苦學する體力が缺けてゐる
私生子は永久的であつたから母がいつも黙つてゐる親類が無かつたし世間の人は金の送られる場所が不明(わから)ないのである
一軒家の様でもあるし赤ん坊の爲家が暴(あ)らされる事が無い閑(ひっそり)して歌聲がない
私生子はどうしても都が故郷なのである
子供が大きくなると引つ越してしまふしどうなるかわからない
幽靈の様で手紙もよこさない
移轉した跡は清潔なのである
皆んなはこのことを知つてゐないのである
私生子は「しっかり」して物事に周章(あわ)てないのである
敷地は湿つて居ないのである
(「新年」大正15年=1926年12月)
(以下後編)
(旧稿を改題・手直ししました)