伊東静雄詩集『わがひとに與ふる哀歌』(昭和10年=1935年刊)その3
(伊東静雄<明治39年=1906年生~昭和28年=1953年没>)

前回ご紹介した杉本秀太郎『伊東静雄』(筑摩書房・昭和60年=1985年刊)は1冊を費やして伊東静雄(明治39年=1906年12月10日生~昭和28年=1953年3月12日没)の第1詩集『わがひとに與ふる哀歌』全編の注釈に徹しており、同書が講談社文芸文庫で再版されたおり(平成21年)、新たな「あとがき」で著者自身が簡略に『わがひとに與ふる哀歌』の特色をまとめています。くり返しになりますが、杉本氏のあとがきはややこしい内容を平易な語句と文章で解き明かしており、小林秀雄以来の迂遠で晦渋な文学批評の主流に対する批判的姿勢もうかがえるものです。
「伊東静雄の詩集『わがひとに與ふる哀歌』は極端に対照的な二つのタイプの詩を包んでいる。高吟にふさわしいような漢文調の詩、ぶつくさとつぶやくような平俗な口調の詩。そしてその両極端の中間を占める詩には、フーガのような趣きを呈するもの、ドイツリートのような短くて声のよく透るもの、バラードのような語り物がまじっている。」
杉本氏によれば、『わがひとに與ふる哀歌』全28編は<私>と<半身>(巻頭詩「晴れた日に」参照)の二人に分かれた「擬作者」を語り手としており、各編の語り手は以下のようになります。
1. <私>晴れた日に (「コギト」昭和9年=1934年8月)
2. <半身>曠野の歌 (「コギト」昭和10年=1935年4月)
3. <半身>私は強ひられる―― (「コギト」昭和9年=1934年2月)
4. <半身>氷れる谷間 (「文學界」昭和10年=1935年4月)
5. <私>新世界のキィノー (「呂」昭和8年=1933年7月/「コギト」昭和8年=1933年9月)
6. <私>田舎道にて (「コギト」昭和10年=1935年2月)
7. <半身>眞昼の休息 (「日本浪曼派」昭和10年=1935年4月)
8. <私>歸郷者 (「コギト」昭和9年=1934年4月)
9. <私>同反歌 (旧題「都會」/「呂」昭和7年=1932年10月)
10. <半身>冷めたい場所で (「コギト」昭和9年=1934年12月)
11. <私>海水浴 (「呂」昭和8年=1933年11月/「コギト」昭和8年=1933年11月)
12. <半身>わがひとに與ふる哀歌 (「コギト」昭和9年=1934年11月)
13. <私>静かなクセニエ (初出不明)
14. <半身>咏唱 (旧題「事物の本抄」第9連/「呂」昭和7年=1932年11月)
15. <私>四月の風 (「呂」昭和9年=1934年6月)
16. <半身>即興 (「椎の木」昭和10年=1935年4月)
17. <私>秧鶏は飛ばずに全路を歩いて來る (「四季」昭和10年=1935年4月)
18. <半身>咏唱 (旧題「朝顔」/「呂」昭和7年=1932年10月)
19. <私>有明海の思ひ出 (「コギト」昭和10年=1935年3月)
20. <半身>(讀人不知) (旧題「秋」/「呂」昭和7年=1932年11月)
21. <半身>かの微笑のひとを呼ばむ (「日本浪曼派」昭和10年=1935年7月)
22. <私>病院の患者の歌 (「呂」昭和8年=1933年6月)
23. <半身>行つて お前のその憂愁の深さのほどに (「コギト」昭和10年=1935年6月)
24. <私>河邊の歌 (「コギト」昭和9年=1934年10月)
25. <半身>漂泊 (「コギト」昭和10年=1935年8月)
26. <私>寧ろ彼らが私のけふの日を歌ふ (「コギト」昭和10年=1935年1月)
27. <一老人>鶯 (「呂」昭和9年=1934年2月)
28. <一老人>(讀人不知) (旧題「静かなクセニエ抄」/「呂」昭和7年=1932年12月)
一見日本の現代詩では時代錯誤的な本格的なロマン派詩集の体裁に見えるこの詩集が、実際には半数あまりにロマン派批判の詩を含んでおり(巻末の「一老人」の述懐による体裁の詩は対立構造の瓦解を暗示して、疲弊感を漂わせます)、しかも半ロマン主義批判的な作品は昭和7年~8年の制作、ロマン主義的作品は昭和9年~10年の制作なのは当初伊東が反ロマン主義詩人として出発したことを示します。完成度の高い詩編は昭和9年~10年度のロマン主義的作品に多いので、詩集全体を読むと意図的に共感を阻む詩編が所々に配置されているのです。「新世界のキィーノー」など大阪・新世界の水商売の元締め(キィーノーは映画館の意)が朝鮮に左遷される元学友を肴して同窓生の飲み会で優越感に浸る、という内容を皮肉で即物的文体で描いており、こうした詩編が純度の高いロマン主義詩と併置されることで理念的世界と世俗的認識が一つの詩集の中で同居しています。
伊東は旧制高校(今日の大学に相当する)はドイツ語科、旧制大学(今日の大学院に相当)は国文学科生で、卒業後は一度の転職もなく病没まで中学校教諭を勤めました。伊東が現代詩人として出発した当初の同時代の最新のドイツ現代詩は反ロマン主義的な即物主義詩でした。伊東は反ロマン主義詩の世界から入ってロマン主義批判を経由したロマン主義詩に至る、という屈折した詩的試行錯誤を経て第1詩集にたどり着いたのです。その達成は三好達治よりも早く、中原中也にも立原道造にもないものでした。伊東の詩はいったん抒情的共感に導いておいて読者を突き放しており、中原や立原以上に自己完結的な自虐性を感じさせるのです。
伊東は詩人仲間との賑やかな交流も特になく、生涯を出世とも文化人扱いとも縁のない、いち中学校教諭として終えました。詩集刊行も約25年間に5冊きりで、詩の玄人の間で読まれていただけです。一般読者にも名声が高まったのは没後に詩集全5冊の合本詩集『伊東静雄詩集』が刊行されてからでした。同書は新潮文庫で版を重ね、現在ではほぼ同内容のまま岩波文庫で杉本秀太郎改訂新編版の入手が容易です。
全集に収録された伊東の日記や書簡には中原中也との邂逅、中原と立原道造の夭逝への見解、またデビュー当時の三島由紀夫に訪問を受けた時の嫌悪が記されており、大阪からほとんど出ない境遇にあって首都の文学界動向を冷ややかに見ていたのが伝わってきます。伊東は上京時に中原家に泊めてもらい丁寧な礼状を送ったようですが、中原中也没後刊行の中原中也全集の日記には「伊東静雄から礼状。真面目な手紙。唯真面目なだけ。かういふ人は何を考えてゐるのか。アイドントノウ」と、まったく気性が合わなかったようです。伊東は中原の夭逝には「中原はあれで十分。惜しかったのは立原」と立原道造の詩才の可能性の方を買っていたのも明らかになりました。少年時代から伊東の詩に心酔していた熱心な礼讃者で、この全集の刊行によって生前の面会時に伊東静雄から嫌悪されていたのを知った三島由紀夫は、生涯伊東へのコンプレックスを抱き続けることになりました。三島は完成後にクーデターと切腹自殺を予定した遺作の長編小説四部作『豊饒の海』(昭和44年~45年)の第1部を伊東の詩から『春の雪』と題したばかりか、最晩年のエッセイでももっとも愛読する詩として伊東の詩を上げ、「なぜ一介の中学教師が現代日本最大の詩人であったのか!」(三島は上流階級出身でした)とコンプレックスを露わにしていました。また伊東静雄は「コギト」や「日本浪漫派」の詩人・田中克己、蔵原伸二郎とは同世代で、作風にも類似点があるにも関わらず、積極的な接近は見られません。伊東ほどに注目すべき詩歴を重ねた詩人が孤立した境遇を四半世紀も貫いたのは、安易に打ち解けない頑なさと狷介さを感じないではいられません。
『わがひとに与ふる哀歌』(発行・杉田屋印刷所/発売・コギト発行所、1935年=昭和10年10月5日発行)
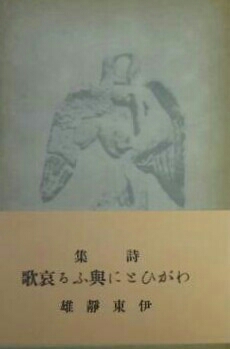
四月の風
私は窓のところに坐つて
外(そと)に四月の風の吹いてゐるのを見る
私は思ひ出す いろんな地方の町々で
私が識(し)つた多くの孤兒の中學生のことを
眞實彼らは孤兒ではないのだつたが
孤兒!と自身に故意(わざ)と信じこんで
この上なく自由にされた氣になつて
おもひ切り巫山戯(ふざ)け 惡徳をし
ひねくれた誹謗と歡び!
また急に悲しくなり
おもひつきの善行でうつとりした
四月の風は吹いてゐる ちやうどそれ等の
昔の中學生の調子で
それは大きな惠(めぐみ)で氣づかずに
自分の途中に安心し
到る處の道の上で惡戯をしてゐる
帯ほどな輝く瀬になつて
逆に後(うしろ)に殘して來た冬の方に
一散に走る部分は
老いすぎた私をからかふ
曾て私を締めつけた
多くの家族の絆(きづな)はどこに行つたか
又ある部分は
見せかけだと私にはひがまれる
甘いサ行(ぎやう)の音で
そんなに誘ひをかけ
あるものには未だ若かすぎる
私をこんなに意地張らすがよい
それで も一つの絆を
そのうち私に探し出させて呉れるのならば
(「呂」昭和9年=1934年6月)
即興
……眞實いふと 私は詩句など要らぬのです
また書くこともないのです
不思議に海は躊躇(たゆた)うて
新月は空にゐます
日日は静かに流れ去り 静かすぎます
後悔も憧憬もいまは私におかまひなしに
奇妙に明(あか)い野のへんに
独り歩きをしてゐるのです
(「椎の木」昭和10年=1935年4月)
秧鶏は飛ばずに全路を歩いて来る
秧鶏(くひな)のゆく道の上に
匂ひのいい朝風は要(い)らない
レース雲もいらない
霧がためらつてゐるので
厨房(くりや)のやうに温(ぬ)くいことが知れた
栗の矮林を宿にした夜よは
反(そり)落葉にたまつた美しい露を
秧鶏はね酒にして呑んでしまふ
波のとほい 白つぽい湖邊で
そ處(こ)がいかにもアツト・ホームな雁(がん)と
道づれになるのを秧鶏は好かない
強ひるやうに哀れげな昔語(がたり)は
ちぐはぐな相槌できくのは骨折れるので
まもなく秧鶏は僕の庭にくるだらう
そして この傳記作者を殘して
來るときのやうに去るだらう
(「四季」昭和10年=1935年4月)
咏唱
秋のほの明い一隅に私はすぎなく
なつた
充溢であつた日のやうに
私の中に 私の憩ひに
鮮(あたら)しい陰影になつて
朝顔は咲くことは出来なく
なつた
有明海の思ひ出
馬車は遠く光のなかを驅け去り
私はひとり岸邊に殘る
わたしは既におそく
天の彼方に
海波は最後の一滴まで沸(たぎ)り墜ち了り
沈黙な合唱をかし處(こ)にしてゐる
月光の窓の戀人
叢(くさむら)にゐる犬 谷々に鳴る小川……の歌は
無限な泥海の輝き返るなかを
縫ひながら
私の岸に辿りつくよすがはない
それらの氣配にならぬ歌の
うち顫ひちらちらとする
緑の島のあたりに
遥かにわたしは目を放つ
夢みつつ誘(いざな)はれつつ
如何にしばしば少年等は
各自の小さい滑板(すべりいた)にのり
彼(か)の島を目指して滑り行つただらう
あゝ わが祖父の物語!
泥海ふかく溺れた兒らは
透明に 透明に
無數な「しやつぱ」に化身をしたと
註 有明海沿の少年らは、小さい板にのり、八月の限りない干潟を蹴つて遠く滑る。「しやつぱ」は、泥海の底に孔をうがち棲む透明な一種の蝦。
(「コギト」昭和10年=1935年3月)
かの微笑のひとを呼ばむ
………………………………………
………………………………………
われ 烈しき森に切に憔(つか)れて
日の了る明るき断崖のうへに出でぬ
静寂はそのよき時を念じ
海原に絶ゆるなき波濤の花を咲かせたり
あゝ 黙想の後の歌はあらじ
われこの魍魅の白き穂波蹈み
夕月におほ海の面(おもて)渉ると
かの味気なき微笑のひとを呼ばむ
(「日本浪曼派」昭和10年=1935年7月)
(以下次回)
(旧稿を改題・手直ししました)